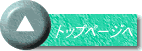画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。

画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。
〔209系直流通勤形電車関連の解説〕
209系電車
209系電車は、東日本旅客鉄道(JR東日本)の直流通勤形電車。
日本国有鉄道(国鉄)から大量に引き継ぎ、老朽化が進んだ103系の置き換え、
および、一部は輸送力増強用などとして、
1993年(平成5年)4月より京浜東北線・根岸線、南武線に本格投入された。
これまでの鉄道車両の製造・整備の方法を全面的に改めた新しい設計思想
(バリューエンジニアリングの手法)が採用され、
JR東日本では本系列以降の車両を「新系列車両」として区分している。
車両デザインは栄久庵憲司率いるGKインダストリアルデザインが手掛けた。
1993年度通商産業省(現・経済産業省)選定グッドデザイン商品(当時)金賞
ブルネル賞奨励賞受賞。
設計段階より廃車後のリサイクル計画が策定されるなど、
環境問題にも配慮した設計となっている。
0番台
1993年(平成5年)に登場した量産車である。
京浜東北線・根岸線用は同年2月15日より、
1編成が限定運用で営業運転を開始し、
3月1日より5本が本格的な営業運転を開始した。
一方、南武線用は同年4月1日より営業運転を開始した。
前面は踏切事故対策として骨組を追加して強度を向上させたほか、
スカートを大形化、運転室スペースを拡大、
運転台背面に非常救出口を設置した。
空気圧縮機にドイツ・クノール社製スクリュー式を採用し、
1 - 6次車は電動発電機 (MG) のような
甲高い動作音が特徴であるTWR70-012 CP.ogg 動作音(ヘルプ / リンク)。
運転席のマスター・コントローラーに左手操作のワンハンドル式を採用。
ドアエンジンは量産初期ロットでは従来と同じ日本製の空気式が採用されたが、
ウラ(浦和電車区の電略)16編成(3次車)から、
外国製の戸挟み安全装置付き電気式に変更された。
ドア開閉時のチャイムと、扉上部に3色LEDディスプレイによる
次駅表示などを行う旅客案内表示器を装備している。
また、先頭車には車椅子スペースが設置されたほか、
連結面に転落防止幌が設けられた。
画像番号FH0104.JPGの画像は、
209系 京浜東北線ウラ65編成
画像番号IMG 8811.JPGの画像は、
京浜東北線209系0番台
3100番台
八高・川越線の103系3000・3500番台を置き換えるために投入された番台区分である。
2005年(平成17年)4月17日から営業運転を開始した。
車体の帯の色は、3500番台と同様のオレンジ色とウグイス色である。
当初は全編成を205系3000番台(4両編成7本)で置き換える計画であった。
しかし、2004年(平成16年)10月16日ダイヤ改正において、
埼京線と東京臨海高速鉄道りんかい線の相互直通運転の拡大が実施され、
その際JR東日本では埼京線205系10両編成1本の車両増備が必要となった。
このため、205系3000番台の最終的な配置は4両編成5本に計画変更された。
この不足分を補うため、東京臨海高速鉄道70-000形全車10両編成化に伴う
編成組み替えの際に余剰となった70-000形の先頭車4両と、
中間車2両の計6両をJR東日本が購入し、
八高・川越線向け改造したのが本番台である。
不足する中間車2両については翌2005年3月に川崎重工業で新規に製造し、
4両編成2本の計8両を本番台とした。
りんかい線からの6両は、民鉄・第三セクター鉄道に在籍していた車両が、
JR車籍に編入された最初の例である。
元々東京臨海高速鉄道70-000形はJR東日本の209系を基本仕様として製作された車両であり、
制御機器類は共通で運用されている3000番台と同一仕様である。
画像番号DSC 6290.JPGの画像は、
209系3100番台ハエ71編成
画像番号CIMG0844.JPG・CIMG0848.JPGの画像は、
209系3100番台ハエ72編成
〔E231系直流通勤形電車関連の解説〕
500番台
2002(平成14)年から登場した山手線専用車。
前面デザインが変更され、情報提供装置(VIS)を搭載した。
車内のドア上には左右で2台の15インチ液晶ディスプレイを設置している。
左側の画面では次駅・乗換・所要時間・運行情報など列車の案内、
右側の画面では広告・天気予報・ニュースを表示する。
2010(平成22)年には、
山手線へのホームドア設置の関係で6扉のサハE230-501〜が廃車され、
代替の4扉車サハE231-601〜・4601〜が導入された。
画像番号IMG 9022.JPGの画像は、
E231系500番台トウ520編成 山手線
〔E233系直流通勤形電車関連の解説〕
E233系電車
E233系電車(E233けいでんしゃ)は、東日本旅客鉄道(JR東日本)の直流一般形電車。
2007年鉄道友の会ローレル賞受賞車。
1999年度から首都圏に大量投入されたE231系車両や、
2005年から常磐線中距離用に導入されたE531系車両の技術を、
ベースとして開発された車両である。
系譜としてはE231系車両の後継に当たる。
そのため、E231系によって置き換えられなかった通勤型車両の201系や205系、
近郊型車両の211系の置き換え用に主に製造されている。
製造メーカーは、東急車輛製造(2012年4月より総合車両製作所)、川崎重工業と、
JR東日本の自社生産工場である新津車両製作所である。
1000番台
京浜東北線・根岸線で使用していた209系の置き換え用として、
京浜東北線・根岸線向けの車両で、さいたま車両センターに配置されている。
2007年度(2007年9月)から2009年度(2010年1月)にかけて870億円を投入し、
10両編成83本(830両)が製造された。MT比6M4Tの10両固定編成のみが製造され、
2007年(平成19年)12月22日から営業運転を開始した。
本番台区分の投入により、車齢が若いものの機器の故障が多かった
京浜東北線・根岸線の209系は0番台の半数程度が廃車、
それ以外の0番台と500番台は他路線へ転用された。
0番台の機能に加え、新製時より209系と同様の超音波ホーム検知装置を、
先頭車前端両側に装備し、保安装置をD-ATCに変更したほか、
6号車のサハE233形1000番台の床下には非常用のハシゴを新設するなど、
安全性の向上が図られている。
ドアエンジンは0番台と同じスクリュー軸駆動式だが半自動機能は搭載されていない、
なお「3/4閉機能」スイッチが搭載されており、
輸送障害などの長時間停車時は使用することがある。
外観では、前面帯が前面窓下に配され、
列車番号表示器が前面窓の右下隅(向かって左)に設置されている点が0番台とは異なる。
客室内では、各ドアの上部に設置されている液晶ディスプレイが、
0番台やE231系500番台などの縦横比率 4:3 の15インチから、
16:9 の17インチワイド画面へ変更された。
座席モケットは路線カラーである青色をベースとした明るい色調とし、
背もたれの柄はバーコード風の長短の線を組み合わせることで「スピード感」と、
「モダンな都会」のイメージを表現した。座面も0番台に比べて改良されている。
209系0番台で6号車に連結されていた6扉車は、当初連結する予定だったが、
京浜東北線・根岸線のピーク時の混雑率が年々緩和されていること、
拡幅車体による定員増加、常時着席のニーズなどの面から本系列では、
連結しないこととなった。
また、編成両端先頭車は、すべての荷棚とつり革の高さを優先席と、
同じタイプの 50 mm 低くした。
ただし、2010年4月19日の女性専用車導入の際には、設定位置は中間の3号車とされ、
両先頭車とも選ばれなかった。
側面・前面の種別・行先表示器では209系500番台と同様に、
路線名と行先を交互に表示するが、
横浜 - 大船間の根岸線内では、京浜東北線内を走行しない磯子発大船行きも含め、
路線名は「京浜東北・根岸線」と表示される
(横浜駅以北では「京浜東北線」のみの表示)。
種別の背景色は各駅停車がスカイブルー、快速はピンクである。
また、0番台では西行の中野以西(土休日は吉祥寺以西)で、
快速列車では種別表示を行わないが、当番台では北行の田端以北、
南行の浜松町以南でも各駅停車に切り替えて表示を続ける。
側面の表示器は、快速のみ始発駅において全停車駅を表示するが、
「この電車の停車駅は、…(省略)…に停まります」と、
主語と述語の組み合わせが不自然で文法的に誤っている。
6000番台以降では修正されている。
3000番台も以前は文法的に誤っていたが、
上野東京ライン開業に向けた旅客案内表示更新により修正された。
画像番号IMG 8824.JPGの画像は、
京浜東北線E233系1000番台
画像番号IMG 1422.JPGの画像は、
京浜東北線E233系1000番台ウラ133編成
画像番号IMG 1424.JPGの画像は、
京浜東北線E233系1000番台ウラ146編成