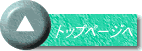画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。

画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。
CIMG1044 |
DSC_0032 |
DSC_0556 |
DSC_1148 |
DSC_7340 |
DSC_7394 |
DSC_9060 |
 FH0064 |
 FH0114 |
IMG_0020 |
IMGP0166 |
DSC_9174 |
1500番台(仙台地区用)
仙台地区715系1000番台置き換え用として、
1000番台の増備型として1998年と2001年に川崎重工業および、
土崎工場にて製造された。
クモハ701形+クハ700形の2両編成が18本(36両)が在籍する。
主変換装置は、インバータ部はパワートランジスタ素子であるが、
コンバータ部にIGBT素子を使用したものに変更された。
回生ブレーキを装備し、
クモハ701形は屋根上のブレーキ用抵抗器がなくなった。
2001年に新製された2次車の 1509 - 1518は、
新製時からATS-Ps保安装置を備えるほか、行先表示器が LED 式とされ、
トイレは車いす対応の大型のものを運転台直後に設ける。
このため、クハ700形の窓配置が変更された。
1508 は浸水事故で床下機器が損傷した
1000番台1編成(クモハ701-1033+クハ700-1033)を修理した車両で、
回生ブレーキと LED 式行先表示器を装備して復旧され、
1500番台に編入された。
全車が仙台車両センターに配置され(F500台編成)、
100番台(F2-106編成)・1000番台
E721系0番台(ワンマン運転対応のP40 - P44編成)と、
共通で使用される。車体帯色は赤+白+緑である。
画像番号IMG 0020.JPGの画像は、
701系1500番台2両、F2−501編成 普通2142M
画像番号DSC 9060.JPGの画像は、
701系1500番台2両、F2−503編成 普通2135M
画像番号DSC 7394.JPGの画像は、
701系1500番台2両、F2−504編成 普通2134M
画像番号IMGP0166.JPGの画像は、
701系1500番台2両、F2−506編成 普通2136M
画像番号CIMG1044.JPGの画像は、
701系1500番台2両、F2−510編成
試8535M 郡山出場
画像番号DSC 0556.JPGの画像は、
701系1500番台2両、F2−511編成 普通2136M
画像番号DSC 0032.JPGの画像は、
701系1500番台2両、F2−516編成 普通2138M
混合編成
画像番号DSC 9174.JPGの画像は、
701系1500・701系1000番台混合編成4両
普通1133M
F2−501編成+後2両F2−25編成
画像番号DSC 1148.JPGの画像は、
701系1500・E721系0番台混合編成4両
普通1142M
F2−503編成+後2両E721系0番台P−43編成
画像番号DSC 7340.JPGの画像は、
701系1000・E721系0番台混合編成4両
普通1137M
F2−508編成+後2両E721系0番台P−42編成
5500番台
山形新幹線開業に伴う奥羽本線の山形 - 新庄間の標準軌化に際し、
普通列車用として1999年に投入された車両である。
1500番台の仕様に準じ、座席はロングシート、
客用扉のステップはない。
車いす対応の大型トイレをクハ700形の前方に設置する。
行先表示器は LED 式で、
尾灯が5000番台と同様運転席窓の上部に設置されている。
回生ブレーキは発電ブレーキ車と混用しないため、
作動範囲が大きくとられた。
台車は標準軌用の DT63A 形・TR252 形で、
米沢 - 福島(板谷峠)の急勾配対策として、
ディスクブレーキや砂撒き装置を搭載する。
パンタグラフは製造当初は仙台地区701系との
互換性を考慮し菱形を搭載したが、
2001年にシングルアーム式に交換された。
加えて同時期に強化型スノープラウ(雪かき器)も設置した。
冷房装置はインバータ方式の AU723 形を搭載する。
719系5000番台と同じスカートを装着している。
クモハ701形+クハ700形の2両編成9本(18両)が、
山形車両センターに配置され(Z編成)、米沢 - 新庄間で運用されている。
車体帯色は山形県の花「ベニバナ」をイメージしたオレンジ+白+緑である。
全車両がワンマン運転に対応しているが、車掌が乗務することもある。
画像番号FH000114.JPGの画像は、
701系5500番台2両、Z−6編成 新庄にて、
画像番号FH0064.JPGの画像は、
701系5500番台2両、Z−9編成
画像番号IMG 0405.JPGの画像は、
701系5500番台4両、新庄にて、