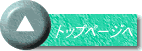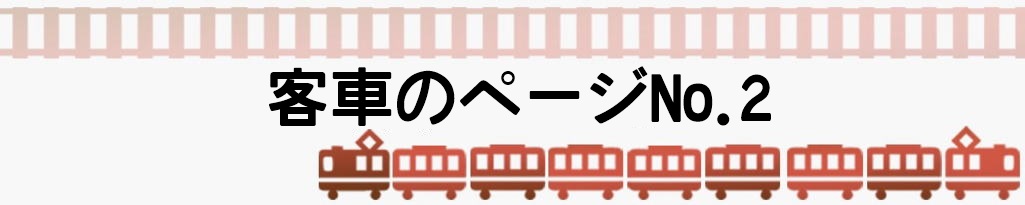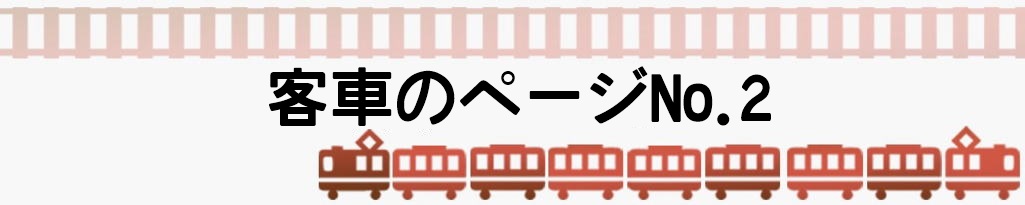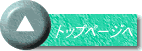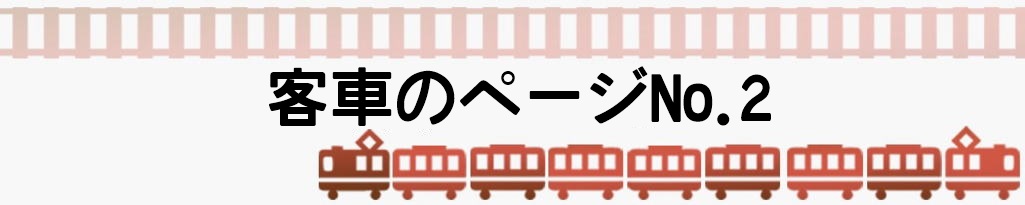
画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。

FH0006 |

DSC_0038 |

IMG_0368 |

IMG_0680 |

IMG_5785 |

IMG_5711 |

DSC_6036 |

DSC_8202 |
|
|
14系14形寝台車
車両の概要としては、特徴としては、B寝台車の内装が、
それ以前の標準寝台幅52cmを踏襲した20系客車と異なり、
B寝台車のベッド幅を581・583系電車で採用したのと同様の70cmと大型化し、
またユニット方式で内装を製造して車内に取り付ける形を初めて採用した。
また、寝台車のベッドの収納などを省力化するため、
中段寝台の自動昇降装置を初めて取り付けた。
形式はB寝台車のオハネ14形・スハネフ14形、A寝台車のオロネ14形、
食堂車のオシ14形が用意された。
A寝台車については、「プルマンタイプ」の開放式寝台車のみが製造された。
食堂車については、
電車・気動車の食堂車とほぼ共通の仕様となってコストダウンが図られた。
合計188両が1971年から翌年にかけて製造されている。
まず、1971年に急行「瀬戸(下り)2号・(上り)1号」に、
試作車のオハネ14 1 - 7とスハネフ14 1 - 3が連結され、試験的に運行を開始した。
同列車では他の従来型客車と連結する必要があったため、
試作車は蒸気暖房(SG)管と電気暖房用引通し線を新製時より搭載している。
1972年3月ダイヤ改正で寝台特急「さくら」・「みずほ」・「あさかぜ(下り)2号、
(上り)3号」の3往復で運用が開始された。
しかし1972年(昭和47年)に発生した北陸トンネル火災事故を機に、
火元となる可能性のある電源エンジンを客室の直下に置く、
分散電源方式は防火安全対策上問題があるとされ、
本形式の製造は一旦中止され、以後の増備は集中電源方式の24系客車に移行した。
1980年代から1990年代にかけてB寝台車の2段寝台化が行われたが、
需給関係との兼ね合いもあり、全車には及ばなかった。
2段化されなかった車両は急行列車や波動輸送用に使われたほか、
JR西日本管轄であった「出雲3・2号」に廉価サービスの一環として、
1989年(平成元年)から3段B寝台車を1両連結する措置がとられ、
同列車が1998年(平成10年)に電車化されるまで続けられた。
画像番号FH0006.JPGの画像は、
14系14形寝台車
24系客車
日本国有鉄道(国鉄)が設計・製造した寝台客車である。
1973年から1980年にかけて量産され、
21世紀初頭まで日本の寝台特急列車ブルートレインの主力車両として運用された。
1980年代中期以降、改造個室寝台車の開発や他の系列からの編入改造などで、
多彩なバリエーションが生じた。
24系24形
1973年に製造された初期のタイプの呼称。
A寝台車・B寝台車・食堂車については、14系の設計をそのまま踏襲している。
なお、車内設備は基本的には14系と同等ではあるものの、
寝台の枠をFRPからアルミに変更するなど難燃化が徹底している。
翌1974年に製造を24系25形へ移行したため、
これら24形グループの発注は1回だけで打ち切られ、製造両数は118両にとどまった。
A寝台車は14系のA寝台車と同様の開放形プルマン式である。
B寝台車は当初3段式寝台であったが、
1983年から1984年にかけて上段寝台を撤去して中段寝台を跳ね上げ、
これを固定して上段寝台とする方法で全車が25形と同様の2段式に改造されている。
新製配置は、向日町運転所(後の京都総合運転所、現・吹田総合車両所京都支所)で、
「あかつき」や「彗星」に使用されていた。
1975年3月のダイヤ改正で、一部を残し、
東京南鉄道管理局品川客車区(後の品川運転所、現・東京総合車両センター田町センター)に、
転属し、「はやぶさ」「富士」「出雲」で使用されたが、
翌1976年10月のダイヤ改正で盛岡鉄道管理局青森運転所(現・青森車両センター)へ再転属し、
「ゆうづる」「日本海」「あけぼの」「出羽」「鳥海」で使用されるようになる。
国鉄末期の1980年代中頃から運用する列車は漸減し、
「あけぼの」のみで使用されていた。
2014年(平成26年)の3月で「あけぼの」が定期運行が終了となり、
2015年1月「あけぼの」冬期以降の臨時列車の運行設定はなく、
運用する列車はなくなっている。
画像番号DSC 0038の画像は、
24系24形客車
画像番号IMG 0368.JPGの画像は、
24系24形客車(逆向き)
24系25形
1973年度下期から製造された、24形のマイナーチェンジ形式である。
製造当時、間近に控えていた山陽新幹線岡山駅 - 博多駅間の延伸開業によって、
寝台特急の利用客が減少することを見越して、定員を減らし居住性を改善するため、
B寝台車がそれまでの3段式寝台から2段式寝台に設計変更された。
1975年(昭和50年)、鉄道友の会より第15回ローレル賞を受賞した。
1974年(昭和49年)4月に「あかつき」と「彗星」の一部に初めて投入、
その後徐々に3段式B寝台を淘汰していく。
なお、2段寝台化による定員減を少しでも抑えるべく、トイレの配置を一区画縦にし、
更衣室も撤廃して1列(2名分)のスペースを捻出し、
オハネ24形とオハネ25形を比較した場合で1両当り1列多い17列の配置にするという
苦肉の策もとられた。外観上も24形が白帯(クリーム10号)塗装なのに対し、
塗装工程省力化の見地から、25形は製造当初よりステンレス帯となった。
製造時期によりマイナーチェンジが何度か行われており、
車体形状など細かなバリエーションが存在する。
また定員が減ったため、冷房装置の能力も若干落とされ(AU77形、10000kcal/h×2台)、
車内の天井高さに余裕ができたことから空調ダクトが、
24形の廊下側から中央へ移動している。
火事対策は、煙感知器がオハネ25形の廊下、換気口近くと便所近くに設置された。
オロネ25形については個室の天井に熱感知器が取り付けられている。
24系25形という名称は、オハネ25形・オハネフ25形の2段開放式B寝台車を、
従来の3段式の24系と区別するために便宜的につけられたものであり、
24系25形登場後もカニ24形・スシ24形・オハ24形など形式番号24の車両が登場している。
当然のことながら、ブレーキやサービス電源等の基本的なシステムは両者に差異はない。
国鉄末期の1987年(昭和62年)、「あさかぜ1・4号」に使用されている客車に対して、
アコモデーション改善(グレードアップ改造)が実施されたことに伴い帯が金色に変更され、
従来の位置に加え屋根下にも1本追加された。
1988年(昭和63年)以降に「北斗星」向け改造が施工された車両も金帯となった。
2013年の時点で、運用に就いていた24系25形は、
「北斗星」・「トワイライトエクスプレス」・「あけぼの」の
北海道・東北方面への列車のみとなっていた。
2014年3月には「あけぼの」が定期運用終了となり臨時運用となるが、
2014年12月 - 2015年1月の臨時列車を最後に「あけぼの」の臨時運用が終了している。
同年3月には「北斗星」・「トワイライトエクスプレス」が廃止となって定期運用は無くなった。
その後は臨時運用の「北斗星」に運用されていたが、
2015年8月22日の札幌発の上り列車をもって臨時運用も無くなっており、
「トワイライトエクスプレス」についても、
『特別な「トワイライトエクスプレス」』として、
京都・大阪-下関間でのツアー臨時列車において運行されているが、
これも2016年3月21日の下関始発を以って運行を終了する予定である。
2015年10月現在においての定期運用は、
急行「はまなす」に14系との混結改造を施したオハネ25形7両のみが使用されている。
画像番号IMG 5785.JPGの画像は、
24系25形客車 寝台特急北斗星
画像番号IMG 0680.JPGの画像は、
24系25形客車 寝台特急北斗星(逆向き)
E26系客車
東日本旅客鉄道(JR東日本)が1999年(平成11年)に製作した寝台客車である。
1988年(昭和63年)に運転を開始した「北斗星」をはじめとする
首都圏 - 北海道連絡の寝台特急について、
設備を一新した新系列の客車群として投入された。
2013年(平成25年)に九州旅客鉄道(JR九州)のクルーズトレイン
「ななつ星in九州」用客車が登場するまで、
JRグループが新造した唯一の新系列客車だった。
また、日本の客車車両としては、
本格的にステンレス車体を採用した、唯一の系列である。
1989年(平成元年)に製作した24系客車「夢空間」の使用経験も参考にし、
すべての客室を2人用A寝台個室で構成し、
高水準の接客設備をもつ寝台列車として開発された。
1編成(12両)が製作され、1999年(平成11年)7月16日に、
上野 - 札幌間の寝台特急「カシオペア」の愛称で営業運転を開始した。
以降、現在に至るまで、北海道 - 本州連絡系統を代表する列車として運用されている。
2000年(平成12年)度第43回鉄道友の会ブルーリボン賞受賞。
画像番号IMG 5711.JPGの画像は、
E26系客車
東武鉄道(旧国鉄・JR)14系
SL列車の運行に際し譲り受けた14系は、国鉄からJR東海に承継され、
さらにJR四国へ移り、JR北海道からも14系客車を譲り受けて、
2015年に除籍されて保存車となったが、今回、東武へ移って、
可能な限りデビュー当時の姿に修復。
営業運転に使用できるよう復活させた。
譲渡当初は車籍がなく、
南栗橋車両管区にて留置状態が続いていた。
その後、「SL大樹」およびSL大樹ふたら用に展望車として改造され復籍し、
2021年(令和3年)10月17日から営業運転を開始した。
14系は1両目とに3両目連結される。
画像番号DSC 6036.JPGの画像は、
東武鉄道(旧国鉄・JR)12系・14系客車
青色編成
画像番号DSC 8202.JPGの画像は、
東武鉄道(旧国鉄・JR)12系・14系客車 ぶどう色2号(茶色)編成