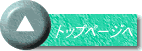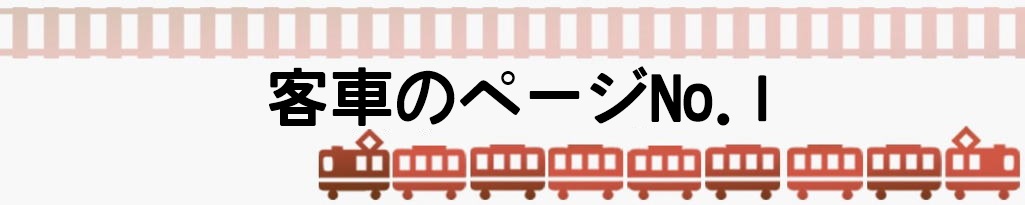
画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。
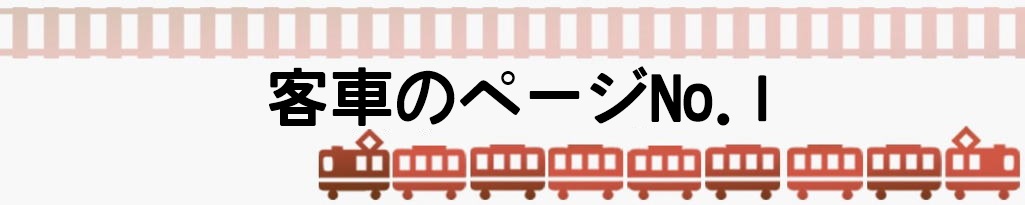
画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。
〔客車関連の解説〕
旧型客車
日本国有鉄道(国鉄)の客車のうち、10系以前に製作された客車の便宜的な呼称である。
旧形客車とも表記する。
JR東日本に残るイベント用の旧型客車。
スハフ42形が2両、オハ47形が3両、スハフ32形とオハニ36形がそれぞれが1両ずつ、
高崎車両センターに配置されている。
略して旧客。
在来形客車・一般形客車とも呼ばれるが、明確に分類されるものではない。
「旧形客車」とは、編成単位で使用することを基本とする
「新系列客車」と呼ばれる20系以降の客車との対比で使われた呼称である。
国鉄の現場で便宜的に使われた用語で、車両称号規程には存在しない呼称である。
正式な呼称ではないため、厳密な定義は存在しないが、
強固な台枠に強度を負担しない車体を載せる在来工法による
スハ43系以前の客車のこととする場合があり、
10系客車はその近代的な構造・外観・内装から「軽量客車」と呼ばれ、
旧型客車の範疇から外されることもある。
しかしながら、10系客車もスハ43系以前の客車のシステムを踏襲しており、
実際の運用でもスハ43系以前の客車と混用されたため、
10系客車も旧型客車の一種である。
また、雑多であったことから「雑型客車」と呼ばれることもあるが、
雑型客車とは国鉄の標準設計によらない客車を意味するものであり、
国有化(1910年以降製造の鉄道院基本形客車)から10系までの客車を、
雑型客車と呼称するのは誤りである。
画像番号DSC 8887.JPG+DSC 8293.JPGの画像は、
旧型客車
12系客車
日本国有鉄道(国鉄)が1969年(昭和44年)から1978年(昭和53年)まで、
合計603両を製造した急行形座席客車のグループである。
当初から冷房装置を搭載し、
また自動ドアの客車初採用などの改良で旅客サービスや
安全面の向上に大きな成果を挙げた。
このほか、客車初の分散ユニット型電源システムによる電源供給の効率化が図られ、
2段式ユニット窓やFRP部材の採用などでコストダウンをも図るなど、
多くの技術面でその後の国鉄客車の基本となった車両である。
当初は、1970年(昭和45年)の日本万国博覧会(大阪万博)輸送を念頭に、
臨時列車・団体列車を含めた波動輸送用車両として製造された。
既に、電車・気動車が旅客輸送の主力となっていた時期であるが、
あえて客車として製作された。
画像番号FH0738.JPGの画像は、
12系客車(基本)
画像番号DSC 8240.JPGの画像は、
12系客車 最終増備車
14系座席車
1969年(昭和44年)から、国鉄は波動輸送用として12系客車を製造していた。
12系は急行用としたことから座席は向かい合わせの固定式クロスシートであるものの、
110km/h運転が可能で冷房装置を完備した唯一の昼行用客車ということもあり、
当初は臨時特急列車にも12系を使用していたが、
特急料金の割引を行っても利用者の評判は芳しくなかった。
そこで12系客車の設計を基本とし、
183系電車と共通の車内設備をもつ特急形車両として、
1972年から1974年にかけて新潟鉄工所・富士重工業・日本車輌製造で、
合計325両が製造されたのが14系座席車である。
波動輸送用として増備されたことから、グリーン車・食堂車の製造は計画されず、
普通車のみが製造された。
簡易リクライニングシート、
AU13A形分散式冷房装置(製造途中から難燃化構造としたAU13AN形に変更)を搭載し、
台車はTR217D形を採用した。
車体の屋根高さは12系客車よりも10cm低い3,520mmである。
また、窓框の高さなど183系電車の普通車とほぼ同一であるが、
窓部の側構は同じ特急形でも電車・気動車と異なり内傾しておらず垂直である。
また、波動用という事でレジャー客のスキー板やゴルフバッグ等、
大型荷物の携行が予想された為客室の一端に大型荷物置場を設置した。
12系・14系寝台車以外の系列との併結は考慮されず、
蒸気暖房管と電気暖房用引通し線は未装備である。
画像番号FH0013.JPGの画像は、
14系座席車
50系客車
日本国有鉄道(国鉄)が主に地方都市圏の
通勤・通学時間帯の普通列車に使用する目的で、
1977年(昭和52年)より設計・製造された一般形客車の系列である
国鉄規格「赤2号」の塗装から「レッドトレイン」とも称されていた。
本州以南用の50形と、北海道用の51形があるが、
基本的な設計コンセプトは同一であるため本項ではこの両形式、
さらに同一の車体構造を有する荷物車マニ50形と、
郵便・荷物合造車スユニ50形についても併せて解説を行う。
1970年代前半まで、地方都市圏(特に交流電化線区や非電化幹線)の
旅客輸送には1920年代から1960年代にかけて製造された鋼製客車が多数使用されていた。
これらの車両は優等列車の電車化・気動車化および12系客車の登場によって、
転用されたもので10系以前の客車は、
登場後しばらくは程度の良い車両が優等列車に使用され、
後継車両の増備や置換えで捻出された中堅車や経年車は、
普通列車にも使用されるようになっていた。
これは国鉄が普通列車用の客車の製造に消極的であったためである。
しかし製造後20年から40年以上を経て老朽化・陳腐化が進行し、
保守上の問題と乗客からの不評を顕在化させていた。
このため一部の鉄道管理局では、室内の両端、
あるいはすべての座席をロングシートに改造し、
つり革を設置することで収容定員の増加が図られていたが、
狭いデッキや出入口はそのままであり乗降の遅滞から列車遅延の原因となっていた。
また自動扉をもたないこれらの客車は、
走行中でも客用扉を開閉できるため乗客や荷物が転落する危険があり、
保安上の問題となっていた。
上記の問題を解決するために、新形車両の導入が求められていた。
輸送改善に際しては、当時行われていた荷物・郵便輸送への配慮と、
貨物輸送量の減少で機関車の余剰が発生していたことから、
新形式客車を開発する方針が採られた。
1両当たりの製造コストが気動車や電車よりも格段に安かったため、
地方部の通勤・通学時間帯に多く運転されていた
比較的長編成の客車普通列車の置換え用として、
余剰化した電気機関車やディーゼル機関車を有効活用し、
輸送力増強やサービス改善を低コストで行うために製造された車両群が本系列である。
1979年(昭和54年)には鉄道友の会よりローレル賞を授与され、
オハフ50 1の車内に記念プレートが取付けられた。
画像番号FH0010.JPGの画像は、
50系50形客車