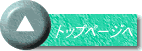画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。

画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。
 FH0002 |
 FH0003 |
 FH0032 |
 FH0042 |
FH0061 |
FH0080 |
FH0090 |
FH0092 |
FH0097 |
FH0111 |
 FH0133 |
 FH162 |
FH0181 |
IMG_0215 |
IMG_1711 |
IMG_1938 |
IMG_2822 |
 FH177 |
 FH179 |
FH180 |
 IMG_2382 |
 DSC_8458 |
 FH0196 |
 CIMG1172 |
 CIMG1526 |
〔417系交直流近郊形電車関連の解説〕
417系電車
417系電車は、1978年(昭和53年)に日本国有鉄道(国鉄)が、
設計・製造した交直流近郊形電車。
全車日立製作所が製造した。
1987年(昭和62年)の国鉄分割民営化時には、
全車東日本旅客鉄道(JR東日本)に承継された。
当時の国鉄は電車に汎用性を追求していたことから、
北海道以外では基本的に交流区間であっても、
交直両用電車を投入する方針としていた。
このため本系列も直流1,500V/交流20,000V50Hz/同60Hzの
3電源方式対応車として設計された。
しかし本系列は、営業運転開始から交流50Hz区間でのみ運用され続け、
後に誤操作防止のため交直流切替スイッチが交流側に固定された。
画像番号FH0061.JPGの画像は、
417系3両 編成番号不明
画像番号FH0090.JPGの画像は、
417系3両 K−2編成
画像番号FH0092.JPGの画像は、
417系3両 K−1編成
画像番号FH0097.JPGの画像は、
417系6両 編成番号不明
画像番号IMG 0215の画像は、
417系3両 編成番号不明
画像番号IMG 1711の画像は、
417系3両 編成番号不明
〔715系交流近郊形電車関連の解説〕
715系電車
715系電車は、日本国有鉄道(国鉄)が、
581系・583系寝台特急形電車の改造により製造した近郊形電車である。
581系・583系は交流直流両用電車であるが、
新幹線延伸による夜行列車としての運用減により、
余剰が発生していた581系・583系特急形電車の近郊形改造が提案され、
近郊形への改造に際して使用線区の事情により、
交流直流切替機能を交流側に固定し交流専用とした
715系電車と交流直流切替機能を存置した419系電車の2系列に分類される。
1000番台
1985年3月のダイヤ改正に合せて仙台地区用に改造されたグループ。
改造施工は、0番台を担当した小倉工場の他に、
郡山工場(現・郡山総合車両センター)
土崎工場(現・秋田総合車両センター)が担当した。
50Hz電化区間で使用されることから、
電動車は50Hz・60Hz両用のモハネ583形・モハネ582形とし、
寒冷地で使用されることから客用扉の半自動化や
車内ロングシートの扉隣接部に防風板が設置されるなどの
防寒・防雪対策の実施をしたため1000番台に区分された。
また、0番台では床下に装備されていた増設運転台の
タイフォン(空気笛)が前照灯横に装備され、
中・上段寝台用小窓が当初から埋込まれるなどの設計変更が実施された。
画像番号FH0002.JPGの画像は、
715系1000番台 黒磯方向 編成番号不明
画像番号FH0032.JPGの画像は、
715系1000番台 黒磯方向 編成番号不明
画像番号FH0133.JPGの画像は、
715系1000番台 黒磯方向 編成番号不明
画像番号FH0162.JPGの画像は、
715系1000番台 黒磯方向 編成番号不明
画像番号FH0181.JPGの画像は、
715系1000番台 黒磯方向 編成番号不明
画像番号FH0003.JPGの画像は、
715系1000番台 仙台方向 編成番号不明
画像番号FH0042.JPGの画像は、 編成番号不明
715系1000番台 仙台方向
画像番号FH0080.JPGの画像は、
715系1000番台 仙台方向 編成番号不明
画像番号IMG 2822.JPGの画像は、
さよなら715系記念号
「さよなら715系記念号」。
さようなら715系電車のヘッドマークを掲げたN7編成
車番は、黒磯方からクハ715−1007・モハ714−1007・モハ715−1007・クハ715−1107
715系1000番台は旧国鉄時代の1984(昭和59)年9月に登場し、
仙台地区普通列車の全面電車化のため60-3改正より使用開始されました。
59-2改正で余剰となった583系の改造車で落成当初は初期故障が続発し、
編成を組んでも起動不能・各種ランプ不点灯、
など検修泣かせの車両だったそうです。
登場時はクリーム1号地でしたが、
1985(昭和60)年9月に登場した455系新塗装車に合わせて、
クリーム10号地に順次塗色変更され東北線黒磯−一ノ関間で使用されましたが、
老朽化のため1998(平成10)年3月までに、
全車が701系に置き換えられて消滅しました。
この画像は、当時のさよなら運転の画像ですが、
その当時わたしは、仙台まで乗車しました。
〔717系交流近郊形電車関連の解説〕
717系電車
717系電車は、日本国有鉄道(国鉄)が設計した近郊形電車である。
両系列とも老朽化・陳腐化した交直流両用451系
453系・471系・473系・475系・457系急行形電車の電装品
冷房装置・台車などを再用して車体を新造した近郊形電車であり、
このうち交直両用車が413系電車、交流専用車が717系電車である。
1980年代に差し掛かり分割民営化を控えていた末期の国鉄は、
多額の債務を抱える赤字経営に加えてサービス水準の低さから、
社会的な批判が大きく利用者の視点に立った輸送サービスの改善が強く望まれていた。
一方、この頃まで金沢・富山あるいは仙台といった
交流電化区間の地方都市圏輸送は機関車が牽引する客車列車および、
急行列車削減により余剰となった457系をはじめとする
急行形電車により運転されていた。
これに対して国鉄では1984年(昭和59年)から、
1985年(昭和60年)にかけて地方中核都市圏のダイヤ改正を実施。
列車短編成化によるフリークエンシー向上と定時隔ダイヤを採用し、
全電車化によるスピードアップなどの輸送改善を行った。
717系0・100番台
仙台地区に投入された交流専用車両である。
クモハ717形 (Mc) - モハ716形 (M') - クハ716形 (Tc') の3両編成10本計30両が、
郡山工場(現・郡山総合車両センター・土崎工場(現・秋田総合車両センター)
小倉工場(現・小倉総合車両センター)で改造更新された。
改造内容は413系同様で、引通線も更新時にKE96形ジャンパ連結器1基装備に改造されたが、
先頭車前位に従来車との併結用KE76形2基も装備。
このため455・457系と編成単位での併結運用実績がある。
塗装は当初からクリーム10号の地色に緑14号帯のデザインである。
仙台運転所(→仙台電車区→現・仙台車両センター)に在籍。
編成番号は種車の電動車ユニットが451系の0番台車がT-1 - 5、
453系の100番台車がT101 - 105。415系電車(1500番台)や、
E721系電車への置換えにより、2007年11月10日に定期運用を終了。
置換え前の2006年から廃車がはじまり、2008年に全車廃車された。
主に常磐線水戸 - 仙台間で普通列車に運用されていたが、
末期は原ノ町以北と範囲が狭まった。
東北本線での運用実績もわずかにあり南は福島、
北は小牛田までの入線が記録されている。
画像番号FH0111.JPGの画像は、
717系0番台T−1編成
画像番号IMG 1938.JPGの画像は、
717系0番台T−2編成・717系100番台T−102編成6両、
〔阿武隈急行8100系電車関連の解説〕
阿武隈急行8100系電車
1988年、阿武隈急行線の全線電化開業にあわせ、日本車輌製造により9編成18両が製造された。
福島側に制御電動車のAM8100形、槻木側に制御付随車のAT8100形を連結し、
2両固定編成を組む。番号は8101-8102 - 8117-8118の連番となっており、
AM8100形が奇数、AT8100形が偶数である。
阿武隈急行が保有・運用する交流型電車。
画像番号FH179.JPGの画像は、
阿武隈急行8100系 編成番号不明
画像番号FH180.JPGの画像は、
阿武隈急行8100系 編成番号不明
画像番号IMG 2382.JPGの画像は、
阿武隈急行8100系 A−5編成
画像番号DSC 8458.JPGの画像は、
阿武隈急行8100系 A−9編成
政宗クロニクル のラッピング車両
画像番号FH0196.JPGの画像は、![]()
阿武隈急行8100系 A−6編成
画像番号CIMG1172.JPG・CIMG1526.JPGの画像は、![]()
阿武隈急行8100系
A−15編成+A−17編成団臨