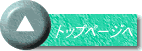画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。

画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。
FH0006 |
FH0019 |
FH0022 |
FH0038 |
FH0041 |
FH0078 |
FH0102 |
FH0103 |
FH0109 |
FH0125 |
 FH0181 |
IMG_0097 |
IMG_0098 |
IMG_0899 |
IMG_0988 |
IMG_2195 |
IMG_3939 |
 IMG_9052 |
FH0111 |
FH0112 |
IMG_0802 |
IMG_0806 |
IMG_0810 |
〔403系交直流近郊形電車関連の解説〕
401系・421系に搭載していた主電動機は出力100kWのMT46系列だったが、
これを120kWに出力向上したMT54系列に変更した系列である。
やはり主変圧器などの違いから常磐線用は403系、
九州用は423系という区分としている。
1965年(昭和40年)にそれぞれ水戸線電化準備用と、
鹿児島本線熊本電化延長用として新製された。
電動車は403系がモハ403・402形、423系がモハ423・422形となっているが、
付随車の制御車は前述のクハ401・421形が継続新製された。
1968年(昭和43年)まで製造され、製造両数は403系が4両編成20本計80両、
423系が4両編成30本計120両である。
なお最終増備車である403系第20編成・423系第29・30編成は、以下の改良が行われた。
屋上通風器をグローブ型から押し込み型に変更。
座席取手の変更。
客室側扉のステンレス化。
403系では行先票差しや急行札差しなどを423系の配置と同一のものに変更・統一。
画像番号FH0111.JPGの画像は、
403系4両 編成番号不明
画像番号FH181.JPGの画像は、
403系7両 原形ライト車K821編成
試8126M
画像番号IMG 0700.JPGの画像は、
403系4両 原形ライト車K921編成
画像番号IMG 9052.JPGの画像は、
403系4両 編成番号不明
画像番号FH0078.JPGの画像は、
403系4両 編成番号不明
画像番号FH0103.JPGの画像は、
403系4両 編成番号不明
画像番号FH0125.JPGの画像は、
403系4両 編成番号不明
〔415系交直流近郊形電車関連の解説〕
415系電車
415系電車は、日本国有鉄道(国鉄)が設計・製造した交直流両用近郊形電車。
国鉄分割民営化後は東日本旅客鉄道(JR東日本)と、
九州旅客鉄道(JR九州)に継承されたほか、
JR東日本が設計・製造した車両や西日本旅客鉄道(JR西日本)が、
113系を改造・編入した車両が存在する。
以上の系列に続き、1971年(昭和46年)から製造が開始された。
交流50/60Hz両用のTM14形主変圧器を搭載する「三電源方式」となっている。
0番台 普通鋼製車両
基本番台車。
制御車は上記系列からの編入を計画していたため300番台に区分された。
また、この番台のみトイレが両先頭車にある。
1974年落成の第4編成以降は当時製造されていた。
直流用113系・115系と同様に冷房装置搭載・外付けユニットサッシ窓の採用。
ロングシート部の座席の改善・クハ411形では運転室の拡大ならびに、
運転台のユニット化などが行われた。
また、公害防止対策として主変圧器などの冷却油をPCB油から、
シリコン油へと変更した。
非冷房車で落成した第3編成までも1977年までに冷房化改造が施工された。
冷房電源は113系・115系とは異なり、
偶数向きクハ411形に自車を含む4両給電対応で、
容量160kVAのMGを搭載するため引き通し線は方渡り構造となる。
勝田車両センター・南福岡車両区・門司港運転区所属の一部編成は、
クハ411形トイレ対向部を除きロングシートに改造。
JR九州所属車では屋上通風器・パンタグラフ周辺の
低屋根構造部の外気取り入れ口
常磐線用列車無線アンテナ台座および配管が撤去された。
さらに車体更新改造の際に側窓が一部を除き固定化された。
クハ411形では一部の奇数向き車両のトイレが撤去された。
1975年製造のクハ411-335は事故廃車となった423系先頭車
クハ421-43の代替として新製されたため、冷房装置は取り付けず、
本系列で唯一冷房準備車で落成し、
1983年に編成を組む423系とともに冷房化された。
冷房準備車特有の最前部の大型箱型通風器や
冷房装置もAU75系でも外キセをステンレス製とした
AU75E形を搭載するなどの外観が特徴だった。
同車の増備により以降0番台先頭車の奇数・偶数の車両番号の進番が逆転した。
2001年に423系の全廃と同時に415系で初の廃車となった。
画像番号FH0006.JPGの画像は、
415系0番台4両
画像番号FH0038.JPGの画像は、
415系0番台4両 K503編成
画像番号FH0061.JPGの画像は、
415系0番台4両 編成番号不明
画像番号IMG 0988.JPGの画像は、
415系0番台4両 編成番号不明
100番台 普通鋼製車両
1978年より製造されたクロスシート部の
座席間隔(シートピッチ)を、
従来車の1,420mmから1,490mmと70mm拡大した車両である。
車体構造は同時期に製造されていた113系2000番台と基本的に同一である。
トイレは偶数向き制御車にのみ設置となり、
制御車は奇数向き(クハ411-101 - )と偶数向き(同201 - )に区分された。
JR九州在籍車は、大分車両センター配置車両を除き、
トイレ対向部以外の座席がロングシートに改造された。
また、屋上通風器とパンタグラフ周辺の低屋根構造部の外気取り入れ口、
常磐線用列車無線アンテナ台座および配管が撤去されている。
さらに、車体更新改造の際に側窓は一部を除き固定化された。
その一方でJR東日本在籍車は順次E531系に置き換えられ、
在籍していた車両は同年3月17日をもって営業運転を終了した。
1984年に増備された偶数向きクハ411形の機能を備える
中間付随車のサハ411形は1 - 4に区分されている。
このうち1と3の冷房電源用MGは新製時は設置スペースを確保した準備工事車で、
翌1985年の7両編成組成時に設置された。
なお、同時に製造されたモハ415・414-127・128には、
ペアとなる先頭車が存在しない。
また、これらの100番台最終増備車は当初より常磐線新塗色で登場し、
屋上通風器、冷房装置の外キセ、室内のカラースキームが、
後述の500番台に合わせたものになった。
また、クロスシート部分の配色は前年の713系に類似している。
画像番号FH0019.JPGの画像は、
415系100番台4両 K515編成
画像番号FH0041.JPGの画像は、
415系100番台4両 K513編成
500番台
常磐線の混雑緩和を目的として1982年より製造されたロングシート車である。
ただし、トイレ対向部はクロスシートとされた。
偶数向き先頭車はクハ411-601 - に区分された。
窓配置などの外観は100番台とほとんど同じだが、
屋上通風器は箱型に変更されている。
内装のデザインとカラースキームは当時増備されていた201系に合わせられ、
座席の端部には袖仕切りを設置した。
ロングシートの構造と寸法は105系新造車グループと、
ほぼ同等で座面が低く奥行きが深い。
当初は車内禁煙区間が上野駅 - 土浦駅間のみだったため、
ロングシート車ながら各車両の出入台の戸袋窓下と妻部に灰皿が設置されていた。
また腐食防止の観点から車体裾部にステンレスが用いられ、
1982年製510・610 - 512・612からは冷房装置の
外キセがステンレス化された。
この他、1984年製造分の513・613 - 516・616から常磐・水戸線新塗装となり、
翌1985年製造の521・621 - 524・624は後述の700番台に合わせて変圧器が変更され、
車内の天井構造も冷房ダクトを平滑化して平天井となっている。
またドアエンジン部分にも増備時期による変遷が見られる。
当初は全車が勝田に配置されたが、
1986年3月に513・613 - 517・617の5編成が、
421系を置き換えるため南福岡に転属した。
その後2007年2月に513・613と517・617の2編成が、
同年3月に514・614 - 516・616の3編成が、
475系・457系を置き換えるため鹿児島総合車両所に転属した。
JR九州在籍車は屋上通風器とパンタグラフ周辺の
低屋根構造部の外気取り入れ口が撤去された。
また勝田所属車には座席がバケット化され座面が、
若干高くなった車両が存在していた。
勝田所属車は2007年3月17日までに定期営業運転を終了した。
保留車となっていたK607編成の507・607と、
K620編成の520・620の2編成8両は、1500番台の1編成とともに、
2008年12月にJR九州に譲渡(12月24日付で廃車)。
旧K607編成は小倉工場で、旧K620編成は鹿児島総合車両所で整備され、
旧K620編成がFM520編成、旧K607編成がFM507編成となって南福岡電車区に配置され、
(それぞれ2009年3月9日・11日付で入籍)、
2009年3月より営業運転を開始している。
その後は2012年に南福岡車両区に817系3000番台が新製配置されたことに伴い、
0番台を置き換えるために大分車両センターへ転属した。
700番台
1984年 - 1985年に製造された。
落成当初より常磐・水戸線新塗装。
車内設備は車端部分をロングシートとしたセミクロスシート車で、
配色は100番台最終増備車と同様である。
屋上主変圧器は自然冷却式に改良され、車内の天井構造を平滑化している。
1985年の科学万博開催に向けた常磐線の輸送力増強のため、
他番台の一部の4両編成に編入し7両編成とする目的で製造されており、
先頭車は基本編成7両編成の4両編成化に伴って1989年に、
サハ411-707から改造されK522編成の
いわき方先頭車として運用されていたクハ411-701の1両のみが存在する。
全車が勝田車両センターに配置されていたが、
2007年3月17日までに定期営業運転を終了した。
2008年7月までに全車両とも廃車され、
廃区分番台(サハ411形は廃形式)となった。
500・700番台の落成時公式試運転は、日立製作所製では九州地区、
日本車輌製では北陸本線を走行した事例がある。
画像番号FH0022.JPGの画像は、
415系500番台4両
画像番号FH0102.JPGの画像は、
415系500〜700番台7両+1500番台4両
編成番号不明
画像番号FH0109.JPGの画像は、
415系500〜700番台7両 編成番号不明
画像番号FH0112.JPGの画像は、
415系500〜700番台7両 編成番号不明
画像番号IMG 0097.JPGの画像は、
415系500〜700番台7両 編成番号不明
画像番号IMG 0899.JPGの画像は、
415系500〜700番台7両 編成番号不明
画像番号IMG 2195.JPGの画像は、
415系500〜700番台7両+4両
編成番号不明
画像番号IMG 3939.JPGの画像は、
415系7両+4両
編成番号不明
画像番号IMG 0802.JPGの画像は、
ありがとう415系4両K515+7両K813編成
画像番号IMG 0806.JPGの画像は、
ありがとう415系ヘッドマーク
画像番号IMG 0810.JPGの画像は、
ありがとう415系パンフレット