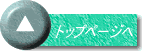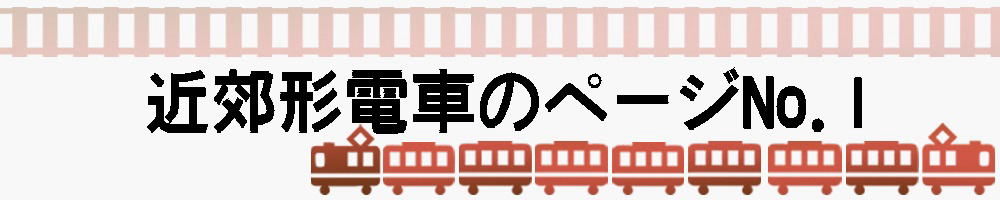
画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。
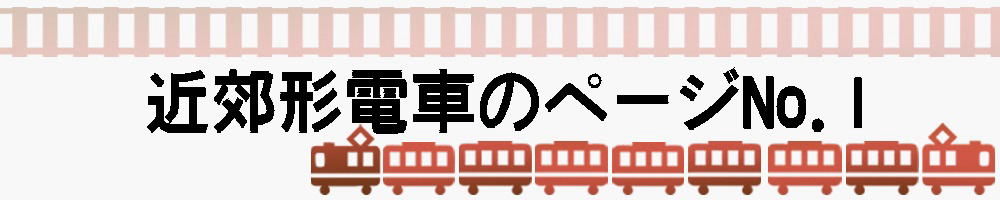
画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。
FH0007 |
FH0011 |
FH0029 |
FH0030 |
FH0034 |
FH0035 |
FH0036 113系 |
FH0037 |
FH0039 |
FH0040 |
FH0086 |
 IMG_0101 |
IMG_8804 |
IMG_8829 |
IMG_8842 |
 DSC_4157 |
 DSC_8416 |
 DSC_8436 |
FH0106 |
FH0110 |
〔113系・115系直流近郊形電車関連の解説〕
113系電車
113系電車とは、1963年に日本国有鉄道(国鉄)が開発した直流近郊形電車。
1962年(昭和37年)に先行開発された上記の111系をもとに、
120kWに出力が強化され新たに標準化されたMT54形主電動機を用いた形式。
これにともない主制御器、主抵抗器なども容量が増大された。
1963年から1982年にかけて約2,900両もの多数の車両が製造され、
おもに本州内の平坦で温暖な地域の路線で広く普通列車から快速列車に用いられた。
関連系列として、寒冷・急勾配路線用に並行製造された115系があるが、
これと比較して、平坦線用のため抑速ブレーキやノッチ戻し制御は装備しない。
JR移行に際しては、東日本旅客鉄道(JR東日本)・東海旅客鉄道(JR東海)
西日本旅客鉄道(JR西日本)の3社に引き継がれ、
主に東海道本線や山陽本線系統など平坦路線の普通・快速列車に運用されたが、
後継形式への置き換えによってJR東日本では2011年、
JR東海では2007年に運用を終了した。
2012年10月時点ではJR西日本とJR四国(JR東日本から一部車両が譲渡された)で、
主に普通列車に運用されている。
1000番台
横須賀線・総武快速線の地下区間(錦糸町 - 品川間、1972年開業)直通を目的に、
1969年から製造された地下区間乗入対応車両グループである。
0番台を基本に、運輸省(→国土交通省)制定の
A-A基準に対応した難燃構造が採用された。
CP付きの西(偶数)向き制御車は、
基本番号+300の「クハ111形1300番台」と区分されている。
画像番号FH0036.JPGの画像は、
113系1000番台(湘南色)
115系電車
115系電車は、日本国有鉄道(国鉄)が寒冷地区・急勾配路線での運用を目的に設計し、
1963年(昭和38年)から製造を開始した直流近郊形電車である。
1963年から1983年(昭和58年)まで、改良を重ねながら1,921両も製造された。
また一時期には急行列車にも投入されたほか、
通常はEF63形による推進・牽引となる
信越本線横川 - 軽井沢間(碓氷峠)での自力走行試験車両にも抜擢された。
汎用性の高さから1987年(昭和62年)の国鉄分割民営化前後に編成両数を減らして、
本数を増やす目的で、中間車の先頭車への改造が多く施工され、
JR発足時には東日本旅客鉄道(JR東日本)・東海旅客鉄道(JR東海)
西日本旅客鉄道(JR西日本)が承継。
2012年(平成24年)4月現在では老朽化や後継形式の登場により、
初期・中期形の多くは廃車のほか一部車両はしなの鉄道・伊豆急行に譲渡され、
全車廃車となったJR東海・伊豆急行を除いた
JR東日本・JR西日本・しなの鉄道
115系0番台
1963年から1970年(昭和45年)にかけて製造されたグループ。
客室窓部は、ユニット窓ではなく四隅に丸め処理がなされる。
クモハ・クハ115形の前照灯は大型の白熱灯で、
中間組み込み時には助士席側を折りたたみ客室(立席)への転換が可能である。
クハ115形は方向転換可能な両渡り構造を採用したほか99- は、
雨樋を乗務員室扉上まで延長し、
最前部の通風器を大型な物にする設計変更が行われた。
広域波動輸送に対応する目的から製造され後述の
モハ114-818 - 831とユニットを組むモハ115-94 - 107
クハ115-193 - 216・サハ115-25 - 30は新製時からの横軽対策施工車である。
1968年(昭和43年)12月落成のクハ115-215 -はタイフォンに耐雪カバーを装着。
1963年1月に製造開始。
同年3月に宇都宮運転所皮切りに、
新前橋電車区(現・高崎車両センター)・三鷹電車区(現・三鷹車両センター)
小山電車区(現・小山車両センター)に新製配置された。
後に新潟・静岡・岡山・下関の各地区にも転出したために<
分割民営化時にはJR東日本・JR東海・JR西日本に承継。
2013年現在も改造車を含み運用される。
画像番号FH0029.JPGの画像は、
115系0番台4両
画像番号FH0035.JPGの画像は、
115系0番台4両
300番台
1973年(昭和48年)に製造を開始したモデルチェンジ車で、
小山電車区・新前橋電車区・三鷹電車区に新製配置された。
画像番号IMG 0101.JPGの画像は、
115系300番台 さよなら115系団臨
画像番号FH0106.JPGの画像は、
115系300番台7両 編成番号不明
画像番号FH0011.JPGの画像は、
115系300番台4両
画像番号FH0030.JPGの画像は、
115系300番台7両
画像番号FH0086.JPGの画像は、
115系300番台8両
ホリデー快速鎌倉号
1000番台
上越線・信越本線などの多雪地域で使用を考慮した
耐寒耐雪構造を強化した区分で1977年から1982年(昭和57年)まで製造された。
300番台をベースとする
画像番号FH0007.JPGの画像は、
115系1000番台4両 高崎車
画像番号FH0034.JPGの画像は、
115系1000番台3両 高崎車
画像番号FH0029.JPGの画像は、
115系1000番台6両(新新潟色)
〔211系直流近郊形電車関連の解説〕
211系電車
211系電車は、1985年(昭和60年)に登場した直流近郊形電車。
本系列は、これらに代わるフルモデルチェンジ車であり、
軽量ステンレス製車体や構造の簡便なボルスタレス台車、
電機子チョッパ制御よりも簡便かつ安価に、
回生ブレーキが使用可能で抵抗制御を基本とした界磁添加励磁制御、
応答性の高い電気指令式ブレーキや簡易的なモニタ装置など、
省エネルギーや保守費低減に配意した新機軸が各所に採用されている。
これらは通勤形電車の205系で先に採用されたものであるが、
本来は近郊形電車用のシステムとして開発されていたものである。
ユニットあたりの力行性能の向上により、電動車比率を下げ、
2M3T編成で25‰区間までの通常の使用ができる設計とし、
新製コストと運営コストの減少を狙った設計とした。
これにより2M3T編成においても113系・115系の2M2T編成と同等以上の走行性能をもつ。
車体は、片側3か所に両開きの扉を設けた国鉄近郊形電車の基本的構成であるが、
両端の側出入口の位置を若干車端に寄せた配置としている。
外板間の車体幅は、従来の2900mmから初めて2950mmまで拡大され、
裾絞りが大きくなっている。また暖地・平坦線用の113系と、
寒地・勾配線用の115系を統合し、
細部の仕様変更を行うことで両系列の取替に対応している。
また座席は従来と同様のセミクロスシートの他、
長距離通勤の増加に伴う混雑に対応するためにオールロングシートの車両も製造した。
クロスシート・ロングシートともバケットタイプとし、
ロングシートの1人分の幅を広げた。
クロスシートはシートピッチ1,490mmのままでスペースと通路幅を広げた。
また、セミクロスシート車も混雑緩和のため、
415系700番台同様車端部はロングシートとした。
国鉄時代は付属編成のみがオールロングシートとされたが、
国鉄分割民営化後の増備車はすべてオールロングシートが基本となっている。
さらに、車体の構造と台車は同時期に製造された415系1500番台にも採用され、
民営化後も車体や制御システムの設計を流用した車両が登場している。
1000・3000番台(寒冷地仕様車)
0・2000番台を基本に宇都宮線と高崎線(東北本線上野口)の
使用に配慮した寒地仕様車で、
115系非冷房車の置換え用として登場したものである。
1000番台はセミクロスシート車、3000番台はロングシート車で、
ともにスノープラウ(排雪器)、耐雪ブレーキ、半自動ドア、
レールヒーターなどの耐寒耐雪装備がなされている。
編成は、東海道本線用0・2000番台と異なり普通車のみの5両編成 (McM'TTTc') で、
1000・3000番台共同一である。東海道本線用には無い
制御電動車が用意されたのは、
将来3両編成に改組して地方路線に転属させられるように考慮したためである。
国鉄時代には、セミクロスシート車1000番台11本55両と、
ロングシート車3000番台22本110両の計165両が製造され、
民営化後は東海道本線用と同様にロングシートの3000番台のみが、
1991年までに40本200両が増備されている。
国鉄時代には、1000番台×1本+3000番台×2本で、
15両編成を組むように計画されたため、
1000番台と3000番台の運用も分けられていたが、
3000番台のみの増備となった民営化後は共通運用となった。
なお、2000番台と同様運転席背後の仕切窓、
荷物棚、吊手などに製造年次による変化がある。
新製配置は1000番台が全車両新前橋電車区(現・高崎車両センター)で、
3000番台は当初クモハ211形・モハ210形・クハ210形の車番
3001 - 3046が新前橋電車区、
3047 - 3062が小山電車区(現・小山車両センター)配置であったが、
2000年(平成12年)からE231系が小山電車区に新製配置になったことにより、
同年12月に新前橋区に配置が集約されている(現在は一部が幕張車両センターに転出)。
そのため、上野発着の東北本線では宇都宮線列車よりも高崎線列車の運用の方が多い。
優先席の吊革は高崎車・幕張車共に全ての編成でE233系タイプのものに交換済みである。
0・2000番台と同様に、2008年秋頃より、
モケット地をすおう色から青緑色に交換しているほか、
順次PS33E形シングルアーム式パンタグラフへの取り替え及び増設(一部)が行われた。
2006年9月4日、両毛線前橋駅 - 前橋大島駅間において踏切事故が発生し、
クハ210-3013が側構体に数メートルにわたって穴が開くなどの大きな損害を受けた。
当該車は大宮総合車両センターに臨時入場のうえ、復旧工事が行われた。
現物での復旧が困難な側構体と窓枠については、同時期に廃車となり、
長野総合車両センターで解体が進められていたサハ211形から該当する部分を切り取り、
これを取り付ける工法で復旧が行われた。
このため、出場後のクハ210-3013は復旧部分のみ、
ステンレスの光沢や帯色に相違が見られる。
前述した田町車両センターに続いて、
2012年度より高崎車両センター向けにもE233系3000番台が投入され、
本系列の置き換えが始まっている。
2013年3月16日のダイヤ改正で宇都宮線上野口の運用から撤退した。
画像番号FH0128.JPGの画像は、
211系3000番台二階建グリーン車連結無し15両
編成番号不明
画像番号FH0110.JPGの画像は、
211系3000番台二階建グリーン車連結無し10両
編成番号不明
画像番号DSC 4157.JPGの画像は、
211系3000番台5両 A28編成
画像番号IMG 8829.JPGの画像は、
211系3000番台二階建グリーン車連結15両の回送
画像番号IMG 8804.JPGの画像は、
211系3000番台二階建グリーン車連結15両 普通列車 上野行
画像番号DSC 8416.JPGの画像は、
211系3000番台5両 A25編成
画像番号DSC 8436.JPGの画像は、
211系3000番台5両 A31編成
画像番号IMG 8842.JPGの画像は、
211系3000番台5両 A33編成