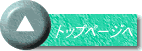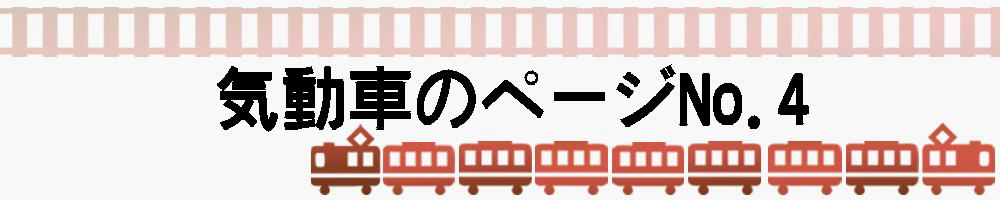
画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。
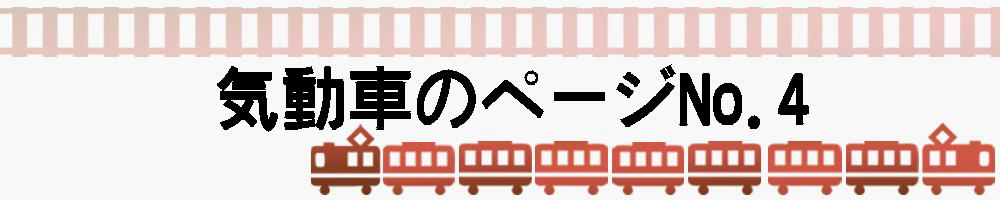
画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。
キハ47形
1.3m 幅の両開き扉を車体中央寄り2か所に配置した、
いわゆる「近郊形」のレイアウトである。
キハ40形・キハ48形よりもラッシュ時などの客扱い能力を重視した片運転台車であり、
仕向け地とトイレの有無により細かな番台区分がある。
車内の化粧板はクリーム色系だが、
初期に製造されたキハ47 1 - 16は緑色系である。
デッキは装備せず、北海道向けの酷寒地仕様も存在しない。
客室窓は2段上昇式ユニット窓である。
0・1000番台
温暖地向け仕様車で、
0番台車はキハ40形100番台車と相前後して1977年上期に製造が開始された。
金属バネ台車装備。
トイレ付きの0番台車は1983年までに193両 (1 - 193) が、
その後1978年から製造が開始されたトイレなしの1000番台車は、
1982年までに134両 (1001 - 1134) が製造された。
この温暖地向けキハ47形327両が本系列の最大グループである。
キハ47 1〜193
暖地向け仕様で、片運転台車であり、金属ばね台車装備。
トイレ付きの0番台車は1977年上期に製造が開始された。
1.3 m幅の両開き扉を車体中央寄り2か所に配置した、
キハ40形、キハ48形よりもラッシュ時などの客扱い能力を重視した片運転台車であり、
いわゆる「近郊形」のレイアウトで、客室窓は2段上昇式ユニット窓、デッキは装備せず、
1983年までに193両が製造された。
キハ47 1001〜1134
暖地向け仕様で、片運転台車であり、金属ばね台車装備。
トイレなしの1000番台車は1978年から製造が開始された。
1.3 m幅の両開き扉を車体中央寄り2か所に配置した、
キハ40形、キハ48形よりもラッシュ時などの客扱い能力を重視した片運転台車であり、
いわゆる「近郊形」のレイアウトで、
客室窓は2段上昇式ユニット窓、デッキは装備せず、
1982年までに134両が製造された。
画像番号FH0138.JPGの画像は、
キハ40形500番台 旧新潟色(青ベースの塗装) +キハ47−188 旧新潟色(青ベースの塗装)
画像番号IMG 3334.JPGの画像は、
キハ47形1000番台2両 旧新潟色(青ベースの塗装)
キハ47 1〜193
暖地向け仕様で、片運転台車であり、金属ばね台車装備。
トイレ設置。
定員124名。
キハ47 1001〜1134
暖地向け仕様で、片運転台車であり、金属ばね台車装備。
トイレ無し。
定員128名。
500・1500番台
新潟地区向け寒地仕様車で、空気ばね台車装備。
1978年から1980年にかけてトイレ付きの500番台車22両 (501 - 522) と、
トイレなしの1500番台車21両 (1501 - 1521) が製造された。
本来は寒地仕様だが、国鉄時代に越後線と弥彦線の電化に伴い四国や中国、
九州など温暖地に転じたのち民営化を迎え、温暖地で運用されている例もある。
キハ47 1501〜1521
新潟地区向け寒地仕様で、片運転台車であり、空気ばね台車装備。
1.3 m幅の両開き扉を車体中央寄り2か所に配置した、
キハ40形、キハ48形よりもラッシュ時などの客扱い能力を重視した片運転台車であり、
いわゆる「近郊形」のレイアウトで、
客室窓は2段上昇式ユニット窓、デッキは装備せず、
21両が製造された。
画像番号FH0017.JPGの画像は、
キハ47形500番台 旧新潟色(青ベースの塗装) +キハ40形500番台 旧新潟色(青ベースの塗装)
画像番号DSC 2364.JPGの画像は、
キハ47−1515 新潟色(赤ベースの塗装) +キハ40−560 旧新潟色(青ベースの塗装)
画像番号DSC 2370.JPGの画像は、
キハ40−583+キハ47−515+キハ47−514(首都圏色)
画像番号DSC 2378.JPGの画像は、
キハ48−523+キハ47−1514(国鉄急行色) +キハ47−514(首都圏色)
磐越西線紅葉号
画像番号DSC 6622.JPGの画像は、
懐かしの水郡レトロ号
キハ47−1514(国鉄急行色)+キハ48−523(国鉄急行色)
画像番号DSC 7190.JPGの画像は、
キハ47−515+キハ47−514(首都圏色)
キハ47 501〜522
新潟地区向け寒地仕様で、片運転台車であり、空気ばね台車装備。
トイレ設置。
定員124名。
キハ47 1501〜1521
新潟地区向け寒地仕様で、片運転台車であり、空気ばね台車装備。
トイレ無し。
定員128名。