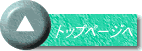画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。

画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。
 FH0004 |
 IMGP1025 |
IMG_0019 |
IMG_0080 |
IMG_1310 |
IMG_1322 |
IMG_9667 |
DSC_0423 |
DSC_2582 |
DSC_2712 |
DSC_2814 |
DSC_4335 |
 DSC_7087 |
DSC_7726 |
485系シルフィード
東日本旅客鉄道(JR東日本)が1990年(平成2年)以降に運用している
鉄道車両(電車)で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。
JR東日本新潟支社では、日本国有鉄道(国鉄)時代から、
継続して12系客車を改造した6両編成の和式(お座敷)客車
(1985年(昭和60年)にサロンカー「サロン佐渡」1両を追加)と、
キハ28形・キハ58形気動車カーペット車を運用していた。
1987年(昭和62年)には欧風車両である
「サロンエクスプレスアルカディア」の運行を開始したが、
1988年(昭和63年)3月30日に火災事故を起こし、使用不能となっていた。
当時、新潟支社のジョイフルトレインは、
分割民営化以後に首都圏への乗り入れが増加していたが、
それまでのジョイフルトレインは一部を除いて客車か気動車であった。
このうち客車の場合は機関車の付け替えなどによる要員確保が必要であるほか、
気動車の場合は機動性については申し分ないものの
走行性能は電車と比べて低いほかブレーキ性能も異なるといった制約があった。
そこで、ベースを交直流電車とした上で、
非電化線区ではディーゼル機関車による牽引を可能にすることで、
これらの問題を解決することになった。
いずれの車両も、編成短縮化により余剰となっていた
サロ189形を種車とした改造車名目ではあるが、車体は新製されており、
種車からは一部の部品が流用されたにすぎない。
また、制御装置や電動機、台車などの走行機器については、
485系1000番台の予備品が使用されたことから、
485系の形式番号が付与された。
ジョイフルトレインでは初めての交直流電車であり、
形式は先頭車がクロ484形とクモロ485形、中間車はモロ484形である。
改造は車体鋼体をそれぞれ近畿車輛・東急車輛製造・新潟鐵工所で新製し、
新津車両所で最終的な艤装工事が行われた。
この時点では全車両がグリーン車扱いであった。
画像番号IMGP1025.JPGの画像は、
485系シルフィード
485系カーペットカーNO.DO.KA(のどか)
東日本旅客鉄道(JR東日本)が、
2001年(平成13年)以降に運用している鉄道車両(電車)で、
ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。
JR東日本新潟支社では、日本国有鉄道(国鉄)時代から、
継続して12系客車を改造した6両編成の和式(お座敷)客車、
(1985年(昭和60年)にサロンカー「サロン佐渡」1両を追加)と、
キハ28形・キハ58形気動車カーペット車を運用していた。
1987年(昭和62年)には欧風車両である
「サロンエクスプレスアルカディア」の運行を開始したが、
1988年(昭和63年)3月30日に火災事故を起こし、使用不能となっていた。
当時、新潟支社のジョイフルトレインは、
分割民営化以後に首都圏への乗り入れが増加していたが、
それまでのジョイフルトレインは一部を除いて客車か気動車であった。
このうち客車の場合は機関車の付け替えなどによる要員確保が必要であるほか、
気動車の場合は機動性については申し分ないものの
走行性能は電車と比べて低いほかブレーキ性能も異なるといった制約があった。
そこで、ベースを交直流電車とした上で、
非電化線区ではディーゼル機関車による牽引を可能にすることで、
これらの問題を解決することになった。
上沼垂運転区(現・新潟車両センター)に配置され、
2001年10月より営業運行を開始し、
DE10形ディーゼル機関車の牽引により非電化線区へ乗り入れ、
さらに同年10月には交流電化区間にも入線するなど、
車両の特徴を生かした団体専用列車を中心に運用された。
2001年(平成13年)1月には、客室設備はそのままに普通車に格下げされ、
次のように改番された。
1号車 クハ484-701(旧クロ484-1) - 展望車・電源車
2号車 モハ484-701(旧モロ484-1)
3号車 クモハ485-701(旧クモロ485-1) - 展望車
同年10月には、カーペット車両に改装し、同時に愛称を「NO.DO.KA」(のどか)に変更した。
この際に、便所の増設と塗装デザインの変更を行なった。
なお、非電化線区用の発電機器類はそのまま残されている。
その後も、団体専用列車を中心に運用されている。
いずれの車両も、編成短縮化により余剰となっていた
サロ189形を種車とした改造車名目ではあるが、車体は新製されており、
種車からは一部の部品が流用されたにすぎない。
また、制御装置や電動機、台車などの走行機器については、
485系1000番台の予備品が使用されたことから、485系の形式番号が付与された。
ジョイフルトレインでは初めての交直流電車であり、
形式は先頭車がクハ484形とクモハ485形、中間車はモハ484形である。
改造は酒田リニューアルセンター(旧酒田機関区)が担当した。
この時点では全車両が普通車扱いになった。
塗装デザインは、車体下半分を白、上半分をベージュとし、
その境目に黄緑と紫(パープル)の帯を入れたものとした。
画像番号DSC 7726.JPGの画像は、
485系カーペットカーNO.DO.KA(のどか)
485系 リゾートやまどり
「群馬デスティネーションキャンペーン」開催に合わせて、
JR東日本高崎支社の新しい観光列車として、
2011年に運行を開始した高崎車両センター所属の
485系電車によるジョイフルトレインである。
編成番号はYD01。名称は群馬県の県鳥「ヤマドリ」に由来する。
485系電車の6両編成でテーマは「癒しと郷愁」で、
編成は上野方からクハ484-703・モハ484-703・モハ485-703
モハ484-704・モハ485-704・クハ485-703。
群馬デスティネーションキャンペーンに合わせ、
2011年夏から吾妻線を中心とした高崎支社エリアを中心に運用される。
高崎車両センターに所属している。
後述する「やまなみ」のMM'ユニットと「せせらぎ」編成を種車に、
東急車輛製造で改造施工をした6両編成。
1999年に登場したお座敷電車「やまなみ」のうち中間の2両と、
2001年に登場したお座敷電車「せせらぎ」の全4両を2011年に、
再改造した座席車のジョイフルトレインである。
グリーン車から普通車に格下げされたため形式はロからハへと変更されているが、
車内は座席が1+2の3列となっておりグリーン車並みの設備となっている。
画像番号DSC 0010.JPG・DSC 0423.JPGの画像は、
485系 リゾートやまどり
485系きらきらうえつ
東日本旅客鉄道(JR東日本)新潟支社が、
新潟駅 - 酒田駅・象潟駅間を白新線・羽越本線経由で運行する快速列車である。
新潟駅で上越新幹線に接続し、新潟県下越地方、
山形県庄内地方を走行する臨時列車で、年間を通じて主に週末を中心に運転される。
列車名は、羽越本線に寄り沿う日本海の美しさを「きらきら」で表現するとともに、
路線名の由来でもある沿線地域の旧国名「出羽国」と
「越後国」を合わせた「羽越」を表したものである。
沿線には日本海に沈む夕日や出羽三山、かつての城下町である鶴岡市と村上市、
北前船の文化が根付く湊町の酒田市などをはじめ数々の観光地が存在し、
また多種多様な食材が豊富な立地でもあり、四季を通じて観光資源に恵まれている。
こうしたことから「きらきらうえつ」には「乗ってうれしい・降りて楽しい」という
キャッチコピーが銘打たれ、沿線観光が主眼に置かれており、
停車各駅からの観光コースも設定されている。
JR東日本新潟支社と秋田支社、仙台支社では沿線自治体と共同で観光振興に取り組んでいるほか、
山形新幹線の在来線区間を運行する臨時特急列車「とれいゆ つばさ」などと、
合わせた周遊観光ルートの提案を進めている。
新潟車両センター所属の485系電車700番台「きらきらうえつ」専用4両編成が充当される。
外装はホワイトをベースに、羽越本線沿線の色彩豊かな四季の風景を、
イメージカラー化してパッチワーク風に配色した塗装が施されている。
種車の485系は高運転台だが、
きらきらうえつ編成は車窓の眺望性を高めるため低運転台に改造されている。
なお、きらきらうえつ編成が定期検査等のため運用できない場合は、
快速「きらきらうえつ」は他車両での代替運転は行わず、全区間で運休となる。
画像番号DSC 7087.JPGの画像は、
485系きらきらうえつ TOCHIGIバルトレイン
485系 宴(うたげ)
JR東日本東京地域本社(当時)では、
「なごやか」・「江戸」の2編成の和式車両(お座敷客車)を保有しており、
中・高年代層の団体輸送に使用されてきた。
しかし、需要に追いつかず、申し込みを断るケースも多々あったことから、
新たな和式車両の投入を行なうことになり、
改造された車両である。
当初から和式車両への改造が行なわれた交流直流両用電車は、
JR東日本では本車両が初めてである。
少なくともJR東日本の電化区間であれば、
信号方式がATC専用の区間でない限り走行可能で、
機関車交換が不要で走行速度も高いために、
到達時分の短縮も図れることになったことから、
以後485系改造の和式車両がいくつか登場することになる。
いずれの車両も485系電車からの改造で、
先頭車がクロ484形とクロ485形、
中間車はモロ484形とモロ485形である。
各車両の番号は「シルフィード」・「リゾートエクスプレスゆう」からの続き番号となっている。
全車両がグリーン車扱いである。
画像番号DSC 2582.JPGの画像は、
485系 宴(うたげ)
485系 華(はな)
JR東日本東京地域本社(当時)では、
お座敷客車「なごやか」「江戸」、
お座敷電車「宴」の3編成の和式車両を保有しており、
中・高年代層の団体輸送に使用されてきた。
しかし、客車編成は老朽化に加えて、
機関車による牽引となることから速度面で電車に劣り、
特に首都圏での運行ではダイヤ作成上の障害となっていた。
このため、「なごやか」の代替編成として、
和式電車を製作することになったものである。
いずれの車両も485系電車からの改造で、
先頭車がクロ484形とクロ485形、
中間車はモロ484形とモロ485形である。
各車両の番号は「リゾートエクスプレスゆう」・「宴」からの続き番号となっている。
全車両がグリーン車扱いである。
画像番号IMG 9667.JPGの画像は、
485系 華(はな)
ジョイフルトレイン485系「ジパング」
2012年(平成24年)4月から6月まで開催される
「いわてデスティネーションキャンペーン(いわてDC)」に合わせて、
JR東日本盛岡支社の新しい観光列車として同年4月1日より運行を開始した。
485系電車から改造された「ジパング」は、
「東北地方の歴史と自然」と2011年(平成23年)に、
世界遺産に登録されたばかりの「平泉」への期待をデザインし、
「落ち着き」「重厚感の中にあるさりげない煌きらびやかさ」
をテーマとしている。
盛岡車両センター所属の4両編成で郡山総合車両センターで改造工事を施工。
1号車・4号車は高崎支社高崎車両センター所属の和式車両で、
「リゾートやまどり」への改造で余剰となっていた
「やまなみ」の先頭車クロ485-4・クロ484-6が種車。
普通車化と視認性向上で上部に前照灯を増設。
2号車・3号車は特急「つがる」等で運用されていた
青森車両センター所属のモハ485・484-3014が種車。
側面方向幕を撤去しサボ入れを新設。
このため先頭2両は屋根がドーム状になっているが、
中間車2両は屋根上に冷房装置などが突き出ているほか、
車体も裾絞り構造など相違点がある。
車体カラーは黒色を基調とし、
先頭車には華やかさと雄大な自然をイメージした
金と緑の「ジパング」のロゴマークが描かれている。
画像番号DSC 4335.JPGの画像は、
ジョイフルトレイン485系「ジパング」
485系リゾートエクスプレスゆう
JR東日本東京地域本社と水戸支社で、
共通使用するジョイフルトレインとして、
1991年にサロ183形・189形・481形を種車に、
4両が大井工場(現・東京総合車両センター)で2両が、
大船工場(現・鎌倉車両センター)で改造された。
非電化区間への直通運用を考慮し、専用の電源車も同時に改造で登場した。
水戸支社で使用してきた和式客車スロ81形・スロフ81形
「ふれあい」の後継編成であると同時に、
首都圏のジョイフルトレインの新しいシンボルとして、
「コンフォートクオリティ」を目指した。
外部塗色はフュージョンベージュをベースカラーとし、
窓周りにフィロスブラウンを配し、
窓上にアクセントとしてペパーミントグリーンのピンストライプが入る。
1998年に内装を和式化し、
引き続き常磐線系統を中心に各種の臨時列車・団体列車に使用されている。
車体断面は651系と同様、下部をしぼった曲面で構成された。
側面窓には大型の連続窓が採用された。
車両前面はセンターピラーの幅を広げた上で、
縦長の電照式ヘッドマークとした。
センターピラーの下には縦型2灯式の前照灯を設置し、
その両側に尾灯兼用のLED標識灯を配した。
集電装置(パンタグラフ)はモロ484に1基搭載するが、
中央東線などのトンネル断面の小さい線区への入線も可能なように、
パンタグラフ取り付け部分の屋根は一段低くなっている。
電源車を除いた全車両がグリーン車扱いである。
画像番号FH0005.JPGの画像は、
485系リゾートエクスプレスゆう (お座敷化改造前)
画像番号DSC 2712.JPG
485系リゾートエクスプレスゆう (お座敷化改造後)
485系 彩(いろどり)
長野支社では14系客車改造のジョイフルトレイン「浪漫」を、
1995年から保有していたが、老朽化の進行ならびに機関車牽引による
運用効率の問題から廃車させることになり、
代替の後継車両として485系電車から改造されたのが「彩」である。
快速「くびき野」で限定運用されていた
新潟車両センター所属の4両編成であるT21・22編成から、
T21編成の制御車を除いた6両を充当した。
なお、余剰となったクハ481−333・1507は廃車・解体となっている。
2006年5月から12月の間に長野総合車両センターで改造を施工した。
制御車は北海道向け耐寒耐雪強化形の1500番台、
中間電動車は本州向け耐寒耐雪強化形の1000番台をベースとする。
これまでのJR東日本が所有する485系改造のジョイフルトレインは、
台枠・機器類の流用で車体は新たに新造されていたが、
「彩」では車体は流用とされ内装の改造が主とされた。
全車両がグリーン車扱いである。
画像番号IMG 0019.JPG・IMG 0080.JPGの画像は、
485系 彩(いろどり)
485系やまなみ
やまなみは、老朽化していた12系客車改造の
お座敷列車「くつろぎ」の代替として1999年に、
485系電車を改造して登場したお座敷列車である。
改造は大宮工場(現・大宮総合車両センター)が担当した。
コンセプトは「ハイグレネードな日本調空間」。
後述の「せせらぎ」と併結運転が可能であった。
旧「やまなみ」は中間車のみを「リゾートやまどり」に改造し、
残る先頭車2両は高崎車両センターに留置されていた。
全車両がグリーン車扱いである。
画像番号IMG 1310.JPGの画像は、
485系やまなみ
485系せせらぎ
老朽化していた12系客車改造の
お座敷列車「やすらぎ」の代替として2001年に、
485系電車を改造して登場したお座敷列車である。
改造は郡山工場(現・郡山総合車両センター)が担当した。
前述の「やまなみ」と併結運転が可能であり、
号車番号は「やまなみ」の1号車〜4号車に続くように、
5号車〜8号車と付けられていた。
「リゾートやまどり」に改造するため、
2010年7月12日に東急車輛製造に入場し、
2011年2月10日に出場した。
全車両がグリーン車扱いである。
画像番号IMG 1322.JPGの画像は、
485系せせらぎ
485系ニューなのはな
JR東日本千葉支社では、1986年よりお座敷電車「なのはな」を保有し、
団体輸送に使用されてきた。
しかし、老朽化に加えて、直流電車であったことから、
交流電化区間への乗り入れが出来ず、運用に制約があった。
このため、「なのはな」の代替と同時に、
サービスレベルの向上を主眼として開発された車両である。
いずれの車両も485系電車からの改造で、
先頭車がクロ484形とクロ485形、
中間車はモロ484形とモロ485形である。
各車両の番号は「リゾートエクスプレスゆう」・「宴」・「華」からの
続き番号となっている。
全車両がグリーン車形式であるが、
後述するように座席仕様での運用も可能であり、
この場合は普通車扱いとなる。
画像番号DSC 2814.JPGの画像は、
485系ニューなのはな