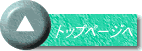画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。

画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。
CIMG0820 |
 CIMG0854 |
CIMG1396 |
 CIMG1536 |
DSC_0067 |
DSC_0098 |
 DSC_6390 |
DSC_8044 |
 DSC_8161 |
 DSC_8170 |
DSC_8202 |
IMG_0438 |
 IMG_1704 |
E956形「ALFA-X」
新幹線E956形電車は、
2019年(令和元年)5月に登場した。
東日本旅客鉄道(JR東日本)の新幹線用高速運転試験電車である。
愛称は「ALFA-X」(アルファエックス)で、
『Advanced Labs for Frontline Activity in rail eXperimentation』
(鉄道実験における最先端の活動を行うための先進的な試験室)に由来する。
北海道新幹線札幌開業を視野に360km/h営業運転が可能な営業車両の開発を目的とし、
2019年5月から2022年3月にかけて、
400km/h走行なども含めた様々な試験を実施する。
同年5月10日夜から試験を開始するにあたり、
2019年5月9日に新幹線総合車両センターにて報道公開された。
1 - 6号車は川崎重工業、7 - 10号車は日立製作所で製造された。
(10号車の先頭車の意匠はJR東日本と日立製作所が共同で取得している)。
2018年12月12日に1号車の車体が川崎重工業兵庫工場で公開され、
2019年2月8日には10号車の車体が日立製作所笠戸事業所で公開された。
先端部分の「鼻」の長さが1号車は約16メートル、
10号車は約22メートルあり、
両端を異なる形状にしてトンネル進入時の車体への圧力などの違いを分析する。
中間車の2 - 9号車のうち、3・7号車は他の車両と比べて窓が小さく、
5号車には客室の窓が設けられていない。これらの車両では、
窓の大きさや有無による車両構造・客室内環境等の評価が行われる。
8号車は客室を2つに分けた車両となり、客室環境の比較評価が行われる。
走行時は先頭車・中間車の各車両に測定器等が搭載される。
制御伝送装置にはS-INTEROSを搭載している。
2020年10月27日には、報道関係者を対象にした試乗会が行われた。
画像番号CIMG0820.JPG+CIMG0854.JPGの画像は、
E956形「ALFA-X」
E926系 East−i
2001年にE3系をベースに開発された。
正式名称は「電気軌道総合試験車」であり、「East i」の愛称がついている。
最高速度は275km/hである。S51編成とも呼ばれる。
E3系をベースにした理由は、
ミニ新幹線規格の山形新幹線区間および、
秋田新幹線区間でも運用できるように考慮されたためである。
北陸新幹線(長野新幹線)でも使用できるように、
周波数50/60Hz切替装置や抑速ブレーキ切替装置も装備している。
フル新幹線規格の東北新幹線・上越新幹線・長野新幹線の各区間と、
ミニ新幹線規格の山形新幹線・秋田新幹線の各区間の検測を一手に引き受けている。
6両編成のうち、軌道検測車であるE926-3には、
同一仕様のE926-13が存在し、
一方が検査などで走行できない時でも軌道の検測が行えるようになっている。
S51編成の全体が全般検査等入場中で計測走行できない時は、
E2系(N21編成)にE926-3または13を組み込み、
軌道検測を行う。メーカーは東急車輛製造。
1号車 (E926-1) :通信(LCX・在来線列車無線)
電力(架線間隔測定)・信号(ATC用)
2号車 (E926-2) :通信・測定用電源
3号車 (E926-3, 13) :軌道
4号車 (E926-4) :電力(集電・検測兼用パンタグラフ)
5号車 (E926-5) :電力・信号
6号車 (E926-6) :電力(架線間隔測定)・信号(ATC用)
1, 2, 4 - 6号車の台車は、
E3系のDT207A(一部に検測用の機器を搭載できるものを使用)を搭載している。
また、軌道検測車(3号車)用の台車TR8012は、
E3系のTR7005Aをベースにしている。
具体的には、検測枠が取り付けられ、車輪径は860mmから820mmに縮小、
ヨーダンパも片側2本取り付け(E3系は1本)となっている。
画像番号DSC 8170.JPGの画像は、
E926系 East i
E491系 East i−E
老朽化した443系・マヤ34形の置き換えとして、
2002年(平成14年)に日立製作所・近畿車輛で製造された。
3両編成1本(3両)が勝田車両センターに配置されている。
主に電化路線の軌道・架線・信号の検測で運用されている。
既に標準軌に改軌された奥羽本線福島 - 新庄間
大曲 - 秋田間(秋田新幹線部分)と、
田沢湖線・電化区間の飛地である仙石線以外の電化区間であれば、
どこでも運転・検測出来る。
クヤE490とモヤE490の間に、
建築限界測定車のマヤ50 5001(旧スヤ50 5001)を連結して4両で走ることも可能。
またJR東日本の各電化路線以外に、
青い森鉄道・IGRいわて銀河鉄道・北越急行・しなの鉄道
東京臨海高速鉄道でも検測を行うことがある。
クモヤE491-1(Mzc・製造:日立製作所)
信号・通信関係 地上信号機器・通信機器の測定装置を有するほか、
測定用の下枠交差式PS96A形パンタグラフを備える。
また検測等必要に応じて1台車の主電動機カットを行うことができる。
モヤE490-1(Mz・製造:近畿車輛)
電力関係 架線測定用の装置を有する。
パンタグラフは集電用のシングルアーム式PS32A形を2基備え、
編成の進行方向に応じて使い分ける。
クヤE490-1(Tzc・製造:日立製作所)
軌道関係 軌道状態測定用の装置を有するほか、
測定用の下枠交差式PS96A形パンタグラフを備える。
画像番号DSC 8161.JPGの画像は、
E491系+マヤ50−5001(3両目に組込)
East i−E
画像番号DSC 0098.JPGの画像は、
E491系+マヤ50−5001(2両目に組込)
East i−E
画像番号IMG 0438.JPGの画像は、
E491系 East i−E 回8125M
画像番号CIMG1396.JPGの画像は、
E491系 East i-E ID-23 試9141M 東北本線計測(勝田車両センター)
キヤE193系East i−D
東日本旅客鉄道(JR東日本)の事業用気動車。
East i-D(イーストアイ・ダッシュディー)の愛称を持つ。
キヤ191系気動車の置き換え用として、
2002年に新潟鐵工所で製造された。
3両1編成が秋田車両センターに配置され、
自社管内の非電化区間の検測を目的として走行するが、
例外として電化区間である仙石線や日光線の検測も実施している。
本系列は、標準軌に改軌された奥羽本線福島〜新庄間、
大曲〜秋田間(秋田新幹線使用部分)、
田沢湖線とATC設置区間を除く、
JR東日本の在来線全線の走行が可能となっている。
運用範囲はJR東日本管内の路線に限定されず、
毎年5月には北海道旅客鉄道(JR北海道)の路線で、
またJR以外では真岡鐵道真岡線・神奈川臨海鉄道
山形鉄道フラワー長井線などにも貸し出され、出張走行をする。
画像番号DSC 0067.JPGの画像は、
キヤE193系事業用気動車 East i−D
画像番号DSC 8044.JPGの画像は、
キヤE193系事業用気動車 East i−D
キヤE192−1中間車 (Mz)無しの2両編成
キヤE991系気動車
元は2003年にシリーズ式ハイブリッド気動車として試作された
E991系気動車キヤE991形(キヤE991-1)で、
2008年(平成20年)に燃料電池動車に改造し、
形式称号もE995系電車クモヤE995形(クモヤE995-1)に改称された。
また、愛称は気動車時代と変わらず「NEトレイン (New Energy Train) 」とした。
燃料電池駆動のためパンタグラフは無かったが、
2009年(平成21年)にパンタグラフを搭載し
「蓄電池駆動電車システム」試験車両として再改造され、
愛称も「NE Train スマート電池くん」と改められた。
電化区間は通常の電車として走行しながら充電し、
非電化区間は電化区間や駅停車中に充電した電力を元に蓄電池駆動で走行するもので、
将来への実用化に向けた研究試験が実施された。
ハイブリッド気動車(キヤE991形)時代は宇都宮運転所所属であったが、
2007年(平成19年)3月に一旦、廃車(除籍)となった。
燃料電池動車への改造後(無車籍)は長野総合車両センター、
蓄電池駆動車に改造された後は小山車両センターに所属し、
周辺の各路線で各種試験を行った。
車籍は2010年(平成22年)2月に復活した(新製車扱い)。
2014年(平成26年)3月15日のダイヤ改正から、
本形式を実用化したEV-E301系電車1編成(2両)が烏山線で運用を開始した。
試験終了後は所属先の小山車両センターに長らく留置されていたが、
2019年(令和元年)12月18日に廃車のため長野総合車両センターへ回送され、
2020年(令和2年)2月19日に解体された。
画像番号IMG 1704.JPGの画像は、
キヤE991−1
ENR‐1000形 投排雪用保守用車
東日本旅客鉄道(JR東日本)では、
老朽化しつつある除雪用機関車の代替として、
新潟トランシス製の投排雪用保守用車ENR‐1000を導入している。
軸配置B-Bの箱形両運転台で機関車然としているが、
車籍はなく機械扱いである。
当機の分類については「投排雪用保守用車」とするものや
「大型排雪用モーターカー」とするものなど文献によりさまざまで一定しない。
除雪に際しては、ロータリーヘッドの掻き寄せ翼を、
プラウ状に変形させることができ、
ラッセル車・ロータリー車の除雪機能を、
ヘッドの着脱なしに選択出来ることが特長である。
また、本線上では軌道回路に反応する状態で運行し、
位置確認の確実化・踏切通過時の安全確保などを図っている。
画像番号DSC 6390.JPGの画像は、
ENRー1000あかべぇマーク付き
209系訓練車
東京・大宮総合訓練センター・横浜総合訓練センターおよび、
八王子総合訓練センターで使用されてきた訓練車を置き換えるために、2連×3本が登場した。
いずれも廃車となった209系0番台の中間車に前面部分を新規接合した。
0番台の一部電動車MM'ユニットを、廃車後、先頭車化して訓練車に改造したもので、
首都圏の訓練センターに残る。
103・105系を中心とした訓練機械を当時における最新型へと置換えるため、
2両編成3本が投入された。
いずれも機械扱いで車籍はない。
画像番号DSC 8202.JPGの画像は、
横浜総合訓練センターの訓練車
209系(元ウラ19編成2両)