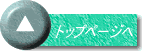画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。

画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。
ED77形電気機関車
日本国有鉄道(国鉄)が、磐越西線郡山 - 喜多方間電化開業にため、
1967年(昭和42年)より製造した交流用電気機関車である。
交流電気機関車の事実上の標準形式となった
ED75形の仕様を基に軸重制限のある磐越西線への入線と、
サイリスタ位相制御の実用化がなされたのが本形式である。
画像番号FH168.JPGの画像は、
ED77−10号機牽引 50系客車4両
画像番号FH160.JPGの画像は、
ED77−14号機の牽引+485系シルフィード
画像番号FH0005.JPGの画像は、
ED77−11号機牽引 50系客車4両
さようならED77ヘッドマーク付き
画像番号FH170.JPGの画像は、
ED77−12号機牽引+補機はカマ番号不明 50系客車4両
さようならED77ヘッドマーク付き
ED78形電気機関車
日本国有鉄道(国鉄)の交流電気機関車である。
1968年の奥羽本線米沢 - 山形間交流電化ならびに既存の直流電化区間であった
福島 - 米沢間の交流電化切替に伴い、
急勾配を有する板谷峠の通過対策を主として開発された交流電気機関車である。
画像番号FH152.JPGの画像は、
ED78−3号機牽引+50系客車
EF71形電気機関車
日本国有鉄道(国鉄)が製造した交流電気機関車である。
1968年の奥羽本線米沢 - 山形間交流電化ならびに、
既存の直流電化区間であった福島 - 米沢間の交流電化切替に伴い、
急勾配を有する板谷峠での牽引定数を極力確保する必要から、
EF70形に続く動軸6軸の「F形」として開発された形式が本形式である。
板谷峠は約33‰の平均勾配を有し、碓氷峠・瀬野八と並ぶ急勾配区間である。
同区間は1949年より直流電化され、
当初はEF15形、1951年からはEF15形に回生ブレーキを追設改造したEF16形、
1964年からは抑速発電ブレーキを装備したEF64形が運用されてきた。
しかし、1959年に東北本線黒磯駅以北が交流電化され、
福島で分岐する奥羽本線も既存直流電化区間である同区間も、
1968年10月1日のダイヤ改正で奥羽本線の米沢 - 山形間が、
交流電化されるのにあわせ交流電化への切替が決定したことから、
対応型の勾配区間用交流電気機関車が計画され、
サイリスタ位相制御・交流回生ブレーキを搭載した
試作機ED94 1(後のED78 901)で試験が行われた。
同区間は貨物列車も多数運転されており、
牽引定数を極力確保する必要があった。
連結器の強度と勾配条件から列車重量は最大650tを想定したが、
ED78形のみの重連運転では連続回生ブレーキ時の熱容量不足であること、
また33‰区間での力行時に均衡電流が、
570A(一時間定格)を上回る懸念からF形機の開発・製造が求められた。
画像番号FH0043.JPGの画像は、![]()
EF71−2号機牽引+50系客車
画像番号FH163.JPGの画像は、
EF71−7号機牽引+50系客車
画像番号FH0155.JPGの画像は、
EF71−6号機+ED78−2号機牽引+12系客車
お別れスイッチバック号