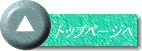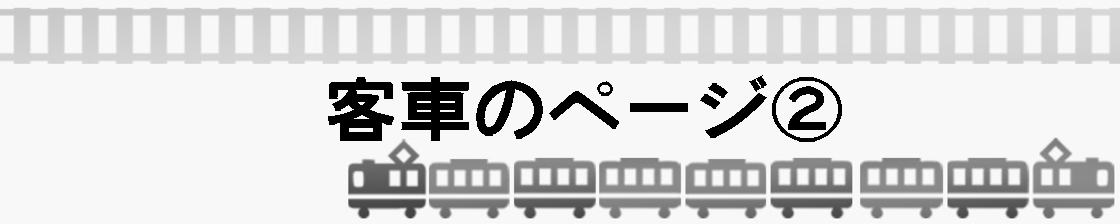
画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。
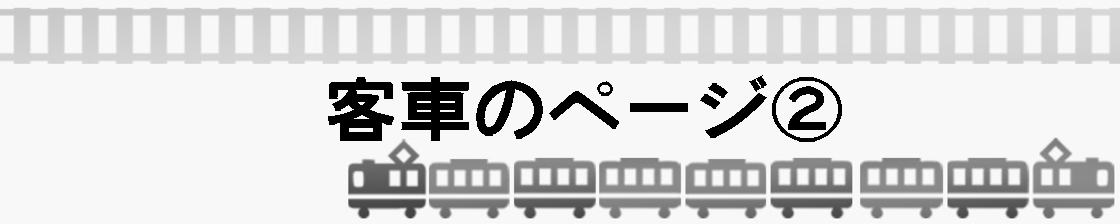
画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。
14系座席車
1969年(昭和44年)から、国鉄は波動輸送用として12系客車を製造していた。
12系は急行用としたことから、
座席は向かい合わせの固定式クロスシートであるものの、
110km/h運転が可能で冷房装置を完備した唯一の昼行用客車ということもあり、
当初は臨時特急列車にも12系を使用していたが、
特急料金の割引を行っても利用者の評判は芳しくなかった。
そこで12系客車の設計を基本とし、
183系電車と共通の車内設備をもつ特急形車両として1972年から、
1974年にかけて新潟鉄工所・富士重工業・日本車輌製造で、
合計325両が製造されたのが14系座席車である。
波動輸送用として増備されたことから、グリーン車・食堂車の製造は計画されず、
普通車のみが製造された。簡易リクライニングシート、
AU13A形分散式冷房装置(製造途中から難燃化構造としたAU13AN形に変更)を、
搭載し台車はTR217D形を採用した。
車体の屋根高さは12系客車よりも10cm低い3,520mmである。
また、窓框の高さなど183系電車の普通車とほぼ同一であるが、
窓部の側構は同じ特急形でも電車・気動車と異なり内傾しておらず垂直である。
12系・14系寝台車以外の系列との併結は考慮されず、
蒸気暖房管と電気暖房用引通し線は未装備である。
スハフ14形(スハフ14 1 - 63)
定員64名の普通座席緩急車である。
サービス用電源としてDMF15HZ-G形
ディーゼルエンジン駆動(出力270PS)による
DM93発電機(容量210kVA)を搭載し、
スハフ14形1両当たり自車を含む6両に給電可能とした。
後位側妻面(車掌室)の貫通扉には手動式の字幕が取り付けられ、
他の特急形客車と同様にテールマークの表示が可能となっている。
定員64名。
画像番号IMG 3805.JPGの画像は、
スハフ14-36
新製落成日、1974(昭和49)年2月25日、新製配置、宮原、製造、新潟鉄工所
転属日、1974(昭和49)年3月、転属配置先、向日町
転属日、1978(昭和53)年、転属配置先、早岐
転属日、1980(昭和55)年、転属配置先、秋田
転属日、1982(昭和57)年11月日、転属配置先、尾久
廃車日、2003(平成15)年7月3日、尾久
オハ14形(オハ14 1~209)
中間に組み込まれる座席車
定員72名の普通車である。
画像番号IMG 3808.JPGの画像は、
オハ14-198
新製落成日、1974(昭和49)年9月24日、新製配置、宮原、製造、富士重工
転属日、1976(昭和51)年3月31日、転属配置先、尾久
廃車日、2003(平成15)年4月15日、尾久
オハフ15形(オハフ15 1 - 53)
定員64名の普通緩急車である。
車体の基本構造はスハフ14形と同じであるが、
サービス電源用の発電セットを搭載しない。
また12系のオハフ13形では搭載準備工事が施工されていたが本形式では未施工である。
画像番号IMG 3810.JPGの画像は、
オハフ15-25
新製落成日、1974(昭和49)年2月15日、新製配置、名古屋、製造、新潟鉄工所
転属日、1985(昭和59)年、転属配置先、尾久
廃車日、2000(平成12)年6月30日、尾久
12系客車
日本国有鉄道(国鉄)が1969年(昭和44年)から、
1978年(昭和53年)まで、
合計603両を製造した急行形座席客車のグループである。
当初から冷房装置を搭載し、
また自動ドアの客車初採用などの改良で、
旅客サービスや安全面の向上に大きな成果を挙げた。
このほか、客車初の分散ユニット型電源システムによる電源供給の効率化が図られ、
2段式ユニット窓やFRP部材の採用などでコストダウンをも図るなど、
多くの技術面でその後の国鉄客車の基本となった車両である。
量産グループIII
12系の製造は1971年以降打ち切られていたが、
6年後の1977年(昭和52年)に再開され、
翌1978年(昭和53年)まで製造された。
スハフ12形は、循環式汚物処理装置の設置に伴う
電源装置の変更により新区分番台の100番台となっている。
また、電源装置を搭載しないオハフ13形は、製造されなかった。
スハフ12 101 - 163
1977年 - 1978年に63両が製造された。
電源機関をDMF15HZ-G形に、発電機をDM93形に変更。
これにより容量が210kVAへ増強。
また冷房装置をAU13AN形に、空気圧縮機をC400A形に、
台車をTR217D形に変更。新たに前位妻側に尾灯設置し、
さらに車内には冷水器を設置。
また、1972年に発生した北陸トンネル火災事故の教訓から、
火災対策が強化されており、床を合板床からアルミに、
車内の布製品を難燃性に変更している。
ばんえつ物語号用の12系客車は、
スハフ12 9 - 90に装備されていた。
発電用エンジンを排気タービン過給器付きの
DMF15HS-G(230 PS/1800 rpm)発電容量を180 kVAのものに変更された。
定員80名。
スハフ12 101 - 148
100番台は電源容量が210 kVAに増強されたほか、
電源機関吸気用ルーバーの反対側面への増設、
車掌室のない側の妻面にも尾灯を設置するなどの変更が行われた。
定員80名。
画像番号FH0725.JPGの画像は、
スハフ12-114
新製落成日、1977(昭和52)年3月18日、新製配置、青森、製造、富士重工
転属日、1985(昭和60)年2月1日、転属配置先、盛岡
転属日、1995(平成6)年12月3日、転属配置先、青森
廃車日、1999(平成11)年12月21日、青森
スハフ12 149 - 163
最終増備車である149 - 163は、後位側幌と緩急室窓を、
当時量産が開始された50系と共通化し、
幌は収納式から外吊の普通型へ、緩急室後方の監視窓は縦長に、それぞれ変更された。
定員80名。
画像番号DSC 6695.JPGの画像は、
スハフ12 161
新製落成日、1978(昭和53)年11月24日、新製配置、尾久、製造、富士重工
転属日、1994(平成6)年12月3日、転属配置先、高崎
画像番号DSC 6712.JPGの画像は、
スハフ12 162
新製落成日、1978(昭和53)年11月24日、新製配置、尾久、製造、富士重工
転属日、1994(平成6)年12月3日、転属配置先、高崎
オハ12 313 - 374
1977年 - 1978年に62両製造された。
冷房装置をAU13AN形に、台車をTR217C形に変更。
定員88名。
画像番号IMG 3671.JPGの画像は、
オハ12 366
新製落成日、1978(昭和53)年12月4日、新製配置、尾久、製造、新潟鉄工所
転属日、1994(平成6)年12月3日、転属配置先、高崎
画像番号DSC 6708.JPGの画像は、
オハ12 367
新製落成日、1978(昭和53)年12月4日、新製配置、尾久、製造、新潟鉄工所
転属日、1994(平成6)年12月3日、転属配置先、高崎
画像番号DSC 6704.JPGの画像は、
オハ12 368
新製落成日、1978(昭和53)年12月4日、新製配置、尾久、製造、新潟鉄工所
転属日、1994(平成6)年12月3日、転属配置先、高崎
廃車日、2023(令和5)年3月30日、高崎
画像番号DSC 6702.JPGの画像は、
オハ12 369
新製落成日、1978(昭和53)年11月24日、新製配置、尾久、製造、富士重工
転属日、1994(平成6)年12月3日、転属配置先、高崎
50系客車
日本国有鉄道(国鉄)が主に地方都市圏の
通勤・通学時間帯の普通列車に使用する目的で、
1977年(昭和52年)より設計・製造された一般形客車の系列である。
国鉄規格「赤2号」の塗装から「レッドトレイン」とも称されていた。
本州以南用の50形と、北海道用の51形があるが、
基本的な設計コンセプトは同一であるため本項ではこの両形式、
さらに同一の車体構造を有する荷物車マニ50形と、
郵便・荷物合造車スユニ50形についても併せて解説を行う。
50形
本州以南向けのグループで、
1978年(昭和53年) - 1982年(昭和57年)に製造された。
東北・北陸地区などに投入された車両は電気暖房を併設し、
車両番号が原番号+2000を付与される。
オハ50形 (オハ50 1 - 2335)
編成の中間に組成する座席普通車で335両が製造された。
定員112名。
画像番号FH0214.JPGの画像は、
オハ50-2208
新製落成日、1980(昭和55)年12月8日、新製配置、新津、製造、新潟鉄工所
転属日、1993(平成5)年6月23日、転属配置先、上沼垂
廃車日、1996(平成8)年8月5日、上沼垂
オハフ50形(オハフ50 1 - 2488)緩急車。
68両が製造された。
定員92名。
画像番号FH0216.JPGの画像は、
オハフ50-2047
新製落成日、1978(昭和55)年7月17日、新製配置、酒田、製造、新潟鉄工所
転属日、1993(平成5)年6月23日、転属配置先、上沼垂
廃車日、1996(平成8)年8月5日、上沼垂
マニ50形
老朽化したマニ60形・マニ36形など旧形車の置換え用として開発された荷物車で、
1977年(昭和52年) - 1982年(昭和57年)に236両が製造された。
室内配置は従来の荷物車とほぼ同等でトイレ・貴重品室を、
乗務員室扉は車体前後に設置し、各々に車掌室と業務用室を配する。
荷重は14t。
外部塗色は青15号である。
全車が電気暖房装置を備え車両番号は2000番台とされた。
ただし1979年(昭和54年)製造車からは、
ブレーキシリンダの配置など細部が変更され車両番号が2101以降に区分された。
1986年(昭和61年)に鉄道荷物輸送が廃止されたことで、
本来の荷物車としての用途はなくなり、
製造年が新しいにもかかわらず大量に廃車となったが、
「MOTOトレイン」用や救援車代用として、
JR旅客6社に63両が承継された。
しかし現在までにMOTOトレインはすべて廃止され、
営業運転に使用されることはほとんどない。
現在使用頻度の高い車両は、
工場入出場時の控車として使用されるごく一部である。
特異なものとして、24系客車の電源車マニ24形500番台や、
「リゾートエクスプレスゆう」用電源車への改造車が存在した。
マニ50 2001~2072
一般形として製造されたグループで、
1977~1978(昭和52~73)年に新潟鉄工所、富士重工業で72両製造された。
車体構造は50系客車を基本としているが、
車内配置はマニ36形と同様に前位から荷物室、便所・貴重品室、車掌室となっている。
積載荷重は13tで、台車は50系客車と同じTR230を使用している。
1986(昭和61)年11月改正の荷物輸送の廃止によりほとんどが余剰となり、
JR移行直前の1987(昭和62)年に59両が廃車となった。
1989(平成元)年にJR東日本在籍の1両が24系客車マニ24形へ改造され、
現在は救援車代用または控車として7両が在籍していた。
画像番号DSC 4850.JPGの画像は、
マニ50 2050
新製落成日、1978(昭和53)年4月17日、新製配置、隅田川、製造、新潟鉄工所
転属日、1979(昭和54)年4月1日、転属配置先、盛岡
転属日、2006(平成18)年8月23日、転属配置先、郡山
廃車日、2019(令和元)年10月25日、郡山
画像番号DSC 8346.JPGの画像は、
マニ50-2051
新製落成日、1978(昭和53)年4月17日、新製配置、隅田川、製造、新潟鐵工所
転属日、1979(昭和54)年4月1日、転属配置先、盛岡
廃車日、2019(令和元)年5月17日、仙台
スユニ50形
スユニ60形などの旧形郵便・荷物合造車を置換えるため、
計画された郵便荷物合造車で、
1978年(昭和53年) - 1981年(昭和56年)に80両
(スユニ50 2001 - スユニ50 2063・スユニ50 501 - スユニ50 517) が製作された。
台枠も含めて車体は完全に新製したが、
台車のTR47および自動連結器一式は廃車となった
スハ43形やスハネ16形などから流用したもので、
名義上は新製ではなく、種車になった車両の改造扱いである。
本州以南用の0番台と北海道用の500番台がある。
0番台は全車電気暖房を備えており、番号は2000番台となっている。
外部塗色は青15号である。技術力の維持と向上をはかるため、
本形式はすべて国鉄工場で施工している。
当初は100両改造される計画であったが、
郵便・荷物輸送の低迷により80両に下方修正された。
1986年(昭和61年)の郵便・荷物輸送の廃止とともに大部分が廃車されており、
JRへの承継は北海道3両、東日本4両にとどまった。
現存している車両は北海道・東北で救援車代用として配置されている。
画像番号IMG 1187.JPGの画像は、
スユニ50-2037
製造時形式車番、スハフ42-312
新製落成日、1955(昭和30)年3月15日、新製配置、宮原、製造、日本車輌
転属日、1972(昭和47)年3月14日、転属配置先、福知山
改造後、スユニ50-2037
改造施行日、1980(昭和55)年11月29日、落成配置、郡山、改造、幡生工場
廃車日、2014(平成17)年12月1日、郡山
「リゾートエクスプレスゆう」用電源車
水郡線など非電化区間直通運転時のサービス電源供給用電源車として、
大宮工場でマニ50 2186を改造した。
鉄道ファンからは通称「ゆうマニ」と呼ばれる。
水郡線営業所に配置されていた。
改造の内容を以下に示す。
外部塗色は「ゆう」編成と同一の配色とした。
荷物室の半分はディーゼル発電機(三相交流270kVA/440V)を収容する機械室に転用し、
機械室側は荷物扉を撤去して通風孔と採光窓を設けた。
荷物室の荷重は8tに減少したが、車両記号の変更はない。
非電化区間では機関車の次位に本車を連結するため、
連結器は電車・機関車のどちらとも連結できる双頭連結器に交換。
双頭連結器・電源供給設備の機能を活用できることから、
配給輸送・廃車回送など電車編成を、
機関車で牽引する際の控車としても頻繁に使用されていた。
2019年7月3日、JR横浜線と東急田園都市線の交わる長津田駅にて、
JR東日本の「マニ50 2186」が東急電鉄に譲渡されました。
北海道胆振東部地震の影響を受けた北海道を応援するため、
JR北海道・JR東日本・東急電鉄・JR貨物の4社で連携し、
観光振興と地域活性化を目的として「THE ROYAL EXPRESS」を運行。
画像番号DSC 7406.JPGの画像は、
マニ50-2186
新製落成日、1980(昭和55)年7月7日、新製配置、隅田川、製造、新潟鉄工所
転属日、1991(平成3)年3月1日、転属配置先、常陸大子
「サービス電源供給用電源車化」
改造施行日、1991(平成3)年8月16日、改造工、大宮工場
廃車日、2018(平成31)年7月28日、水郡線営業所
東武鉄道(旧国鉄・JR)12系
SL列車の運行に際し譲り受けた12系は、国鉄からJR四国に承継され、
今回、東武へ移って、
その後、「SL大樹」およびSL大樹ふたら用に展望車として改造され復籍し、
2021年(令和3年)10月17日から営業運転を開始した。
内装では元の座席やカーペット等をすべて撤去し、
ボックスシートへの交換とフック付きの大型テーブルの設置、
トイレの撤去と乗務員室への用途変更、
下今市寄りをオープンデッキ構造として、ドアを埋めた。
車両下部には車外向けスピーカーが設置され、
沿線からのおもてなしに対して感謝を伝えるために、
メロディーホーンを鳴らすことが可能となっている。
画像番号DSC 8208.JPGの画像は、
2号車 オハテ12-1
製造時形式車番、オハ12 5
新製落成日、1969(昭和44)年6月11日、新製配置、宮原、製造、新潟鉄工所
量産化改造
改造施行日、1972(昭和47)年4月20日、改造、土崎工場
転属日、1972(昭和47)年、転属配置先、竜華
万博PR用サイエンストレイン化改造
改造施行日、1984(昭和59)年9月7日、改造、土崎工場
現車両復元カーペット車化改造
改造施行日、1985(昭和60)年5月、改造、高砂工場
転属日、1988(昭和63)年4月19日、転属配置先、高松
グリーン車・2&1シート化改造
改造後、オロ12-5
改造施行日、1988(昭和63)年4月19日、改造、多度津工場
廃車日、2010(平成22)年3月31日、高知
東武鉄道へ譲渡
2016(平成28)年、
東武鉄道入籍、
2021(令和3)年10月13日、
展望デッキ付き展望車としてリニューアル改造
改造後、オハテ12 2
改造施行日、2021(平成27)年10月、改造、南栗橋車両管区
ぶどう色2号(茶色)化塗装変更
2021(令和3)年11月2日、施行工、南栗橋車両管区
オハテ12 1
室内は大型テーブル付きのボックスシートで64席が配置される。
展望スペース下部にはメロディホーンが設置され、
車体塗色は、ぶどう色2号(茶色)、窓下には国鉄の2等車に使用される。
画像番号DSC 6028.JPGの画像は、
2号車 オハテ12-2
製造時形式車番、オハ12 10
新製落成日、1969(昭和44)年6月19日、新製配置、宮原、製造、新潟鉄工所
量産化改造
改造施行日、1972(昭和47)年5月30日、改造、土崎工場
転属日、1972(昭和47)年、転属配置先、竜華
転属日、1988(昭和63)年6月14日、転属配置先、高松
グリーン車・2&1シート化改造、
改造後、オロ12-10
改造施行日、1988(昭和63)年6月14日、改造、多度津工場
廃車日、2010(平成22)年3月31日、高松
東武鉄道へ譲渡
2016(平成28)年、
東武鉄道入籍、
2021(令和3)年10月13日、
展望デッキ付き展望車としてリニューアル改造
改造後、オハテ12 2
改造施行日、2021(平成27)年10月、改造、南栗橋車両管区
オハテ12 2
室内は大型テーブル付きのボックスシートで64席が配置される。
展望スペース下部にはメロディホーンが設置され、
車体塗色は、青色15号で、窓下には国鉄の2等車に使用される。
東武鉄道(旧国鉄・JR)14系
SL列車の運行に際し譲り受けた14系は、国鉄からJR東海に承継され、
さらにJR四国へ移り、JR北海道からも14系客車を譲り受けて、
2015年に除籍されて保存車となったが、今回、東武へ移って、
可能な限りデビュー当時の姿に修復。
営業運転に使用できるよう復活させた。
譲渡当初は車籍がなく、
南栗橋車両管区にて留置状態が続いていた。
その後、「SL大樹」およびSL大樹ふたら用に展望車として改造され復籍し、
2021年(令和3年)10月17日から営業運転を開始した。
画像番号DSC 6024.JPGの画像は、
1号車 スハフ14-1
新製落成日、1972(昭和47)年9月30日、新製配置、秋田、製造、新潟鉄工所
転属日、1985(昭和60)年3月14日、転属配置先、沼津
転属日、1988(昭和63)年3月13日、転属配置先、名古屋
転属日、1997(平成9)年4月1日、転属配置先、美濃太田
廃車日、2005(平成17)年5月24日、美濃太田
JR四国へ譲渡
2005(平成17)年5月24日、転属配置先、高松
廃車日、2016(平成28)年3月31日、高松
東武鉄道へ譲渡
2016(平成28)年、
東武鉄道入籍、
2017(平成29)年5月14日、
画像番号DSC 6032.JPGの画像は、
3号車 オハフ15-1
新製落成日、1972(昭和47)年9月30日、新製配置、秋田、製造、新潟鉄工所
転属日、1982(昭和57)年11月15日、転属配置先、尾久
転属日、1985(昭和60)年3月14日、転属配置先、名古屋
転属日、1993(平成5)年8月1日、転属配置先、美濃太田
JR四国へ譲渡
2005(平成17)年5月24日、転属配置先、高松
廃車日、2016(平成28)年3月31日、高松
東武鉄道へ譲渡
2016(平成28)年、
東武鉄道入籍、
2017(平成29)年5月14日、
画像番号DSC 8204.JPGの画像は、
1号車 スハフ14-5
新製落成日、1972(昭和47)年11月20日、新製配置、秋田、製造、富士重工
転属日、1982(昭和57)年11月15日、転属配置先、尾久
転属日、1985(昭和60)年3月14日、転属配置先、名古屋
転属日、1993(平成5)年4月1日、転属配置先、美濃太田
廃車日、2005(平成17)年5月24日、美濃太田
JR四国へ譲渡
2005(平成17)年5月24日、転属配置先、高松
廃車日、2016(平成28)年3月31日、高松
東武鉄道へ譲渡
2016(平成28)年、
東武鉄道入籍、
2017(平成29)年5月14日、
ぶどう色2号(茶色)化塗装変更
2021(令和3)年5月26日、施行工、南栗橋車両管区
北海道向け500番台改造(座席車)
蒸気管と旧形客車併結用のKE85-KE54特殊両栓ジャンパ線装備
1981年(昭和56年)、
北海道の急行列車で使われていた旧形客車の置き換えのため、
本州内及び本州-九州直通の急行列車廃止で余剰になっていた
本系列に暖房強化や空気圧縮機の大型化、
これに伴いスハフ14形1両当たり自車を含めた6両から4両給電に変更、
冬季の着雪・凍結対策として折戸であった客用扉の引戸化など、
道内向け改造を施した番台区分。
当初から、荷物車、郵便車、寝台車(当初は10系寝台車と混結されていた)などの
旧形客車との併結が前提であったため、
12系客車と同じく機関車からの暖房用蒸気を旧形客車に送るための、
暖房用蒸気の引通管が新たに設けられた。
オハ14 501 - 539・スハフ14 501 - 509が改造された。
画像番号DSC 8212.JPGの画像は、
3号車 スハフ14-501
新製落成日、1974(昭和47)年2月20日、新製配置、名古屋、製造、日本車輌
製造時形式車番、スハフ14 43
転属日、1980(昭和55)年8月、転属配置先、函館
北海道向け500番台化改造
改造施行日、1980(昭和55)年8月、改造、五稜郭工場
転属日、1988(昭和63)年3月13日、転属配置先、札幌
転属日、1988(昭和63)年11月11日、転属配置先、函館
自動販売機設置
施行日、1992(平成4)年3月27日、改造、五稜郭工場
転属日、2002(平成14)年12月5日、転属配置先、札幌
廃車日、2016(平成28)年3月31日、函館
東武鉄道へ譲渡
2017(平成29)年2月23日、
東武鉄道入籍、
2020(令和2)年7月30日、
ぶどう色2号(茶色)化塗装変更
2021(令和3)年6月19日、施行工、南栗橋車両管区
スハフ14 501
スハフ14形0番代を北海道向けに改造した電源機関付き座席緩急車
客用扉の引戸化、サービス用電源としてDMF15HZ-G形
ディーゼルエンジン駆動(出力270PS)による
DM93発電機(容量210kVA)を搭載
定員64名。