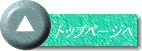画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。

画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。
415系電車
日本国有鉄道(国鉄)が設計・製造した交直流両用近郊形電車。
国鉄分割民営化後は東日本旅客鉄道(JR東日本)と、
九州旅客鉄道(JR九州)に継承されたほか、
JR東日本が設計・製造した車両や西日本旅客鉄道(JR西日本)が、
113系を改造・編入した車両が存在する。
以上の系列に続き、1971年(昭和46年)から製造が開始された。
交流50/60Hz両用のTM14形主変圧器を搭載する「三電源方式」となっている。
1500番台 [ステンレス鋼製車両]
1986年から製造を開始した。
軽量なステンレス製車体、ボルスタレス台車といった211系に用いられた技術が採用されている。
従来の車両と相互に連結して運転するため、
電装品やブレーキシステムは500・700番台に準じている。
従来車と性能を揃えるため、軽量化による加減速力の増分は、
主電動機の限流値を低く設定することで相殺している。
また、従来車ではすべてのクハ411形にC1000形を搭載していた空気圧縮機は、
1600番台のみC2000形1台搭載と改められている。
JR東日本では1991年まで製造が続き、行先票(サボ)受けの有無、
運転室仕切窓の大きさなど、細部に差異が見られる。
車内はトイレ対向部を除いてロングシートとなっている。
なお、モハ414形1500番台の前位側(パンタグラフ搭載側)の客室は、
機器があるため座席が1人分少ない4人掛けとなっており、
窓や行先表示器の位置も若干異なっている。
最初に投入されたグループは車内放送用スピーカーも、
在来車と同様の箱型を各車に2基設置している。
2011年現在、勝田車両センターおよび南福岡車両区に配置されている。
編成構成は原ノ町・下関・門司港方から、
クハ411-1500 - モハ415-1500 - モハ414-1500 - クハ411-1600(トイレ付き)の4両である。
勝田車両センターでは700番台の中間電動車を連結した
7両編成のK820編成が存在していたが、
2005年7月18日に4両編成のK526編成に短縮された。
これに伴い旧K526編成だった1502・1602の編成はK626編成に改番されている。
また、JR東日本車は帯色が鋼製車の青20号を踏襲しているが、
JR九州車は落成当初より帯色が明るい青色(青25号)で、
その後屋上通風器が撤去された。
1989年度以降の増備車(モハ414-1524以後)は、主変圧器が50Hz専用のTM24に変更された。
本来なら別系列もしくは別区分番台となってもおかしくないが、
広域転配を想定していないため、続番となった。
南福岡に配置された車両(FM1509 - 1521編成)は本来勝田に投入する予定で、
南福岡には捻出した100番台を転用して、
421系低運転台車などを置き換える計画だったが、
非冷房車の置き換えにあたってイメージアップのために、
直接新車を投入することとなった。
オールロングシートでありながら、
熊本 - 門司港・下関間のような長距離列車に充てられていたため、
一時は禁煙車を除きロングシート部に灰皿を設置するなどの工夫がなされていた。
1両のみ存在したサハ411-1601はMG・CP搭載のため1600番台に区分されている。
2005年6月までは、後述する2階建普通車の
クハ415-1901と同じK880編成に組み込まれており、
勝田方よりクハ415-1901 - モハ415-1535 - モハ414-1535 - サハ411-1601 - クハ411-1534
モハ415-1534 - モハ414-1534 - クハ411-1634の8両固定で運用されていた。
その後は、2007年まで500番台と700番台混結のK810編成に組み込まれていた。
このグループは、2007年3月18日ダイヤ改正での
普通鋼製車をE531系への置き換え後も常磐・水戸線で運用を続けているが、
常磐線上野口の中距離電車はグリーン車を連結した同系列に統一し、
同系列の最高速度130km/hの性能を本格的に活用するダイヤ構成に移行されたため、
常磐線では友部 - 原ノ町間の運用となり、上野口からは撤退した。
また、上記の転用で余剰となる初期に製造された3編成と、
サハ411-1601・1701(後述)・モハ415・414-1522は廃車予定とされ、
中間車の4両は2007年10月から2008年5月までに廃車となった。
なお、元K525編成のクハ411-1501などの1編成4両は、
500番台の2編成とともに、2008年12月にJR九州に譲渡された(12月24日付で廃車)
後、小倉工場で整備され、2009年6月23日付でFM1501編成として入籍。
2009年6月末より営業運転を開始した。
車体の帯色は青25号に変更されているが、
連結部の外幌部分のみ勝田時代の青20号のまま残されている。
一方、K626・K526編成のクハ411-1502・1503など8両は、
2009年度上半期に廃車となった。
K528編成
画像番号IMG 0588.JPGの画像は、
クハ411−1605
新製落成日、1986(昭和61)年2月26日、新製配置、勝田、製造、日本車輌
廃車日、2017(平成29)年5月25日、勝田
画像番号IMG 0580.JPGの画像は、
モハ414−1505
新製落成日、1986(昭和61)年2月26日、新製配置、勝田、製造、日本車輌
廃車日、2017(平成29)年5月25日、勝田
画像番号IMG 0571.JPGの画像は、
モハ415−1505
新製落成日、1986(昭和61)年2月26日、新製配置、勝田、製造、日本車輌
廃車日、2017(平成29)年5月25日、勝田
画像番号IMG 0560.JPGの画像は、
クハ411−1505
新製落成日、1986(昭和61)年2月26日、新製配置、勝田、製造、日本車輌
廃車日、2017(平成29)年5月25日、勝田
K535編成
画像番号IMG 0770.JPGの画像は、
クハ411−1625
新製落成日、1989(平成元)年8月29日、新製配置、勝田、製造、近畿車輌
廃車日、2016(平成28)年12月28日、勝田
画像番号IMG 0774.JPGの画像は、
モハ414−1525
新製落成日、1989(平成元)年8月29日、新製配置、勝田、製造、近畿車輌
廃車日、2016(平成28)年12月28日、勝田
画像番号IMG 0780.JPGの画像は、
モハ415−1525
新製落成日、1989(平成元)年8月29日、新製配置、勝田、製造、近畿車輌
廃車日、2016(平成28)年12月28日、勝田
画像番号IMG 0788.JPGの画像は、
クハ411−1525
新製落成日、1989(平成元)年8月29日、新製配置、勝田、製造、近畿車輌
廃車日、2016(平成28)年12月28日、勝田
クハ411−1601〜
ステンレス車体で上野・小山方のT'c車で、便所付き。
定員132(座席55)名。
モハ414−1501〜
ステンレス車体のM'車で、交流機器を搭載。
車体は、直流近郊形の211系に準じており、
台車はボルスタレスのDT50Cとなったほかは、
機器類は500番代に準じている。
ロングシート仕様。
定員150(座席62)名。
モハ415−1501〜
ステンレス車体のM車で、直流機器を搭載。
定員156(座席64)名。
クハ411−1501〜
ステンレス車体で原ノ町方のTc車で、便所なし。
台車はTR235C。
定員142(座席58)名。
クハ415-1901
定員156人。116人分の座席は客用扉付近をロングシートとしたほかは、
1階および車体後部が2+2配列、2階は2+3配列クロスシートとした。
1991年に日本車輌製造にて1両のみ試験的に製造された。
AU714形集約分散式冷房装置を2基搭載。台車もTR235H形と本形式独自のものを装着する。
他の1500番台車とは異なり、
客用扉が片側2か所のみでラッシュ時の乗降に時間を要する欠点から、
基本的に上野 - 勝田間で朝の上りと夕方の下りは停車駅の少ない通勤快速に、
朝の下りはラッシュ後、夕方の上りはラッシュ前に限定して運用された。
1両のみの製造で増備は行われず、
2006年に廃車されたが、運用成果は215系の設計に反映された。
画像番号FH0316.JPGの画像は、
クハ415−1901
新製落成日、1991(平成3)年3月9日、新製配置、勝田、製造、日本車輌
廃車日、2006(平成18)年3月11日、勝田
クハ415-1901
混雑緩和と着席率向上を目的として、
1991(平成3)年に試作車として新製された2階建ての制御車で、
1両のみの存在した。
2階は2+3列、1階は2+2列の固定クロスシート、
前位寄りと後位寄りの1階部分はセミクロスシートとなっている。
台車はTR235H。冷房装置はAU714。
定員156(座席116)名。
211系
1985年(昭和60年)に登場した直流近郊形電車。
本系列は、これらに代わるフルモデルチェンジ車であり、
軽量ステンレス製車体や構造の簡便なボルスタレス台車、
電機子チョッパ制御よりも簡便かつ安価に、
回生ブレーキが使用可能で抵抗制御を基本とした界磁添加励磁制御、
応答性の高い電気指令式ブレーキや簡易的なモニタ装置など、
省エネルギーや保守費低減に配意した新機軸が各所に採用されている。
これらは通勤形電車の205系で先に採用されたものであるが、
本来は近郊形電車用のシステムとして開発されていたものである。
ユニットあたりの力行性能の向上により、電動車比率を下げ、
2M3T編成で25‰区間までの通常の使用ができる設計とし、
新製コストと運営コストの減少を狙った設計とした。
これにより2M3T編成においても113系・115系の2M2T編成と同等以上の走行性能をもつ。
車体は、片側3か所に両開きの扉を設けた国鉄近郊形電車の基本的構成であるが、
両端の側出入口の位置を若干車端に寄せた配置としている。
外板間の車体幅は、従来の2900mmから初めて2950mmまで拡大され、
裾絞りが大きくなっている。また暖地・平坦線用の113系と、
寒地・勾配線用の115系を統合し、
細部の仕様変更を行うことで両系列の取替に対応している。
また座席は従来と同様のセミクロスシートの他、
長距離通勤の増加に伴う混雑に対応するためにオールロングシートの車両も製造した。
クロスシート・ロングシートともバケットタイプとし、
ロングシートの1人分の幅を広げた。
クロスシートはシートピッチ1,490mmのままでスペースと通路幅を広げた。
また、セミクロスシート車も混雑緩和のため、
415系700番台同様車端部はロングシートとした。
国鉄時代は付属編成のみがオールロングシートとされたが、
国鉄分割民営化後の増備車はすべてオールロングシートが基本となっている。
さらに、車体の構造と台車は同時期に製造された415系1500番台にも採用され、
民営化後も車体や制御システムの設計を流用した車両が登場している。
1000・3000番台(寒冷地仕様車)
0・2000番台を基本に宇都宮線と高崎線(東北本線上野口)の
使用に配慮した寒地仕様車で、
115系非冷房車の置換え用として登場したものである。
1000番台はセミクロスシート車、3000番台はロングシート車で、
ともにスノープラウ(排雪器)、耐雪ブレーキ、半自動ドア、
レールヒーターなどの耐寒耐雪装備がなされている。
編成は、東海道本線用0・2000番台と異なり普通車のみの5両編成 (McM'TTTc') で、
1000・3000番台共同一である。
東海道本線用には無い
制御電動車が用意されたのは、
将来3両編成に改組して地方路線に転属させられるように考慮したためである。
国鉄時代には、セミクロスシート車1000番台11本55両と、
ロングシート車3000番台22本110両の計165両が製造され、
民営化後は東海道本線用と同様にロングシートの3000番台のみが、
1991年までに40本200両が増備されている。
国鉄時代には、1000番台×1本+3000番台×2本で、
15両編成を組むように計画されたため、
1000番台と3000番台の運用も分けられていたが、
3000番台のみの増備となった民営化後は共通運用となった。
なお、2000番台と同様運転席背後の仕切窓、
荷物棚、吊手などに製造年次による変化がある。
新製配置は1000番台が全車両新前橋電車区(現・高崎車両センター)で、
3000番台は当初クモハ211形・モハ210形・クハ210形の車番
3001 - 3046が新前橋電車区、
3047 - 3062が小山電車区(現・小山車両センター)配置であったが、
2000年(平成12年)からE231系が小山電車区に新製配置になったことにより、
同年12月に新前橋区に配置が集約されている(現在は一部が幕張車両センターに転出)。
そのため、上野発着の東北本線では宇都宮線列車よりも高崎線列車の運用の方が多い。
優先席の吊革は高崎車・幕張車共に全ての編成でE233系タイプのものに交換済みである。
0・2000番台と同様に、2008年秋頃より、
モケット地をすおう色から青緑色に交換しているほか、
順次PS33E形シングルアーム式パンタグラフへの取り替え及び増設(一部)が行われた。
2006年9月4日、両毛線前橋駅 - 前橋大島駅間において踏切事故が発生し、
クハ210-3013が側構体に数メートルにわたって穴が開くなどの大きな損害を受けた。
当該車は大宮総合車両センターに臨時入場のうえ、復旧工事が行われた。
現物での復旧が困難な側構体と窓枠については、同時期に廃車となり、
長野総合車両センターで解体が進められていたサハ211形から該当する部分を切り取り、
これを取り付ける工法で復旧が行われた。
このため、出場後のクハ210-3013は復旧部分のみ、
ステンレスの光沢や帯色に相違が見られる。
前述した田町車両センターに続いて、
2012年度より高崎車両センター向けにもE233系3000番台が投入され、
本系列の置き換えが始まっている。
2013年3月16日のダイヤ改正で宇都宮線上野口の運用から撤退した。
211系3000番台5両 A28編成
画像番号DSC 4158.JPGの画像は、
新製落成日、1988(昭和63)年4月19日、新製配置、新前橋、製造、川崎重工
転属日、2005(平成17)年12月10日、転属配置先、高崎
半自動スイッチ取付工事
施行日、2012(平成24)年5月12日、
転用改造日、2016(平成28)年7月29日、大宮総車セ
延命工事
施行日、2024(令和6)年9月11日、
画像番号DSC 4160.JPGの画像は、
サハ211−3056
新製落成日、1988(昭和63)年4月19日、新製配置、新前橋、製造、川崎重工
半自動スイッチ取付工事
施行日、2012(平成24)年5月12日、
転用改造日、2016(平成28)年7月29日、大宮
廃車日、2015(平成27)年7月2日、高崎
画像番号DSC 4162.JPGの画像は、
サハ211−3055
新製落成日、1988(昭和63)年4月19日、新製配置、新前橋、製造、川崎重工
転属日、2005(平成17)年12月10日、転属配置先、高崎
半自動スイッチ取付工事
施行日、2012(平成24)年5月12日、
転用改造日、2016(平成28)年7月29日、大宮総車セ
延命工事
施行日、2024(令和6)年9月11日、
画像番号DSC 4164.JPGの画像は、
モハ210−3028
新製落成日、1988(昭和63)年4月19日、新製配置、新前橋、製造、川崎重工
転属日、2005(平成17)年12月10日、転属配置先、高崎
半自動スイッチ取付工事
施行日、2012(平成24)年5月12日、
転用改造日、2016(平成28)年7月29日、大宮総車セ
延命工事
施行日、2024(令和6)年9月11日、
画像番号DSC 4166.JPGの画像は、
クモハ211−3028
新製落成日、1988(昭和63)年4月19日、新製配置、新前橋、製造、川崎重工
転属日、2005(平成17)年12月10日、転属配置先、高崎
パンタグラフシングルアーム化
施行日、2009(平成21)年6月24日、施行工、大宮総車セ
半自動スイッチ取付工事
施行日、2012(平成24)年5月12日、
転用改造日、2016(平成28)年7月29日、大宮総車セ
延命工事
施行日、2024(令和6)年9月11日、大宮総車セ
クハ210-3001〜(T'c)
3000番代の偶数向制御車。
便所付きで、定員132(座席55)名。
サハ211-3001〜(T)
3000番代の付随車。
定員156(座席64)名。
モハ210-3001〜(M)
クモハ211-3001〜とユニットを組む中間電動車で、
190kVA MG・CPを搭載している。
定員156(座席64)名。
クモハ211-3001〜(Mc)
3000番代の奇数向制御電動車で、
シングルアームパンタグラフ(PS35C)を1基装備し、
制御装置、励磁装置、主抵抗器などを床下に搭載する。
冷房装置はAU75G、台車はDT50B。
定員142(座席50)名。
719系
東日本旅客鉄道(JR東日本)の交流近郊形電車。
従来、主に急行形電車が使用されていた
JR東日本仙台地区の輸送改善を目的として、
1989年(平成元年)より投入された。
急行形電車は1両につき客用扉が端部に2か所配され、
また客室と乗降口の間に仕切りがあり、
座席はクロスシート主体であったことから、
ラッシュ時の混雑に対応しにくかった。
また、3両編成が基本であることから、柔軟な輸送力調整が難しかった。
さらに、初期の451系・453系は特に車齢が高く、
陳腐化が進んでいたことなどから、
輸送状況に見合った車両として開発されたのがこの719系である。
1991年(平成3年)の奥羽本線福島 - 山形間改軌の際には、
一部仕様改修を施した5000番台車が投入され、
同区間の客車列車を置き換えた。
クモハ719形 (Mc) + クハ718形 (Tc') の2両編成を基本とし、
最大8両編成まで併結が可能である。
分割・併合を容易にするために自動解結装置と電気連結器を備える。
片側3扉のステンレス車体は211系に近縁の外観であるが、
同系5000番台のように助士席側正面窓と貫通扉窓が拡大され、
側面の窓配置も異なる。
座席配置はセミクロスシートだが、
クロスシート部分は特異な「集団見合い型」の配置である。
車内は淡いクリーム色の化粧板、あずき色の座席モケット、
薄茶色の床材(5000番台車はクリーム色)という
暖色系のカラースキームとなっている。
また、従来仙台地区で運用されていた
417系や717系(0・100番台)と同様に乗降口の脇に、
ガラス製の風防が設置されている。
トイレは和式で、クハ718形の連結面寄りに設置されている。
〔基本形・オリジナル色〕
画像番号DSC 7210.JPGの画像は、
719系0番台 H−1編成
クモハ719−1
新製落成日、1989(平成元)年12月25日、新製配置、仙台、製造、東急車輌
廃車日、2018(平成30)年4月14日、仙台
画像番号DSC 7208.JPGの画像は、
クハ718−1
新製落成日、1989(平成元)年12月25日、新製配置、仙台、製造、東急車輌
廃車日、2018(平成30)年4月14日、仙台
画像番号DSC 4318.JPGの画像は、
719系0番台 H−30編成
クモハ719−30
新製落成日、1990(平成2)年8月24日、新製配置、仙台、製造、東急車輌
廃車日、2019(平成31)年4月14日、仙台
画像番号DSC 4320.JPGの画像は、
クハ718−30
新製落成日、1990(平成2)年8月24日、新製配置、仙台、製造、東急車輌
廃車日、2019(平成31)年4月14日、仙台
〔シングルアーム式パンタグラフ・スカート形状換装車・オリジナル色〕
画像番号IMG 1738.JPGの画像は、
719系0番台 H−16編成
クモハ719−16
新製落成日、1990(平成2)年5月24日、新製配置、仙台、製造、東急車輌
廃車日、2019(平成27)年8月10日、仙台
画像番号IMG 1745.JPGの画像は、
クハ718−16
新製落成日、1990(平成2)年5月24日、新製配置、仙台、製造、東急車輌
廃車日、2019(平成27)年8月10日、仙台
〔シングルアーム式パンタグラフ・スカート形状換装車・磐越西線用あかべぇ色〕
画像番号IMG 1702.JPGの画像は、
719系0番台 H−10編成
クモハ719−10 あかべぇ色
新製落成日、1990(平成2)年4月27日、新製配置、仙台、製造、東急車輌
転属日、2017(平成29)年3月29日、転属配置先、秋田
廃車日、2020(令和2)年3月14日、秋田
画像番号IMG 1706.JPGの画像は、
クハ718−10 あかべぇ色
新製落成日、1990(平成2)年4月27日、新製配置、仙台、製造、東急車輌
転属日、2017(平成29)年3月29日、転属配置先、秋田
廃車日、2020(令和2)年3月14日、秋田
クモハ719-1〜42
719系0番代の交流制御電動車 (Mc) で、
制御方式としてサイリスタ連続位相制御を搭載。
台車は廃車発生品のDT32
定員134 座席62名。
クハ718-1〜42
719系0番代の交流制御車で、
台車は廃車発生品のTR69、
CPを搭載、便所付き。
定員131 座席59名。
5000番台
奥羽本線標準軌区間(福島 - 新庄、愛称「山形線」)の普通列車用として、
1991年(平成3年)に全車が日本車輌製造で新製された
JRグループ初の在来線標準軌車両である。
標準軌用のボルスタレス台車DT60形・TR245形が新たに採用された他、
パンタグラフがシングルアーム式(2002年までは下枠交差式)である点、
客用扉にステップが設けられていない点、
車体の帯が上から「オレンジ(紅花色)+白+緑」である点が0番台車との相違である。
また、パンタグラフがシングルアーム式に交換された際にスカート形状も変更された。
EB装置、TE装置を搭載。保安装置はATS-P形である。
山形車両センターに2両編成12本(Y-1 - Y-12編成)、
合計24両が配置されている。
画像番号DSC 2396.JPGの画像は、
719系5000番台 Y11編成
クモハ719−5011
新製落成日、1991(平成3)年10月22日、新製配置、山形、製造、川崎重工
パンタグラフシングルアーム化
施行日、2001(平成13)年11月8日、
EB装置取付
施行日、2011(平成23)年1月7日、
画像番号DSC 2394.JPGの画像は、
クハ718−5011
新製落成日、1991(平成3)年10月22日、新製配置、山形、製造、川崎重工
セラジェット装置取付
施行日、2012(平成24)年2月23日、
EB装置取付
施行日、2011(平成23)年1月7日、
クモハ719-5001〜
制御電動車(Mc)で、
新庄方に連結される。
定員はステップの廃止により、0番代よりも立席が4名増えて138(座席62)名。
また、先頭部屋根上にも警笛が追加されている。
パンタグラフは当初、下枠交差式のPS104、
写真のように2001(平成13)年に全車シングルアーム化された。
クハ718-5001〜
制御車(T'c)で、
福島方に連結される。
定員はMc車と同様に0番代よりも立席が4名増えたため、
135(座席59)名。