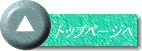画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。

画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。
 CIMG0838 |
 CIMG0836 |
CIMG2652 |
DSC_1648 |
 DSC_2036 |
 DSC_2048 |
 DSC_2098 |
 DSC_4092 |
DSC_4210 |
IMG_0006 |
 DSC_8776 |
 DSC_8778 |
FH133 |
IMG_0225 |
キハ185系気動車
キハ185系気動車は、
日本国有鉄道(国鉄)が開発し、
現在は四国旅客鉄道(JR四国)と、
九州旅客鉄道(JR九州)が保有する特急形気動車。
製造メーカーは、日本車輌製造、
新潟鐵工所(現・新潟トランシス)・富士重工業である。
1986年11月1日のダイヤ改正から営業運転を開始した。
国鉄の分割民営化を控えた1986年に、
四国地区向けに製造された車両の一つである。
従来四国の特急列車に用いられていたキハ181系の代替車ではなく、
老朽化した急行形のキハ58系・キハ65形の置き換えと、
同時に急行列車の特急格上げを行い、
経営基盤の脆弱が予想されるJR四国の経営安定化を図る目的で開発された。
また、短編成での小単位輸送に用いることを、
念頭に置いて設計されているほか、更に徹底したコストダウンも図られた。
画像番号IMG 0225.JPGの画像は、
キハ185−26
新製落成日、1988(昭和63)年12月23日、新製配置、高松、製造、富士重工
改造後、キロ185-26
改造施行日、2015(平成27)年3月6日、改造工、多度津工場
キハ185形0番台
片運転台を持つ普通車
行先表示器、トイレと洗面所を設置、26両製造。
定員60名、
キハ185-26
2015年にキクハ32-502のリニューアルに合わせて、
塗装・車内をアンパンマン仕様としグリーン車扱いとなったため、
形式が「キロ185-26」に変更された。
キハ185−26
機関(DMF13HS)
2015(平成27)年3月
キハ100形気動車
キハ100形気動車は、東日本旅客鉄道(JR東日本)の一般形気動車。
地方交通線の普通列車用として設計され、
セミクロスシート、トイレ付き、ワンマン運転対応。
乗務員室は進行方向に対して左側にしかない半室タイプを採用しており、
助士席に相当するスペースには乗客用のドアが設置されている。
そのため、ドアの位置が左右対称ではなくなっている。
ただ、車掌によるドア操作が可能なように、
小窓や車掌用ドアスイッチユニット
(通常は鍵が掛けられており、乗務員以外は操作できない)が設けられている。
0番台
46両が製造され、大船渡線、北上線、釜石線、山田線宮古 - 釜石間、
東北本線花巻 - 盛岡間および一ノ関 - 北上間で運用されている。
かつては間合い運用でIGRいわて銀河鉄道線盛岡 - 好摩間、
三陸鉄道南リアス線、三陸鉄道北リアス線、
奥羽本線横手 - 湯沢間にも入線していた時期があった。。
試作車
1990年(平成2年)1月から2月にかけ1、2が新潟鐵工所、3、4が富士重工業で製作された。
車体側の排障器は一般的な鋼板製のスカート形ではなく、
ステンレス製丸鋼管の3段組みとされ、
側面は吹き寄せおよびトイレ部分にもダミーガラスを使用して、
連続窓のように見せるデザインとなっている。
また、量産車と異なり、乗務員室の側窓が鋼製枠支持となっている。
登場当初は、先頭車の正面の左右が黒色に塗装されていたが、
後に量産車に合わせてベリーペールグリーンに変更された。
また、車体に雨どいを設置していなかったが、のちに量産車同様、
客用扉・乗務員室扉上部に取り付けられている。
ワンマン運転への対応は落成当初は準備工事のみとされ、
1991年(平成3年)に改造工事が行われている。
室内は1・2・3位側出入り口付近のロングシート2席ずつを収納式とし、
混雑時に対応している点が特徴である。
キハ100-1〜4
1990(平成2)年に量産先行車として、
1・2が新潟鐵工所、3・4は富士重工業で製造された。
写真は1・3位側を示すが、逆サイドの4位側は便所部分がダミー窓となっており、
JRマークが白色である。
また、2・3位の乗務員室側窓が押さえ金支持となっている。
新製以来一ノ関に配置され、北上線と大船渡線で使用されている。
画像番号DSC 2098.JPGの画像は、
キハ100−2
新製落成日、1990(平成2)年2月23日、新製配置、一ノ関、製造、新潟鉄工所
キハ100-1〜4
量産先行車
両運転台車
大船渡・北上・釜石・山田線用
セミクロスシートを備える。
トイレ設置
定員104(座席41)名で、補助席使用時は103(座席47)名。
キハ100-5〜8
1990(平成2)年度末の1991(平成3)年3月に、
富士重工業で製造された量産車(2次車)で、
量産先行車と同様にパイプスカートを装備しているが、
4位側の便所部分のダミー窓が廃止されたほか、
2・3位の乗務員室側窓がHゴム支持に変更された。
このグループも新製以来一ノ関に配置され、北上線と大船渡線で使用されている。
画像番号DSC 4092.JPGの画像は、
キハ100−6
新製落成日、1991(平成3)年3月12日、新製配置、一ノ関、製造、富士重工
キハ100-5〜8
量産車(2次車)
両運転台車
大船渡・北上・釜石・山田線用
セミクロスシートを備える。
トイレ設置
定員103(座席47)名
量産2次車
1991年(平成3年)6月から10月にかけ製造された9 - 46では、
スカートのパイプによる補強が廃止されたほか、
側面方向幕がHゴム押さえに変更されている。
室内はつり手の支持方式が曲げパイプからブラケット支持に変更されている。
製造は、9 - 29が富士重工業、30 - 46が新潟鉄工所である。
キハ100-9〜46
1991(平成3)年度の1991(平成3)年6?10月に、
富士重工業および新潟鐵工所で製造された3次車で、
パイプスカートを廃止し、側面の行先表示器はHゴム支持に変更された。
盛岡と一ノ関に新製配置されたが、21は2011(平成23)年度、
20は2014(平成26)年度に八戸に転属している。
9・12・30・38の4両は東日本大震災で津波により被災し、
2011(平成23)年6月に廃車となった。
画像番号DSC 1648.JPGの画像は、
キハ100−18
新製落成日、1991(平成3)年7月5日 新製配置、盛岡、製造、富士重工
画像番号DSC 2036.JPGの画像は、
キハ100−33
新製落成日、1991(平成3)年8月29日、新製配置、八戸、製造、新潟鉄工所
キハ100-9〜46
量産車(3次車)
両運転台車
大船渡・北上・釜石・山田線用
セミクロスシートを備える。
トイレ設置
定員103(座席47)名
200番台
5両が製造され、大湊線および青い森鉄道線青森 - 八戸間で運用されている。
1992年に発生した成田線大菅踏切事故を受けての設計変更が行われ、
運転台部分の強化のため車端部が各250mm延長された。
客用ドアは0番台のプラグ式から引き戸式に変更された。
画像番号DSC 4210.JPGの画像は、
キハ100−204
新製落成日、1993(平成5)年9月21日、新製配置、八戸、製造、富士重工
画像番号IMGP0150.JPGの画像は、
キハ100−205
新製落成日、1993(平成5)年9月21日、新製配置、八戸、製造、富士重工
キハ100-201〜205
大湊線・青い森鉄道用
両運転台車
セミクロスシートを備える。
トイレ設置
3位側出入口脇に車椅子スペース設置
定員103(座席44)名。
キハ101形
左沢線用に13両が製造された。
オールロングシートで、トイレなし、ワンマン運転対応。
車内の床材はピンクの色の物とブルーの色の物がある。
ロングシートに座ると床材の足元部に黒い線が敷いてあるが、
これは足を線の内側に置くようにするためである。
優先席近くにはオレンジ色のつり革が設置されている。
車体塗色は同線独自のものを使用するとともに、
側面に「FRUITS LINER(フルーツライナー)」の
アルファベット文字が施されている。
運賃表示器は設置車と未設置車があり、
未設置車については運賃表示器の部分に運賃表のステッカーを貼付してある。
乗務員室は進行方向に対して左側にしかなく、
助士席に相当するスペースには乗客用のドアが設置されている。
そのため、ドアの位置が左右対称ではなくなっている。
ただ、車掌によるドア操作が可能なように小窓や車掌用ドアスイッチユニット
(通常は鍵が掛けられており、乗務員以外は操作できない)、
乗客が立ち入らないように柵などが設置されている。
当初は新庄運転区配置であったが、
山形新幹線の新庄延伸に伴い山形電車区(現・山形車両センター)に転配された。
キハ101-12とキハ101-13には左沢寄りにメガホンが設置されている。
キハ101-1〜11
左沢線用として1993(平成5)年に1〜6、翌94(平成6)年に 7〜11、
が新潟鐵工所で製造された。
画像番号DSC 2048.JPGの画像は、
キハ101−2
新製落成日、1993(平成5)年9月21日、新製配置、新庄、製造、新潟鉄工所
転属日、1999(平成11)年3月12日、転属配置先、山形
画像番号IMGP0266.JPGの画像は、
キハ101−7
新製落成日、1993(平成5)年9月21日、新製配置、新庄、製造、新潟鉄工所
転属日、1999(平成11)年3月12日、転属配置先、山形
キハ101-1〜11
左沢線用 両運転台車
トイレなし
オールロングシートを備える。
定員107(座席44)名。
キハ101-12・13
左沢線用として1997(平成9)年に増備された
11・12は側面助士席側窓の形状が異なっている。
左沢方にメガホンが設置
画像番号FH133.JPGの画像は、
キハ101−13
新製落成日、1997(平成9)年2月4日、新製配置、新庄、製造、新潟鉄工所
転属日、1999(平成11)年3月12日、転属配置先、山形
キハ101-12・13
左沢線用 両運転台車 ラストグループ後期車
トイレなし
オールロングシートを備える。
定員107(座席44)名。
キハ110系気動車
東日本旅客鉄道(JR東日本)の一般形気動車。
200番台 キハ110形50両、
キハ111・112形2両編成21本の計92両が製造された。
そのうち、キハ110形14両とキハ111・112形2両編成3本の計20両は、
後述の300番台改造車である。
ドアが引き戸式となりステップ高さも下げられた。
羽越本線、磐越西線、八高線、飯山線、陸羽東線、陸羽西線、米坂線に投入された。
陸羽西線と陸羽東線に投入された車両
(キハ110-237 - 245、キハ111・112-213 - 221)は専用塗装とし、
先頭車前面左下に「奥の細道」の文字が表記されている。
また、窓側に45°回転あるいは通路側に180°回転可能な1人掛けクロスシートを備え、
車窓から景色を眺めるように座ることができる車両も存在する。
さらにその2線のキハ111・112形は、他の路線のそれとは仕様が異なり、
側面の行先表示機はキハ112形にのみ車端部に設置されている。
また、キハ111形の便所も同様に車端部に移設されている。
300番台改造車は、テーブルを兼ねていた窓枠がそのまま残ったほか、
蛍光灯にはカバーがかけてあり、
特急列車で使われていた面影を残している。
0番台
キハ110形5両、キハ111・112形2両編成3本の計11両が製造された。
優等列車用で回転リクライニングシートを装備する。
登場当初は釜石線と山田線で運行される急行「陸中」で使用を開始した。
2011年現在は快速「はまゆり」をはじめ、
釜石線や山田線および東北本線日詰 - 盛岡間の普通列車に使用されている。
快速「はまゆり」では、主に指定席車両として使用される。
また、東日本大震災以前の2007年7月〜2011年3月までは、
気仙沼線快速「南三陸」の指定席車両でも使用されていた。
試作車は登場当時先頭車の正面の左右の塗装が黒色だったが、
後に量産車に合わせて、わずかに緑がかった
白色(ベリーペールグリーン)に変更された。
2011年現在、JRグループにおいて急行列車で、
使用されることを前提として新製された最後の車両である。
試作車 キハ112〜3
急行列車用の片運転台車で、
キハ111形と組み合わせで、ユニットを組む。
基本的に同番号の車両とユニットを組んで運用される。
試作車 キハ111〜3
急行列車用の片運転台車で、
キハ112形と組み合わせで、ユニットを組む。
基本的に同番号の車両とユニットを組んで運用される。
試作車 キハ110-1〜3
急行列車用の両運転台車試作車として、
基本的に同番号の車両とユニットを組んで運用される。
画像番号DSC 8776.JPGの画像は、
キハ112−3
新製落成日、1991(平成3)年3月30日、新製配置、盛岡、製造、新潟鉄工所
転属日、2021(令和3)年3月26日、転属配置先、小牛田
画像番号DSC 8778.JPGの画像は、
キハ111−3
新製落成日、1991(平成3)年3月30日、新製配置、盛岡、製造、新潟鉄工所
転属日、2021(令和3)年3月26日、転属配置先、小牛田
画像番号CIMG0836.JPGの画像は、
キハ112−3
※鉄道開業150年記念 レトロラッピング車両
画像番号CIMG0838.JPGの画像は、
キハ111−3
※鉄道開業150年記念 レトロラッピング車両
画像番号IMG 0006.JPGの画像は、
キハ110−3
新製落成日、1991(平成3)年3月30日、新製配置、盛岡、製造、新潟鉄工所
キハ111-1〜3
試作車
キハ112形とペアを組む片運転台車
回転リクライニングシートを備える。
トイレ設置
定員60名。
キハ112-1〜3
試作車
キハ111形とペアを組む片運転台車
回転リクライニングシートを備える。
トイレなし
定員64名。
キハ110-1〜3
試作車 両運転台車
回転リクライニングシートを備える。
トイレ設置
定員52名。