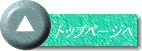画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。

画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。
キハ11形(キハ48000形)
キハ11形は、便所付き両運転台車で、
1955年から1957年にかけて74両が製造された。
このうち48016 - 48026の11両は、寒地向けの耐寒耐雪装備で、
北海道に新製配置されており、1957年の改番の際は100番台(101 - 111)に区分された。
定員は88人(座席74人、立席14人)である。
外観上の特徴として、客用扉下部の明かり窓が無いことがあげられる。
これは、この後北海道用として造られたキハ12、
キハ21、キハ22、キハユニ25の各形式にも引き継がれており、
同様に明かり窓は無い。
キハ112。
旧番号はキハ48035→キハ11 25)については、
21世紀に入っても車籍を保って営業運転に充てられたのち、
キハ11 25として、
2007年(平成19年)10月14日に開館した鉄道博物館に収蔵・展示されている。
画像番号IMG 1672.JPGの画像は、
キハ11−25
新製落成日、1956(昭和31)年8月8日、新製配置、真岡、製造、東急車輌
製造時形式旧車番、キハ48035、
譲渡廃車 回送は2月28日〜実施
那珂湊 2月29日、那珂湊回着
譲渡廃車日、1980(昭和55)年4月17日、譲渡先、茨城交通
茨城交通認可、1980(昭和55)年8月16日、
キハ112へ改番竣工
2005年1月29日茨城交通より搬出、
2005(平成17)年1月30日、廃車
2005年1月31日郡山総合車両センター着、
JR郡山総合車両センターにて修復
2007年6月4日鉄道博物館へ搬入。
キハ45系気動車
日本国有鉄道(国鉄)が1966年(昭和41年)から製造した一般形気動車
(近郊形気動車に分類している資料もある。
カテゴリについての詳細は後述)。
片運転台車の淘汰が進んだ時期にはキハ23系とも呼ばれた。
これは、国鉄車両称号規程に規定された制式の系列呼称ではないが、
同一の設計思想により設計・製造された気動車の形式群を便宜的に総称したものである。
1960年代中期、国鉄の普通列車用気動車は、地方線区向けにキハ20系が、
大都市近郊線向けはキハ35系がそれぞれ大量に増備されていた。
しかし、キハ20系は扉が片開き式で扉幅が850mmと狭いため、
ラッシュ時の客扱いに難があり、
キハ35系は3扉オールロングシートという通勤輸送に特化した構造であるため、
通勤時間帯以外の使用時に設備が乗客の要求する水準を満たせないという難があった。
1966年(昭和41年)から1969年(昭和44年)までに5形式が製造された
(製造を開始した昭和41年はまだキハ52が継続生産されていた)が、
電化の進捗に加えて戦前製機械式気動車の老朽化に伴う取替えが一巡したことなどで、
この時期には気動車の所要数をほぼ充足していたこともあり、
グループ全体で179両の製造にとどまった。
なお、本グループの落成に先立ち、
客車改造気動車のキハ40形(初代)・キハ45形(初代)がそれぞれ
キハ08形・キハ09形(2代)に改称されている。
キハ45形
1機関搭載の片運転台車で、
1966年(昭和41年)から1969年(昭和44年)にかけて暖地形の0番台74両、
寒地形の500番台22両、暖地形簡易郵便荷物車の600番台2両の
計98両が製造された本グループの基幹形式で、全国各地で使用された。
東日本旅客鉄道(JR東日本)に0番台11両・500番台14両の25両、
西日本旅客鉄道(JR西日本)に0番台30両・500番台8両の38両、
四国旅客鉄道(JR四国)に0番台24両、
九州旅客鉄道(JR九州)に0番台8両・600番台2両の10両、
計97両が承継されたが、非冷房に加えて片運転台車で運用上小回りが利かないこともあって、
民営化直後から急速に淘汰が進み、1995年(平成7年)に全廃となった。
※本形式のうち1967年(昭和42年)4月から5月にかけて製造された
32 - 36・42 - 61の25両は、製造直後、一時的に北海道に配置された。
これは夏季の観光客輸送など波動輸送に充当するためで、
函館・苗穂・旭川・池田・釧路に配置され、
シーズン終了後の1967年(昭和42年)秋に新潟や高松など、
道外の本来の配置予定区に転属している。
キハ45 1〜74
一般形の暖地向け片運転台車として製造されたグループで、
1966〜1969(昭和41〜44)年に日本車輌、新潟鉄工所、富士重工業で74両製造された。
キハ23形0番代と同様の車体構造で、室内はセミクロスシートとなっており、
出入口は2カ所設けられいる。後位には便所が設けられている。
機関は180PS(1,500rpm)のDMH17Hを1台搭載し、
台車はDT22C(TR51B)を使用している。
広島地区を中心に全国で使用されたが、
1995(平成7)年までに全車廃車となり形式消滅した。
機関はDMH17H、液体変速機はTC2AまたはDF115Aと、キハ58系と同様である。
画像番号IMGP1214.JPGの画像は、
キハ45−1(首都圏色)
新製落成日、1966(昭和41)年10月17日、新製配置、千葉、製造、日本車輌
転属日、1975(昭和50)年3月24日、転属配置先、水戸
転属日、1990(平成2)年3月10日、転属配置先、常陸大子
廃車日、1992(平成4)年5月1日、水郡線
画像番号IMGP1038.JPGの画像は、
キハ45−2(水郡色)
新製落成日、1966(昭和41)年10月17日、新製配置、千葉、製造、日本車輌
転属日、1975(昭和50)年3月24日、転属配置先、水戸
転属日、1990(平成2)年3月10日、転属配置先、常陸大子
廃車日、1992(平成4)年5月1日、水郡線
キハ45 1〜74
一般形の暖地向け片運転台車として製造されたグループで、
エンジンはDMH17H原形
トイレ設置。
定員124名。
キハ45 501〜522
キハ45形の寒地向け車両として製造されたグループで、
1967〜69(昭和42〜44)年に新製された。
画像番号IMGP1039.JPGの画像は、
キハ45−504(首都圏色)
新製落成日、1967(昭和42)年10月21日、新製配置、小牛田、製造、新潟鉄工所
転属日、1986(昭和61)年3月12日、転属配置先、水戸
転属日、1990(平成2)年3月10日、転属配置先、常陸大子
廃車日、1992(平成4)年5月1日、水郡線
キハ45 501〜522
一般形の寒地向け片運転台車として製造されたグループで、
エンジンはDMH17H原形
トイレ設置。
定員124名。
キハ23形500番台
主に東北地方を対象とした寒地仕様車である。
1台機関搭載の両運転台車で、
1966年(昭和41年)から1969年(昭和44年)にかけて暖地形の0番台33両、
寒地形の500番台21両の計54両が製造された。
国鉄時代は最後まで1両も廃車となることなく、
JR東日本に500番台11両、JR西日本に0番台30両・500番台10両の40両、
JR九州に0番台3両が承継された。
両運転台であることから、ワンマン改造や車両更新工事を施工されたものがあり、
比較的長く使用された。
2003年(平成15年)までJR西日本に残っていた520が本グループ最後の稼働車となった。
同じくJR西日本には1が廃車保留状態だったが、
前述の通り2009年(平成21年)6月10日付で廃車され、全廃された。
キハ23 501〜521
寒地向けに製造されたグループで、
1967〜1969(昭和42〜44)年に富士重工業、日本車輌、新潟鉄工所で21両製造された。
車体構造はキハ23形0番代を基本としているが、床下機器カバーが取り付けられ、
温水管による機器類の保温対策などが施されている。
主に東北、山陰地区に新製配置され使用された。
画像番号FH902.JPGの画像は、
キハ23−517(仙台色)
新製落成日、1969(昭和44)年1月24日、新製配置、郡山、製造、新潟鉄工所
転属日、1986(昭和61)年3月1日、転属配置先、一ノ関
転属日、1991(平成3)年11月5日、転属配置先、小牛田
機関換装・車両更新を施工され
エンジンはコマツ製DMF11HZへ換装
廃車日、2000(平成12)年1月15日、小牛田
キハ23 501〜521
寒地向けのに製造されたグループで、
エンジンはコマツ製DMF11HZへ換装
車両更新工事施工車
トイレ設置
定員116名。
キハ52形
勾配区間用の一般形気動車で、キハ20形の2基エンジン搭載形である。
国鉄の2基エンジン気動車としては最初の両運転台車であり、
急勾配のローカル線用車両として本州・四国・九州各地で重用された。
キハ20形に準じた両運転台、片開き2ドア、2段窓であるが、
エンジン、変速機、放熱器をそれぞれ2基搭載する必要から、
床下スペースの確保目的で、全長が1.3m長い車両限界一杯の21.3mとなり、
それに伴い、ドア間の2段窓の数もキハ20形の5個から6個に増えている。
それでもなお床下は手狭なため、
水タンクは床上(通路を挟んだ便所の反対側)に置かれた。
後期形(100番台)1962年から1966年に製造された。
キハ58形とキハ80形の好評を受け、騒音と振動の低減はもちろんのこと、
量産効果の向上(コスト低減)の見地からも2基エンジン車については、
すべて横形エンジンに統一されることになった。
水平シリンダー形のDMH17Hを搭載し、
床面点検蓋・車体中央壁面の排気管が廃止された。
それにともない、排気管が車体の中央部から車端寄りに移ったため、
0番台では排気管によって3個-3個に分かれていた客用扉間の窓が、
6個等間隔に並ぶようになった。
さらに、勾配線区での使用実績に基づきエンジンブレーキ機能が追加されている。
末期にはキハ22形同様、外ハメ式の尾灯や、ハニカム構造の客扉が採用された。
室内照明は蛍光灯で、キハ20系の中ではキハ22形と並んで例外的な温水暖房車。
スタイルと旅客設備を除いたメカニズム面では、
急行形気動車のキハ58形との共通点が多い。
100番台は静粛性に対する期待から、寝台気動車の試験に供され、
注目を集めたが、音振(おとしん)や変速ショックの点で採用には至らなかった。
その後も日本では寝台気動車が実現した例はなかったが、
2017年から運行開始する「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」が、
初の寝台気動車として登場することとなった。
2010年3月12日には、大糸線で運用されていたJR西日本が保有する
キハ20系気動車最後の3両の運用が終了し、
同年3月13日のダイヤ改正でキハ120形に置き換えられた。
これによってJR線上でのキハ20系列の定期運用が終了した。
2011年8月3日に最後まで在籍していた新津運輸区のキハ52形7両が、
廃車されたことでJRでは全車廃車、同時にキハ20系の系列消滅となった。
キハ20形は一般型気動車であり、
キハ22形を除いて定期の急行運用に就くことはまずなかったが、
本形式については、2基エンジンで強力なこと、単行運転が可能なことから、
只見線および会津線の急行「いなわしろ」として、
1982年6月23日の東北新幹線開業による列車自体の廃止時まで、長らく使用された。
この列車は気動車単行の急行で、なおかつ遜色急行であるとともに、
急行「あがの」「いわき」と併結する多層建て列車として異色の存在であった。
なお、この列車に専ら用いられたキハ52 128は首都圏色化されず、
同列車廃止後小牛田から、盛岡、米子と転属した後も、
1999年の廃車時まで国鉄一般色で残った。
キハ52 101〜156
2次車として製造されたグループで、
勾配区間用の両運転台の一般形気動車、
キハ20形の2基エンジン搭載形で強力型として登場しました。
国鉄の2基エンジン気動車としては最初の両運転台車であり、
急勾配のローカル線用車両として本州・四国・九州各地で重用された。
一部が新型エンジンへの換装と内装の更新改造を施され、
2000年代後半まで使用された。
画像番号IMG 8707.JPGの画像は、
キハ52−127(国鉄色)
新製落成日、1965(昭和40)年10月20日、新製配置、小牛田、製造、新潟鉄工所
転属日、1982(昭和57)年11月15日、転属配置先、郡山
転属日、1984(昭和59)年4月7日、転属配置先、盛岡
転属日、1986(昭和61)年11月1日、転属配置先、一ノ関
転属日、1991(平成3)年11月22日、転属配置先、長野
転属日、1998(平成10)年3月13日、転属配置先、新津
廃車日、2011(平成23)年8月3日、新津
キハ52 101〜156
1962年からの増備車で、両運転台車でキハ58系と同等のエンジンが装備された。
車両更新工事施工車
エンジンはカミンズ製DMF14HZへ換装
トイレ設置
定員88名。