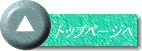画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。

画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。
 FH107 |
FH117 |
 FH140 |
 IMG_8709 |
 IMG_8710 |
 IMGP1031 |
 IMG_7312 |
IMG_7310 |
 IMGP1029 |
 IMGP1030 |
 IMGP1078 |
 IMGP1133 |
 IMGP1232 |
 IMG_3341 |
キハ58系気動車
キハ58系気動車は、日本国有鉄道(国鉄)が1961年に開発した
急行形気動車(ディーゼル動車)である。
1969年まで大量に増備され、
1960年代から1980年代にかけて幹線・ローカル線を問わず、
日本全国で急行列車を中心に投入された。
1960年代に、蒸気機関車牽引列車を置き換え、
スピードアップと居住性改善を図る無煙化を目的に大量製造された。
幹線・ローカル線の別なく、日本全国に気動車急行列車網を完成させた車両群である。
1970年代以降は、幹線電化の著しい進展に伴い、
急行列車の電車化さらには特急列車への格上げが進められたことから、
気動車急行列車は徐々にその運用域を狭め、1980年代以降は、
ローカル線の普通列車用として多くが転用されている。
1987年の国鉄分割民営化時には総数の約2/3がJR各社に引き継がれ、
その多くは近郊形化改造やワンマン化改造を施した上で、
非電化ローカル線の普通列車に運用されたり、
座席のグレードアップを施して地方幹線の快速列車などに運用される一方、
一部の車両は「ジョイフルトレイン」と呼ばれる団体専用列車用に改造された。
しかし老朽化や後継形式の増備、及び赤字ローカル路線の廃止に伴って、
淘汰・廃車が進行し、最終増備車の製造から40年以上が経過した2011年時点では、
一般車は運用を終了し少数の波動用車両と保留車が残っているのみである。
一般に「広義のキハ58系」として扱われるのは、
北海道用の耐寒耐雪型「キハ56系」・信越本線用の
空気バネ台車装備車「キハ57系」・本州以南向けの
標準型である狭義の「キハ58系」の3系列である。
製造メーカーは、新潟鐵工所・富士重工業・日本車輌製造
帝國車輛工業・東急車輛製造の5社。
これらの広義のキハ58系全体の製造両数1,823両は、
日本のディーゼル動車としては史上最多で一時は、
国鉄在籍気動車の3割を占めたこともあった。
キハ58 1〜312
1961〜63(昭和36〜38)年に新製された。
駆動エンジン2基の普通車用車両。
先に登場した北海道向けキハ56形に準じているが、暖地向けのため、
客室側窓の高さが北海道向けより広くなっている。
水タンクが屋根上に取付けられている。
後に順次冷房化が実施された。
冷房化改造工事は全車に行き渡らず、非冷房の未改造施工車も存在した。
画像番号IMGP1078.JPGの画像は、
キハ58−202
新製落成日、1962(昭和37)年10月6日、新製配置、新潟、製造、日本車輌
転属日、1971(昭和46)年4月30日、転属配置先、水戸
転属日、1990(平成2)年3月10日、転属配置先、常陸大子
1991年4月にエンジンがコマツ製DMF11HZへ換装
転属日、1992(平成4)年3月11日、転属配置先、小牛田
廃車日、1997(平成9)年2月18日、小牛田
キハ58 1〜312
1961から1963年までに製造されたグループ。
水タンクは屋根上に取付けられている。
小牛田車 コマツ製DMF11HZへ換装
新津車 カミンズ製DMF14HZへ換装
登場時原形車 定員84名
車両更新工事施工車セミクロスシート改造
車端部座席のロングシート化 定員139名
回転式リクライニングシート車 定員60名。
アコモデーション改善車
「よねしろ」「月山」などの優等列車運用充当車両に実施。
通常の更新工事とは別に座席をリクライニングシートへ交換したほか、
側面の行先表示に電動式方向幕を搭載するなどの施工を行った。
画像番号IMGP1030.JPGの画像は、
キハ58−308(よねしろ・月山色)
新製落成日、1963(昭和38)年2月11日、新製配置、長野、製造、日本車輌
転属日、1966(昭和41)年6月6日、転属配置先、新潟
転属日、1966(昭和41)年9月27日、転属配置先、長野
転属日、1969(昭和44)年度、転属配置先、美濃太田
転属日、1971(昭和46)年度、転属配置先、長野
転属日、1973(昭和48)年7月12日、転属配置先、米子
転属日、1976(昭和51)年3月1日、転属配置先、岡山
転属日、1985(昭和60)年3月27日、転属配置先、中込
転属日、1991(平成3)年7月3日、転属配置先、新庄
転属日、1999(平成11)年3月15日、転属配置先、小牛田
機関更新・車体更新・アコモ改造等徹底的な体質改善工事が施工
コマツ製DMF11HZへ換装
廃車日、2000(平成12)年5月1日、小牛田
長大編成対応車
キハ58、401 - 799・1000 - 1052
キハ28形、301 - 494
国鉄の気動車は、KE53形ジャンパ連結器2基で直流24V電源による制御と、
空気圧作動の自動ブレーキを共通装備としていた。
このため、長大編成を組むと電圧および空気圧の低下で、
先頭運転台から後方車両までの制御の応答性・確実性に問題が生じた。
長大編成を頻繁に組む本系列も当初はその例に漏れず、
最大11両17エンジンまでに編成を制限されるため問題は深刻であった。
そこで1963年度以降に製造されたグループからは、以下に示す仕様変更を行った。
各車の自動ブレーキA動作弁直近に応答性能が優れる電磁給排弁を付加。
運転台のM23系ブレーキ制御弁も電磁給排弁への指令を可能としたME23B弁とし、
運転台付車両はDAE1、運転台のないキロはDAE2電磁自動空気ブレーキに仕様変更。
DAEブレーキ化のために回路制御用KE67形ジャンパ連結器による引き通しを増設。
また従来からの制御回路にも中継装置を設置し、
引き通し線の電圧降下・制御電流の容量制限
ブレーキ作動時間の遅延に対する改良を実施。
その結果、最大15両23エンジンまで制御可能となり新規の番号区分が行われた。
後に順次冷房化が実施された。
冷房化改造工事は全車に行き渡らず、非冷房の未改造施工車も存在した。
キハ28形、定員84名、キハ58形、定員84名(オリジナル車)
キハ58 401〜799、1000〜1052
1963〜67(昭和38〜42)年に新製された長大編成対応車で、
キハ28 301〜と同様に引通し線の電圧降下、
制御電流の容量制限、ブレーキ作動時間の遅延に対する改善がなされ、
車体は客用扉下部に小窓が新設されるなどの変更点がある。
画像番号IMG 7312.JPGの画像は、
キハ58−414(国鉄修学旅行色)
新製落成日、1963(昭和38)年6月6日、新製配置、松本、製造、新潟鉄工所
転属日、1969(昭和44)年度、転属配置先、長野
1969(昭和44)年度、転属配置先、中込(小海)
転属日、1970(昭和45)年度、転属配置先、名古屋
転属日、1978(昭和53)年10月2日、転属配置先、美濃太田
転属日、1984(昭和59)年2月9日、転属配置先、長野
転属日、1991(平成3)年10月4日、転属配置先、新庄
転属日、1997(平成9)年3月12日、転属配置先、小牛田
機関更新・車体更新・アコモ改造等徹底的な体質改善工事施工
コマツ製DMF11HZへ交換済み
廃車日、2009(平成21)年1月14日、小牛田
画像番号FH107.JPGの画像は、
キハ58−578(仙台色)
新製落成日、1964(昭和39)年12月25日、新製配置 水戸、製造、帝國車輛
新製落成日、1963(昭和38)年6月6日、新製配置、松本、製造、新潟鉄工所
転属日、1969(昭和44)年度、転属配置先、長野
1969(昭和44)年度、転属配置先、中込(小海)
転属日、1970(昭和45)年度、転属配置先、名古屋
転属日、1978(昭和53)年10月2日、転属配置先、美濃太田
転属日、1984(昭和59)年2月9日、転属配置先、長野
転属日、1991(平成3)年10月4日、転属配置先、新庄
転属日、1997(平成9)年3月12日、転属配置先、小牛田
機関更新・車体更新・アコモ改造等徹底的な体質改善工事が施工
コマツ製DMF11HZへ交換済み
廃車日、2009(平成21)年1月14日、小牛田
画像番号IMGP1133.JPGの画像は、
キハ58−636 旧新潟色(青ベースの塗装)
新製落成日、1965(昭和40)年6月1日、新製配置、新潟、製造、新潟鉄工所
エンジンがカミンズ製DMF14HZへ交換済
廃車日、1998(平成10)年9月30日、新津
画像番号IMG 3341.JPGの画像は、
キハ58−677 旧新潟色(青ベースの塗装)
新製落成日、1965(昭和40)年12月10日、新製配置、米子、製造、富士重工
転属日、1972(昭和47)年度、転属配置先、鳥取
転属日、1985(昭和60)年5月23日、転属配置先、中込(小海)
転属日、1991(平成3)年11月30日、転属配置先、新津
廃車日、2009(平成21)年6月30日、新津
画像番号IMGP1029.JPGの画像は、
キハ58−1010 旧新潟色(青ベースの塗装)
新製落成日、1966(昭和41)年10月10日、新製配置、新潟、製造、新潟鉄工所
1969年度中に冷房化
1990(平成2)年12月度にカミンズ製DMF14HZ機関へ換装
転属日、1993(平成5)年12月1日、転属配置先、長野
転属日、1997(平成9)年8月27日、転属配置先、新庄
転属日、1999(平成11)年3月17日、転属配置先、小牛田
廃車日、2000(平成12)年5月1日、小牛田
画像番号IMG 8709.JPGの画像は、
キハ58−1022(国鉄急行色)
新製落成日、1967(昭和42)年3月16日、新製配置、長野、製造、富士重工
転属日、1991(平成3)年4月25日、転属配置先、新潟
冷房改造化は不明
車両更新工事施工
車両更新の際にカミンズ製DMF14HZへ換装
廃車日、2010(平成22)年1月30日、新津
キハ58 401〜799、1000〜1052
長大編成対応車
1963年度以降に製造されたグループ
最大15両23エンジンまで制御可能、
登場時原形車 定員84名
小牛田車 コマツ製DMF11HZへ換装
新津車 カミンズ製DMF14HZへ換装
車両更新工事施工車セミクロスシート改造
車端部座席のロングシート化 定員139名
回転式リクライニングシート車 定員60名。
末期増備車グループ
1968年から1969年までに製造されたグループで、
走行性能に変化はないが車体のマイナーチェンジなどの以下の改良が行われた。
冷房化を考慮し屋根高さを低下。
運転台前面窓をパノラミックウインドウに変更。
運転台下部に排障器(スカート)を採用。
この結果、前面の印象は1966年から増備されていた
近郊形気動車のキハ45系に追随する形になったため、
従来形に比べて大きく変わった。
しかし、DMH17系エンジンを核とした構成の陳腐化や
電化の進展による電車特急列車の増発で
気動車急行列車の減少が予測されたため、
同時期の他の気動車と同様に製造両数は少なく抑えられた。
また、帝國車輛工業と東急車輛製造は製造を担当していない。
キハ58 1501〜1534
1968(昭和43)年に新製された寒地向けのモデルチェンジ車で、
1101〜と同様に冷房準備車として登場した。
しかし、大半の車両が非冷房のままであった。
画像番号FH140.JPGの画像は、
キハ58−1527(仙台色)
新製落成日、1968(昭和43)年4月9日、新製配置、釧路、製造、新潟鉄工所
転属日、1968(昭和43)年9月14日、転属配置先、秋田
1973〜1974年頃に冷房改造化
転属日、1985(昭和60)年3月14日、転属配置先、盛岡
転属日、1988(昭和63)年3月16日、転属配置先、山形
1990年11月度にコマツ製DMF11HZへ換装
車両更新工事施工
転属日、1991(平成3)年3月16日、転属配置先、小牛田
廃車日、2000(平成12)年5月1日、小牛田
1501〜1534
寒地向けマイナーチェンジ車。
パノラミックウインド採用、冷房工事準備車。
コマツ製DMF11HZ機関へ換装
登場時原形車 定員84名
車両更新工事施工車セミクロスシート改造
車端部座席のロングシート化 定員139名
キハ28形2000番台(4VK冷房用発電装置搭載車)
上述の状況から、新たに自車を含めて3両分の冷房電源の供給が可能となる
4VK冷房用発電装置が開発された。
機関 - ダイハツ工業製V型8気筒4VK形ディーゼルエンジン(90PS)
発電機 - DM83形発電機
発電能力 - 三相交流440V・70KVA
本装置は、走行用エンジン2基搭載のキハ58と、
キロ58には搭載不可能なために一部のキハ28・キロ28に搭載され、
搭載車は原番号+2000の車番に区分された。
ただし、以下の例外がある。
キハ28 1〜203
北海道以外の急行用車両として製造された車両で、
1968年にはモデルチェンジが行われ、
前面窓がパノラミックウインドウになり、
当初から冷房を念頭においた屋根上配置となりました。
本州用キハの1機関搭載車で、1961(昭和36)年から新製された。
給電が可能な4VK発電装置を搭載する改造が行われたものについては、
原番号+2000に改番された。
アコモデーション改善車
「よねしろ」「月山」などの優等列車運用充当車両に実施。
通常の更新工事とは別に座席をリクライニングシートへ交換したほか、
側面の行先表示に電動式方向幕を搭載するなどの施工を行った。
画像番号IMG 7310.JPGの画像は、
キハ28−2174(国鉄修学旅行色)
製造時形式車番、キハ28-174、
新製落成日、1963(昭和38)年2月18日、新製配置、秋田、製造、東急車輌
転属日、1967(昭和42)年度、転属配置先、盛岡
冷房化+4DQ(4VK)電源装置搭載改造
改造後、キハ28-2174
改造施行日、1972(昭和47)年7月15日、改造工、盛岡工場
転属日、1972(昭和47)年度、転属配置先、青森
転属日、1973(昭和48)年10月1日、転属配置先、秋田
転属日、1982(昭和57)年11月20日、転属配置先、山形
転属日、1991(平成3)年3月16日、転属配置先、新庄
転属日、1993(平成5)年12月1日、転属配置先、小牛田
廃車日、2009(平成21)年1月14日、小牛田
キハ28 1〜203
駆動エンジン1基の普通車用車両。
4VK発電装置搭載改造車は、原番号+2000に改番。
小牛田車 コマツ製DMF11HZへ換装
新津車 カミンズ製DMF14HZへ換装
機関 ダイハツ製V型8気筒4VK形ディーゼルエンジン(連続定格90 PS)
発電機 DM83形発電機(2極)
発電能力 三相交流400 V・50 Hz・70 kVA
登場時原形車 定員84名
車両更新工事施工車セミクロスシート改造
車端部座席のロングシート化 定員139名
回転式リクライニングシート車 定員60名。
キハ28 301〜494
1963〜67(昭和38〜42)年に新製された長大編成対応車で、
駆動エンジン1基の普通車用車両。
引通し線の電圧降下、制御電流の容量制限、
ブレーキ作動時間の遅延に対する改善がなされている。
そのほか客用扉下部に小窓が取付けられ、
出入台に通風器が増設されている。
4VK発電装置搭載改造車は、原番号+2000に改番。
画像番号IMG 8710.JPGの画像は、
キハ28−2371(国鉄急行色)
製造時形式車番、キハ28-371、
新製落成日、1964(昭和39)年12月14日、新製配置、水戸、製造、新潟鉄工所
冷房化+4DQ(4VK)電源装置搭載改造
改造後、キハ28-2371
改造施行日、1972(昭和47)年7月27日、改造工、土崎工場
転属日、1986(昭和61)年11月、転属配置先、真岡
転属日、1988(昭和63)年度、転属配置先、水戸
転属日、1990(平成2)年3月10日、転属配置先、常陸大子
転属日、1991(平成3)年4月2日、転属配置先、新潟
1991年12月度に機関換装・車両更新を施工
エンジンはカミンズ製DMF14HZへ換装
廃車日、2010(平成22)年1月30日、新津
画像番号IMGP1232.JPGの画像は、
キハ28−2380(仙台色)
製造時形式車番、キハ28-380、
新製落成日、1964(昭和39)年12月3日、新製配置、水戸、製造、富士重工
冷房化+4DQ(4VK)電源装置搭載改造
改造後、キハ28-2380
改造施行日、1972(昭和47)年4月20日、改造工、大宮工場
転属日、1986(昭和61)年度、転属配置先、真岡
転属日、1988(昭和63)年3月16日、転属配置先、山形
転属日、1991(平成3)年3月16日、転属配置先、新庄
転属日、1993(平成5)年12月1日、転属配置先、小牛田
廃車日、2009(平成21)年1月14日、小牛田
キハ28 301〜494
最大15両23エンジンまでの制御可能な長大編成対応車。
駆動エンジン1基
4VK発電装置搭載改造車は、原番号+2000に改番。
小牛田車 コマツ製DMF11HZへ換装
新津車 カミンズ製DMF14HZへ換装
機関 ダイハツ製V型8気筒4VK形ディーゼルエンジン(連続定格90 PS)
発電機 DM83形発電機(2極)
発電能力 三相交流400 V・50 Hz・70 kVA
登場時原形車 定員84名
車両更新工事施工車セミクロスシート改造
車端部座席のロングシート化 定員139名
回転式リクライニングシート車 定員60名。
寒地向けキハ28 1505 - 1510
中央本線用のキロ58が2エンジン車で、
4DQ発電装置を搭載することができないことから、
新造時から4VK発電装置が搭載された。
1971年に自車も冷房化されたため2505 - 2510に改番。
キハ28 501〜504・1505〜1510
キハ28 2506
寒地向けモデルチェンジ車で、1968(昭和43)年に新製された。
前面窓がパノラミックウィンドウとなリ、スカートが取付けられた。
さらに冷房準備工事がなされている。
1505〜1510はキロ58形への電源供給のため4Vk発電装置付きで、
1971(昭和46)年度に2505〜2510に改番された。
画像番号IMGP1031.JPGの画像は、
キハ28−2506 旧新潟色(青ベースの塗装)
製造時形式車番、キハ28-1506、
新製落成日、1968(昭和43)年3月30日、新製配置、松本、製造、富士重工
改番後、キハ28-2506 1971(昭和46)年
転属日、1982(昭和57)年11月21日、転属配置先、新潟
転属日、1993(平成5)年12月1日、転属配置先、小牛田
廃車日、2007(平成21)年4月12日、小牛田
キハ28 501〜504・1505〜1510
キハ28 2506
カミンズ製DMF14HZへ換装
機関 ダイハツ製V型8気筒4VK形ディーゼルエンジン(連続定格90 PS)
発電機 DM83形発電機(2極)
発電能力 三相交流400 V・50 Hz・70 kVA
登場時原形車 定員84名
キハ53形(両運転台化改造)
国鉄末期の1986年からJR化後の1988年にかけて、
5両のキハ58形が両運転台化改造された。
改造は、車体の後位を切断して廃車の運転台を接合する方式で施行され、
外観は富士急行から有田鉄道に譲渡されたキハ58003に似ているが、
窓配置に違いがある。
形式は、すでにキハ45系に存在していたキハ53形とされ、
既存車との重複を避けるため新区分番台が起こされた。
200番台
1987年に東北地区の増結用として土崎工場(現・秋田総合車両センター)で、
キハ58形非冷房車2両を改造、その際客室内にトイレを設置した。
小牛田運輸区に配置されて陸羽東線などで運用された後、
会津若松運輸区に転出。
只見線で運用され2000年に廃車となった。
キハ53 201・202
キハ58形を両運転台化改造しキハ53形に編入したグループで、
1987(昭和62)年に土崎工で2両改造された。
キハ56形またはキハ27形の先頭部(廃車発生品)を接合して、
さらに便所、水タンク(室内取り付け)を新設している。
1991年度に機関がコマツ製DMF11HZへ換装
キハ53−201(仙台色)
新製落成日、1966(昭和41)年5月10日、新製配置、釧路、製造、富士重工
製造時形式車番、キハ58-741、
転属日、1966(昭和41)年9月15日、転属配置先、小牛田
転属日、1985(昭和60)年3月14日、転属配置先、郡山
改造後、キハ53-201
改造施行日、1987(昭和62)年3月、改造工、郡山工場
改造後転属配置先、小牛田
転属日、1994(平成6)年12月17日、転属配置先、会津若松
廃車日、2000(平成12)年5月1日、会津若松
キハ53 201・202
キハ58形を両運転台化改造しキハ53形に編入したグループ、
1987(昭和62)年に土崎工で2両改造された。
エンジンはコマツ製DMF11HZへ換装
定員74名。