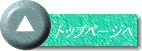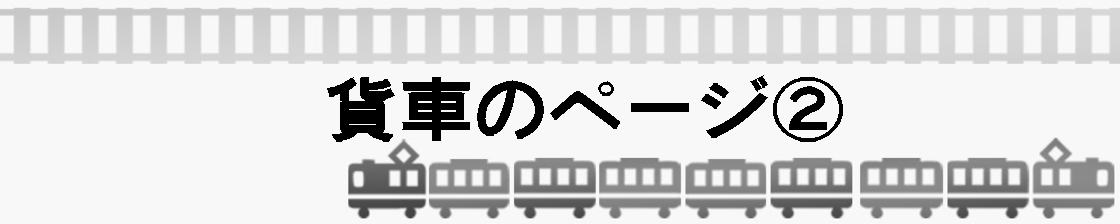
画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。
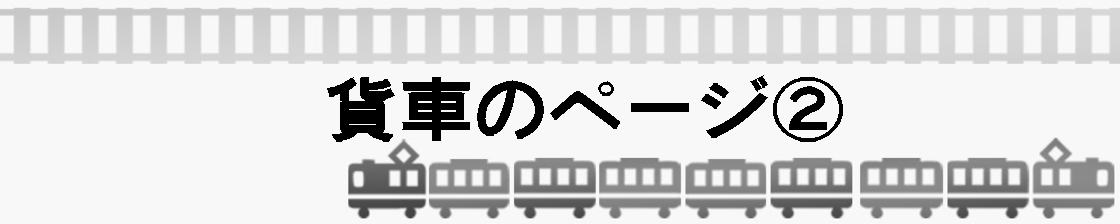
画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。
タキ38000形
1977年(昭和52年)から製作された、
ガソリン専用の 36 t 積 貨車(タンク車)である。
私有貨車として製作され、日本国有鉄道(国鉄)に車籍編入された。
1987年の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道(JR貨物)に車籍を承継している。
日本国内外で多発した危険品輸送貨車の重大事故を契機とし、
安全対策の強化方針を受けて設計された。
「保安対策車」と総称される貨車群の一形式である。
1977年 - 1979年に140両 (38000 - 38139) が日本車輌製造・富士重工業で製作された。
所有者は日本石油輸送である。
画像番号IMG 1710.JPGの画像は、
タキ38000形
タキ38128
日本石油輸送所有車
新製落成年、1979(昭和54)年 製造、富士重工
仙台北港駅常備 廃車
タキ43000形
43t・44t積のガソリン専用タンク車である。
1967年(昭和42年) - 1993年(平成5年)に819両が製作された。
1967年(昭和42年)から製作されたガソリン専用の貨車(タンク車)である。
日本オイルターミナルまたは日本石油輸送が所有する私有貨車で、
当初は日本国有鉄道(国鉄)に、
1987年の国鉄分割民営化以降は日本貨物鉄道(JR貨物)に車籍編入されている。
鉄道貨物においても、
1965年(昭和40年)頃から「物資別適合輸送」の
運用形態が増加してきた。
これは石灰石・セメント・石油製品などのバラ積み輸送
(バルク輸送)品目について、
新設した各品目専用の物資別ターミナルに輸送拠点を集約し
専用の貨車で組成された直行列車を拠点間に、
運行して一括大量輸送を行う輸送体系である。
ガソリンなどの石油製品においては、
国鉄と各石油会社との共同出資で、
日本オイルターミナル株式会社が1966年(昭和41年)に設立され、
倉賀野駅や西上田駅を皮切りに、各地に拠点が新設された。
この各拠点への専用列車に充当する目的で開発された新形式が、
タキ43000形(ガソリン専用)・タキ44000形(石油類専用)である。
輸送効率向上のためにフレームレス構造や
異径胴のタンク体を採用して容積を極限まで拡大し、
43tの荷重を実現した。
これは当時の2軸ボギータンク車では最大である。
外部塗色は識別のため、
ガソリン専用タンク車としては異例の青15号(濃青色)とされた。
1974年(昭和49年)のタンク車構造基準改訂を受け製作が中断されるが、
設計変更のうえ1982年(昭和57年)に製作を再開した。
以後、種々の設計変更を経ながら1993年(平成5年)までに、
2形式合計990両が製作され、
主に名古屋以東の地域で後継のタキ1000形とともに、
石油専用列車に使用されている。
基本番台 (43000 - 43036)
1967年(昭和42年)に37両が三菱重工業及び日本車輌製造にて製作された。
平軸受・鋳鉄制輪子付のTR210形台車を装備し、
車両番号・専用種別などの標記は側面中央から片側に寄せて記される。
転がり性能に難のあるTR210形台車は、
後に100番台以降と同様のコロ軸受台車TR214系列に交換されている。
画像番号DSC 3550.JPGの画像は、
タキ43000形
タキ43000(トップナンバー)
日本オイルターミナル所有車
新製落成年、1967(昭和42)年、製造、三菱重工
宇都宮貨物ターミナル駅常備
画像番号DSC 2300.JPGの画像は、
タキ43000形
タキ43005
日本オイルターミナル所有車
新製落成年、1967(昭和42)年、製造、三菱重工
郡山駅常備
43100番台 (43100 - 43485)
1968年(昭和43年)から1974年(昭和49年)にかけて、
386両が日本車輌製造及び三菱重工業にて製作された。
台車の転がり性能を改善するため、
軸受をコロ軸受に改良したTR214A形台車に変更した区分である。
ブレーキ制輪子もレジン製に変更された。
タンク体など車体各部寸法は基本番台と同一であるが、
車両番号・専用種別などの標記が側面中央に移されている。
画像番号DSC 2335.JPGの画像は、
タキ43000形
タキ43135
日本オイルターミナル所有車
新製落成年、1971(昭和43)年 製造、日本車輌
郡山駅常備
画像番号DSC 2332.JPGの画像は、
タキ43000形
タキ43205 黒色
日本石油輸送株式会社所有車
新製落成年、1968(昭和46)年 製造、日本車輌
根岸駅常備
画像番号CIMG0184.JPGの画像は、
タキ43000形
タキ43354
日本オイルターミナル所有車
新製落成年、1971(昭和46)年 製造、三菱重工
南松本駅常備
準保安対策車 (43486 - 43499, 43519 - 43599)
1974年(昭和49年)に95両が日本車輌製造にて製作された。
成田空港燃料輸送への充当を考慮して製作された、
本系列初の日本石油輸送所有車で、外部塗色は黒である。
同年に施行されたタンク車の安全基準改定に伴い、
従来設計の範囲で安全確保を考慮した仕様を採り入れた。
脱線転覆時の安全確保のため、
車体下部にある取出口の開閉弁をタンク上部で操作する方式に変更した。
また、タンク体の衝突安全空間を確保するため、
手ブレーキのない側の車端部デッキを200mm延長し、
前後のデッキを同じ長さとした。
本区分は単年度に一括製造され、
車両番号は100番台の続番を付番した後に500番台の続番を付番した。
本来の500番台(北海道向け)とは仕様が異なる。
画像番号DSC 2302.JPGの画像は、
タキ43000形
タキ43568
日本オイルターミナル所有車
新製落成年、、1974(昭和49)年、製造、日本車輌
宇都宮貨物ターミナル駅常備
保安対策車 (43600 - 43644)
1982年(昭和57年)に45両が日本車輌製造及び富士重工業にて製作された。
本形式の製作再開にあたり、
安全性能と積載効率を両立した車両として設計された区分で、
車両前後の安全空間を確保するためタンク形状を変更した。
タンク体直径は50mm拡大し、
球面半径を大きく取った扁平形状の鏡板とすることで、
タンク全長を252mm短くしている。
タンク上部の踏板は、転覆時のタンク倒立を防ぐため強度を増した形状に改良された。
画像番号IMG 2842.JPGの画像は、
タキ43000形
タキ43638
日本オイルターミナル所有車
新製落成年、1982(昭和57)年 製造、富士重工
浜五井駅常備
243000番台
243000番台 (243646 - 243885)
243732 淡緑+灰色塗装の日本石油輸送所有車
1989年(平成元年)から1993年(平成5年)にかけて240両が製作された。
タンク寸法の変更、ハシゴ・踏板のアルミ合金化などで軽量化と容積の拡大を図り、
荷重を1t増の44tに拡大した。全車とも日本石油輸送の所有車で、
外部塗色は243665までの車両は黒色、
以降の車両はエメラルドグリーン+灰色の2色塗装である。
台車は全車とも灰色である。
画像番号DSC 7572.JPGの画像は、
タキ243000
243000番台
243668
日本石油輸送株式会社所有車
新製落成年、1990(平成2)年 製造、日本車輌
浜五井駅常備
画像番号CIMG0174.JPGの画像は、
タキ243000
243000番台
243716
日本オイルターミナル所有車
新製落成年、1991(平成3)年 製造、日本車輌
宇都宮貨物ターミナル駅常備
画像番号IMG 1355.JPGは、
タキ243000
243000番台
243732
日本石油輸送株式会社所有車
新製落成年、1991(平成3)年 製造、日本車輌
浜五井駅常備
画像番号CIMG0180.JPGの画像は、
タキ243000
243000番台
243885
日本オイルターミナル所有車
新製落成年、1993(平成5)年 製造、日本車輌
宇都宮貨物ターミナル駅常備
タキ44000形
43t積の石油類(除ガソリン)専用タンク車である。
1967年(昭和42年)から1982年(昭和57年)にかけて、
170両が日本車輌製造にて製作された。
積荷の比重が大きいため、タキ43000形と比べ全長は約2m短く、
車端部のタンク鏡板には点検用ハッチと、
荷役のための加熱管を装備する。
基本番台 (44000 - 44023)
1967年(昭和42年)に24両が製作された。
平軸受・鋳鉄制輪子付のTR210形台車を装備する。
画像番号DSC 2320.JPGの画像は、
タキ44000形
タキ44004
日本オイルターミナル所有車
新製落成年、1967(昭和42)年 製造、日本車輌
郡山駅常備
100番台(タキ44100 - タキ44223)
1968年(昭和43年)から1974年(昭和49年)にかけて124両が製作された。
台車をコロ軸受・レジン制輪子のTR214A形に変更した。
画像番号DSC 4615.JPGの画像は、
タキ44000形
タキ44124
日本オイルターミナル所有車
新製落成年、1968(昭和43)年 製造、日本車輌
郡山駅常備
JRFタキ1000形
1993年(平成5年)から製作されているガソリン専用の貨車(タンク車)である。
全車が日本石油輸送または日本オイルターミナルが所有する私有貨車で、
日本貨物鉄道(JR貨物)に車籍編入されている。
1984年(昭和59年)2月ダイヤ改正で貨物列車の輸送体系が、
拠点間直行方式に改められて以降、
貨物列車の運用は行先別・荷種別に集約する「専用列車」への転換が進行してきた。
コンテナ列車は従来よりコキ50000系やコキ100系などによる
高速運転が主体となっていたが、
タンク車など一般の車扱貨物に用いられる貨車は依然として、
最高速度は75km/hにとどまり、
到達時分の短縮やダイヤを組成する際の懸案事項となっていた。
これを受け、専用列車のうち特に占める割合の
大きい石油類専用貨物列車の高速化を図る目的で製作されたのが、
本形式である。
タンク車初の高速貨車として開発された本形式は、
輸送効率と高速走行とを両立させた形式として、
2011年現在も製作が続いている。
タキ1000-1
試作車
先行試作車の1両。台車はFT21X形式を履く、
タンク受台に標差しがあるなど量産車に近いスタイルです。
画像番号CIMG0962.JPGの画像は、
タキ1000-1
日本オイルターミナル所有車
倉賀野駅常備、
新製落成年、1993(平成5)年、製造、日本車輌
量産車
402までは台車はFT21で、
台車側面に補強板を取り付けた。
写真のようにENEOSの油槽所と製油所との間で使用される一部車両には、
「ENEOS」と「エコレールマーク」のロゴが 掲出されている。
画像番号DSC 4712.JPGの画像は、
タキ1000-89
日本石油輸送所有車 ENEOSロゴ
淡緑/灰色塗装
仙台北港駅常備
新製落成年、1994(平成6)年、製造、川崎重工
画像番号DSC 1728.JPGの画像は、
タキ1000-94
日本オイルターミナル所有車
倉賀野駅常備、
新製落成年、1994(平成6)年、製造、日本車輌
画像番号CIMG0190.JPGの画像は、
タキ1000-100
日本オイルターミナル所有車
倉賀野駅常備、
新製落成年、1994(平成6)年、製造、川崎重工
画像番号DSC 3856.JPGの画像は、
タキ1000-240
日本石油輸送所有車 ENEOSロゴ
淡緑/灰色塗装
仙台北港駅常備
新製落成年、1996(平成8)年、製造、日本車輌
画像番号IMG 2838.JPGの画像は、
タキ1000-333
日本オイルターミナル所有車
日本オイルターミナル㈱所有の登場時の塗装。
青15号に帯を巻き、さらに銀色の細い帯のある車両
根岸駅常備
新製落成年、1997(平成9)年、製造、日本車輌
403~
403以降は台車側面の補強板を廃止した改良型のFT21A台車となった。
写真は日本オイルターミナル所属車で、車体塗色は青15号。
画像番号DSC 2693.JPGの画像は、
タキ1000-632
日本石油輸送所有車 ロゴ無し
根岸駅常備
淡緑/灰色塗装
新製落成年、1999(平成15)年、製造、日本車輌
画像番号IMG 2991.JPGの画像は、
タキ1000-673
日本オイルターミナル所有車
宇都宮タ常備、廃車
新製落成日、2005(平成17)年10月25日、製造、日本車輌
※東日本大震災で被災のため廃車
津波に流されるなどした。
画像番号DSC 1732.JPGの画像は、
タキ1000-674
日本オイルターミナル所有車
宇都宮タ常備、
新製落成日、2005(平成17)年10月25日、製造、日本車輌
画像番号IMG 1222.JPGの画像は、
タキ1000-745
日本オイルターミナル所有車
タキ1000形式で組成した
特急貨物「スーパーオイルエクスプレス」の拡大を図るためのPRと
日本オイルターミナル㈱創設40周年を記念して施された塗装。
「矢羽」と呼ばれる8つの楕円は所有する製油所を表したものです。
川崎貨物駅常備
新製落成日、2007(平成19)年3月16日、製造、川崎重工
画像番号DSC 2396.JPGの画像は、
タキ1000-748
日本オイルターミナル所有車
川崎貨物駅常備
新製落成日、2007(平成19)年3月16日、製造、川崎重工
タキ1000-1000 タキ1000号記念塗装
令和3年(2021)に1000号記念として特別な塗装で落成して話題となった。
反対側は「環境にも優しい安全・安心の石油タンク車輸送」の記述も見られます。
画像番号CIMG1284.JPGの画像は、
タキ1000-1000 1000号記念塗装
日本石油輸送所有車
根岸駅常備
1000号記念塗色ECO
新製落成年、2021(平成15)年12月1日、製造、日本車輌