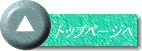画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。

画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。
DSC_2408 |
DSC_2406 |
DSC_2508 ① |
DSC_2510 ② |
DSC_2516 ③ |
DSC_2520 ④ |
DSC_4178 ① |
DSC_4174 ② |
DSC_4170 ③ |
DSC_4565 ① |
DSC_4561 ② |
DSC_4557 ③ |
びゅうコースター風っこ
びゅうコースター風っこは、
キハ48形をトロッコ気動車に改造した車両で、
仙台支社が2000年から運用を開始した。
従来、仙台支社では貨車を改造したトロッコ車両を保有していたが、
運転時の入れ換え作業や保安要員の配置など運行コストの問題を抱えていた。
本編成はこれら貨車編成の置き換え用で、
キハ48 547・1541を種車として改造した。
機関はDMF14HZに換装している。
車体側面を大きく開口させ、
外気を存分に感じることができるようにするとともに、
冬季には寒気対策のために開口部にガラス戸をはめ込んだり、
取り付けられたストーブを焚くことができる。
また開口部の下部にはガラス戸を設置し、さらに開放感を高めている。
外装は、春から夏に掛けての車窓の自然をイメージした
緑(若葉)、青(川・湖)、白(雲)、黄(光)をちりばめた爽やかなものである。
車内には、難燃木材を使用した木製座席が設けられ、
各ボックスにはテーブルが設置された。
天井は骨組みを剥き出しにし、
白熱灯を用いてレトロで暖かみのある雰囲気を創り出している。
画像番号DSC 2408.JPGの画像は、
キハ48-1541
新製落成日、1980(昭和55)年7月24日、新製配置、小牛田、製造、富士重工
転属日、1998(平成10)年12月21日、転属配置先、会津若松
転属日、1999(平成10)年12月21日、転属配置先、小牛田
改造後、キハ48-1541「びゅうコースター風っこ」
改造施行日、2000(平成12)年5月20日、改造工、新潟鐵工所
画像番号DSC 2406.JPGの画像は、
キハ48-547
新製落成日、1980(昭和55)年7月24日、小牛田、製造、富士重工
転属日、1990(平成2)年11月7日、転属配置先、郡山
転属日、1991(平成3)年3月16日、転属配置先、新潟
転属日、1991(平成3)年10月24日、転属配置先、常陸大子
転属日、1993(平成5)年12月1日、転属配置先、南秋田
転属日、1994(平成6)年2月2日、転属配置先、小牛田
改造後、キハ48-547「びゅうコースター風っこ」
改造施行日、2000(平成12)年5月20日、改造工、新潟鐵工所
1号車 キハ48-547
東京方に連結される車両で、
トイレ設置。
機関をDMF14HZに換装
定員66名。
2号車 キハ48-1541
青森方に連結される便所なし車両で、後位側の出入口が撤去され、
イベントスペースが設置されている。
機関をDMF14HZに換装
定員74名。
キハ141系気動車SL銀河鉄道用
北海道旅客鉄道(JR北海道)に所属する一般形気動車で、
キハ141形、キハ142形、キハ143形およびキサハ144形の総称である。
札幌市周辺の人口増加により、
沿線の都市化が急速に進んだ札沼線(学園都市線)の輸送力増強を目的として、
1990年(平成2年)から投入された。
電車や気動車への置き換えで余剰となっていた
50系客車(オハフ51形)を改造して製作された。
客車 (Passenger Car) 改造のディーゼル動車 (Diesel Car) であることから、
PDCとも呼ばれる。
客車の気動車化改造は、根本的な強度構造の違いから来る車体重量の違いから、
国鉄・私鉄ともにほとんど成功例がないが、
本系列は客車としては軽量な50系客車に、
新世代の軽量高回転エンジン(DMF13HS系エンジン)を組み合わせることによって、
一定以上の成果を引き出した。
4形式で合計44両が製作され、オハフ51形の2/3が本系列に改造された。
客車から気動車への改造車としては日本最多である。
他系列同様、車体にコーポレートカラーの萌黄色の帯を巻いているが、
外板の地色は白ではなく、ライトグレーとなっている。
画像番号DSC 2508.JPGの画像は、
1号車 キハ142-701
製造時形式車番、オハフ51-30
新製落成日、1981(昭和56)年3月23日、新製配置、函館、製造、新潟鉄工所
一度目改造、キハ142-201「気動車化」
改造施行日、1999(平成11)年3月31日、改造工、苗穂工場
二度目改造、キハ142-701(さそり座)「SL銀河鉄道用客車化」
改造施行日、2014(平成26)年1月23日、改造工、郡山総車セ
画像番号DSC 2510.JPGの画像は、
2号車 キサハ144-701
製造時形式車番、オハフ51-10
新製落成日、1978(昭和53)年12月18日、新製配置、岩見沢、製造、富士重工
一度目改造、キサハ144 103「気動車化」
改造施行日、1994(平成6)年3月28日、改造工、苗穂工場
二度目改造、キサハ144-701(いて座)「SL銀河鉄道用客車化」
改造施行日、2014(平成26)年1月23日、改造工、郡山総車セ
画像番号DSC 2516.JPGの画像は、
3号車 キサハ144-702
製造時形式車番、オハフ51-7
新製落成日、1978(昭和53)年12月18日、新製配置、岩見沢、製造、富士重工
一度目改造、キサハ144 101「気動車化」
改造施行日、1994(平成6)年3月24日、改造工、苗穂工場
二度目改造、キサハ144-702(わし座)「SL銀河鉄道用客車化」
改造施行日、2014(平成26)年1月23日、改造工、郡山総車セ
画像番号DSC 2520.JPGの画像は、
4号車 キハ143-701
製造時形式車番、オハフ51-27
新製落成日、1981(昭和56)年3月23日、新製配置、函館、製造、新潟鉄工所
一度目改造、キハ143-155「気動車化」
改造施行日、1995(平成7)年3月31日、改造工、苗穂工場
二度目改造、キハ143-701(はくちょう座)「SL銀河鉄道用客車化」
改造施行日、2014(平成26)年1月23日、改造工、郡山総車セ
1号車 キハ142-701
星のミュージアム・プラネタリウム室・プラネタリウムを設置
機関DMF13HZE
定員32名。
2号車 キサハ144-701
車端部に宮沢賢治ギャラリーを設置
定員64名。
3号車 キサハ144-702
車端部に宮沢賢治ギャラリーを設置
定員62名。
4号車 キハ143-701
宮沢賢治ギャラリー・SLギャラリー・売店
車販準備室・大型ソファー・車椅子対応トイレを設置
機関DMF13HZD
定員18名。
Kenji
日本の詩人、童話作家である岩手県花巻市出身の
宮沢賢治にちなんだネーミング。
キハ58系気動車を改造した3両編成。
キハ58 650・1505・キハ28 2010で構成されています。
盛岡支社が保有、盛岡車両センターに所属している。
1992年に岩手県で行なわれた三陸・海の博覧会にあわせて、
旅客輸送のための列車を運行することになり、
休車になっていた2両を盛岡支社へ転属させた上で、
新たにキハ58を1両、ほぼ同形態の外見と仕様で追加改造した。
また、東日本旅客鉄道のDMH17系エンジン淘汰の方針により、
3両ともエンジンは新型に換装されている。
この時、全車両が普通車に格下げされ、2両は原番号に戻された。
車体外部塗装は白をベースに青色系の濃淡の帯が入るものとなった。
上の写真のように緑に金帯の外観となったが、
2013年12月には青に金帯の外観となっている。
2013年現在、JR線上において唯一営業運転に就いているキハ58系の車両となっている。
1992年7月4日より「三陸マリンライナー」として運行を開始し、
三陸・海の博覧会終了後は「Kenji」として、
団体用を中心に「さんりくとれいん」号などの臨時列車で運用されている。
画像番号DSC 4178.JPGの画像は、
1号車 キハ58-1505
新製落成日、1968(昭和43)年2月7日、新製配置、青森、製造、日本車輌
改造施行日、1973(昭和48)年10月1日、転属配置先、秋田
改造施行日、1985(昭和60)年3月14日、転属配置先、盛岡
改造施行日、1992(平成4)年3月11日、改造工、土崎工場
廃車日、2018(平成30)年9月26日、盛岡
画像番号DSC 4174.JPGの画像は、
2号車 キハ28-2010
製造時形式車番、キハ28-10、
新製落成日、1961(昭和36)年6月8日、新製配置、広島、製造、東急車輌
転属日、1965(昭和40)年9月30日、転属配置先、長崎
転属日、1968(昭和43)年10月1日、転属配置先、小郡
一代目改造後、キハ28-2010、
冷房化+4DQ(4VK)電源装置搭載改造
改造施行日、1970(昭和45)年6月15日、改造工、幡生工場
転属日、1980(昭和55)年10月23日、転属配置先、新潟
転属日、1991(平成3)年7月7日、転属配置先、盛岡
二代目改造後、キロ29-505、
改造施行日、1987(昭和62)年3月25日、改造工、新津車両所
改番後、キハ28-2010、
改番、1992(平成4)年3月11日、
廃車日、2018(平成30)年9月26日、盛岡
画像番号DSC 4170.JPGの画像は、
3号車 キハ58-650
新製落成日、1965(昭和40)年6月18日、新製配置、千葉、製造、富士重工
改造後、キロ59-509、
改造施行日、1978(昭和53)年3月25日、改造工、新津車両所
転属日、1991(平成3)年7月7日、転属配置先、盛岡
改番後、キハ58-650、
改番、1992(平成4)年3月11日、
廃車日、2018(平成30)年9月26日、盛岡
1号車 キハ58 1505(追加改造車)
展望室・一般席(2列-2列、)
トイレは1号車と3号車のデッキ寄り
洋式トイレと小さな洗面台を設置
運転室寄りは、ハイデッカーの展望席。
2+2で4列、合計12席
定員46名。
2号車 キハ28 2010
一般席(2列-1列、)
車両半分は「コミュニケーションルーム」と称するフリースペース
定員32名。
3号車 キハ58 650
展望室・一般席(2列-2列、)
冷房装置は、展望室の直後にAU76A形集中式冷房装置1基を設置し、
後位側はベース車両に設置されていた。
AU13A形分散式冷房装置3基をそのまま使用。
サニタリースペースは、洗面台と洋式トイレを設置。
2+2で4列、合計12席
運転室寄りは、ハイデッカーの展望席。
定員52名。
リゾートみのり
「リゾートみのり」は、2008年10月から12月にかけて開催された
「仙台・宮城デスティネーションキャンペーン」の一環として、
郡山総合車両センターで改造製作された。
2008年10月1日より「リゾートみのり」として、
仙台駅 - 新庄駅間(東北本線・陸羽東線経由)で運転を開始した。
「みのり」の愛称は一般公募により決定したもので、
陸羽東線のキーワードである「稲穂」=実りある収穫、
「温泉」=実りあるひととき、「紅葉」=実りの秋、
そして「実り多い旅にしてほしい」という意味が込められている。
東京方先頭1号車から順にキハ48 550+キハ48 549+キハ48 546の普通車3両編成で、
車両番号は改造前と変わっていない。
画像番号DSC 4565.JPGの画像は、
1号車 キハ48-550
新製落成日、1979(昭和54)年7月7日、新製配置、郡山、製造、富士重工
転属日、1993(平成5)年12月1日、転属配置先、会津若松
みのり化改造、
改造施行日、2008(平成20)年9月8日、改造工、郡山総車セ
転属日、2008(平成20)年9月8日、転属配置先、小牛田
廃車日、2020(令和2)年8月12日、小牛田
画像番号DSC 4561.JPGの画像は、
2号車 キハ48-549
新製落成日、1981(昭和56)年2月10日、新製配置、郡山、製造、富士重工
転属日、1993(平成5)年12月1日、転属配置先、会津若松
みのり化改造、
改造施行日、2008(平成20)年9月8日、改造工、郡山総車セ
転属日、2008(平成20)年9月8日、転属配置先、小牛田
廃車日、2020(令和2)年8月12日、小牛田
画像番号DSC 4557.JPGの画像は、
3号車 キハ48-546
新製落成日、1980(昭和55)年7月24日 新製配置、小牛田、製造、富士重工
転属日、1998(平成10)年12月21日、転属配置先、会津若松
みのり化改造、
改造施行日、2008(平成20)年9月8日、改造工、郡山総車セ
転属日、2008(平成20)年9月8日、転属配置先、小牛田
廃車日、2020(令和2)年8月12日、小牛田
1号車 キハ48 550
基本的には3号車と同様である。
前位寄りの出入台が廃止され、
展望スペースが設置されている。
機関はDMF14HZC
3位側に車椅子対応便所、
4位側に男子用小便所と洗面所が設置されている。
側出入口横には「みのり」のロゴを配し、
LED式の行先表示器が設けられた。
定員34名。
2号車 キハ48 549
3両編成時の中間車で、
写真のように2両編成での運転などに対応するため、
種車の運転台は存置されている。
出入台は種車の位置のまま前後位にあり、
客室内前位寄りにはイベントスペースが設置されている。
種車の便所は撤去されている。
定員36名
3号車 キハ48 546
前位寄りの出入台が廃止され、
展望スペースが設置されている。
機関はDMF14HZC
3位側に車椅子対応便所、
4位側に男子用小便所と洗面所が設置されている。
側出入口横には「みのり」のロゴを配し、
LED式の行先表示器が設けられた。
定員34名。