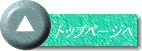画像をクリックすると拡大します。
解説は画像の下の欄から掲載してあります。
[検測車・事業用車部門]
国鉄143系電車
本国有鉄道(国鉄)が1977年から1982年にかけて導入した
直流の事業・郵便・荷物用電車群である。
クモヤ143形
クモヤ143形は、首都圏地区のATC化に対応し、
また老朽化したクモヤ90形の代替として、
1977年に登場した直流用事業用車(牽引車)である。
番台区分は出自の違いにより、新製車の0番台、
クモニ143形から編入された50番台の2区分が存在する。
画像番号FH0047.JPGの画像は、
クモヤ143−8
新製落成日、1978(昭和53)年3月1日、新製配置、品川、製造、近畿車輌
転属日、1985(昭和60)年12月12日、転属配置先、山手
転属日、2004(平成16)年6月1日、転属配置先、東総車セ
廃車日、2023(令和5)年4月4日、東総車セ
クモヤ143形(Mzc')
室内配置は前位乗務員室後部からATC機器室・ATS等の機器室、
その後部に機材室、控室、後位乗務員室の配置
控室には片側あたり6人分のロングシートが両面に設置
集電装置パンタグラフはPS23形2基搭載
主制御器は新設計のCS44形、主幹制御器は力行5ノッチ、抑速5ノッチのMC53形
空気圧縮機MH113B-C2000M形
主抵抗器はMR133形、発電ブレーキ・抑速ブレーキが装備
電動発電機はは耐雪構造強化型のMH94B-DM58B形(70kVA)
主電動機はMT57A(100kW)、台車はDT21C。
国鉄145系電車
日本国有鉄道(国鉄)が101系電車の改造名義で製作した
単独電動車 (1M) 方式の直流用新性能電車である。
クモヤ145形100番台
国鉄が1980年(昭和55年)から製造した直流電化区間用の牽引車である。
主に車両基地内の入換やマヤ34形客車(軌道試験車)の牽引(マヤ検)に使用される。
救援車として使用できるように車体中央部に救援機材積載用のスペースを設け、
天井にはクレーンが設置されている。
それに伴い側窓と側扉の配置が変更され、
新たに機器搬入口が設けられた。
1982年(昭和57年)から1986年にかけて、26両が改造製作された。
クモヤ145-107はパンタグラフが霜切り用として回路が独立しており、
避雷器もパンタグラフごとに1台ずつ搭載された。
画像番号FH0042.JPGの画像は、
クモヤ145−107
製造時形式車番、クモハ101-98
新製落成日、1961(昭和36)年8月、新製配置、武蔵小金井、製造、日本車輌
転属日、1966(昭和41)年12月12日、転属配置先、豊田
転属日、1981(昭和56)年9月1日、転属配置先、武蔵小金井
改造後、クモヤ145-107
改造施行日、1985(昭和60)年11月2日、改造工、郡山工場
転属日、1982(昭和57)年11月16日、転属配置先、新前橋
廃車日、2020(令和2)年2月21日、高崎
クモヤ145形(Mzc')
室内配置は前位乗務員室後部からATC機器室・ATS等の機器室、
その後部に機材室、控室、後位乗務員室の配置
控室には片側あたり6人分のロングシートが両面に設置
集電装置パンタグラフはPS23形2基搭載
主制御器は発電ブレーキなし・ノッチ戻し付きのCS50形、
主幹制御器は力行5ノッチ、抑速5ノッチのMC53形
主抵抗器はMR145A形、発電ブレーキ無し・抑速ブレーキが装備
電動発電機はMH94A-DM58A形(70kVA)
電動空気圧縮機はMH113B-C2000MA形
主電動機はMT46A形(100kW)、台車はDT21形。
国鉄443系電車
日本国有鉄道(国鉄)が1975年(昭和50年)に製造した、
電気検測用の事業用交流直流両用電車である。
架線検測を行うクモヤ443形と、
信号検測を行うクモヤ442形の2両編成で構成される。
2編成4両が近畿車輛で製造された。
外観は同時期に製造されたキヤ191系に準じており、
当時の特急形電車の前頭部と、急行形電車並の車体を組み合わせた形態で、
側窓は上下2段のユニット窓(外ハメ式)となっている。
車体塗色は当時の交直流電車の標準色であった
ピンク(赤13号)とクリーム(クリーム4号)の塗り分けとなっている。
前面には警戒色の目的でクリーム色が配されているが、
特急形の矢羽模様同様、側面まで回りこんでいる。
様々な運用をこなす必要から、両端には双頭連結器が備えられている。
架線については、検測室内パネル上の切替スイッチにより、
直流、交流50Hz、同60Hzの計測が可能であり、
また測定室内の天井部には速度計を備え、測定中の速度確認が可能である。
画像番号FH0169.JPGの画像は、
クモヤ442−1
新製落成日、1975(昭和50)年6月24日、新製配置、勝田、製造、近畿車輌
廃車日、2003(平成15)年7月11日、勝田
画像番号FH0170.JPGの画像は、
クモヤ443−1
新製落成日、1975(昭和50)年6月24日、新製配置、勝田、製造、近畿車輌
廃車日、2003(平成15)年7月11日、勝田
クモヤ443形(Mzc')
架線関係の検測車で、
屋根上に測定用パンタグラフ(前位PS910、後位PS909)を搭載、
観測ドームや照明装置が設置されている。
室内は両端(1位側および4位側)にクーラー室(床置形のAU41冷房装置を2基ずつ設置)、
高圧室(2位側および3位側)が設置されている。
中央部には前位側からサーボ機構、観測台、データレコーダーなどが設置、
2・4位側に機器搬入用の扉を備えている。
主電動機はMT54D、台車はDT32I。
クモヤ442形(Mzc')
信号関係の検測車で、
主変圧器・主整流器、交流機器
集電用パンタグラフとAU13EN冷房装置を3基搭載
室内は前位側に電源室と物置を設置、
中央部に測定盤や会議室、機器室等を有し、
出入台の後部には3位側に便所、
4位側に洗面室が設置。
また、2・4位側には機器搬入口が設けられている。
MG・CPを装備。
主電動機はMT54D、台車はDT32I。
455系訓練車クヤ455-1
1991年にJR東日本では、
乗務員を対象に定期的に行う異常時の取扱いや応急処置等の教育訓練のため、
保留車を活用して訓練用編成を整備することになった。
455系ではクハ455形をベースにし、
室内は座席を一部撤去、
テーブルとパイプ椅子を持込みミーティングルームとし、
備品収納用ロッカーや視聴覚教育用モニタ、
ビデオを搭載したクヤ455形に改造。
クモハ455・モハ454-1と編成を組み、
塗装は交直流急行色に白帯と「訓練車」の表記が入れられていた。
2006年11月14日に編成に組まれていた
クモハ455-1の鉄道博物館展示準備を兼ねて、
郡山総合車両センターへ廃車回送されて形式消滅した。
画像番号FH0152.JPGの画像は、
クヤ455−1(訓練車)
製造時形式車番、クハ451-26
新製落成日、1964(昭和39)年1月28日、新製配置、仙台、製造、日立製作所
一代目改造後、クハ455-203、
改造施行日、1979(昭和54)年6月26日、改造後配置、仙台、改造工、郡山工場
二代目改造後、クヤ455-1、
改造施行日、1991(平成3)年3月29日、改造後配置、仙台、改造工、郡山工場
廃車日、2006(平成18)年12月25日、仙台
クヤ455-1(Tzc')
室内は座席を一部撤去、
テーブルとパイプ椅子を持込みミーティングルームとし、
備品収納用ロッカーや視聴覚教育用モニタ、ビデオを搭載した
キヤ28 1(訓練車)
1991年にJR東日本では、
乗務員を対象に定期的に行う異常時の取り扱いや
応急処置等の教育訓練のためK訓練用編成です。
余剰になった103系・113系・115系・455系・485系などの電車で改造を行ったが、
同様に気動車でも、本系列からも盛岡車両センター所属車への改造が、
土崎工場で行われた。
車内は一部の座席が撤去され、備品収納用ロッカーやテーブル、
視聴覚教育用モニタ、ビデオを搭載するためのラックが装備されている。
外観上は白線2本と「訓練車」の表記が追加され、
一般車とは区別されている。
改造後も盛岡車両センターに配属され、
キハ58 75と常にユニットを組む形で運用されたが、
2008年11月に廃車され形式消滅した。
(キハ28 102→)キハ28 2102→キヤ28 1
画像番号IMG 1687.JPGの画像は、
キヤ28 1(訓練車)
製造時形式車番、キハ28 102
新製落成日、1962(昭和37)年6月21日、新製配置、盛岡、製造、帝国車輌
冷房改造後、キハ28 2102
改造施行日、1974(昭和49)年4月20日、改造後配置、盛岡、改造工、郡山工場
改造後、キヤ28 1
改造施行日、1991(平成3)年1月23日、改造後配置、盛岡、改造工、盛岡工場
廃車日、2008(平成20)年4月8日、盛岡
キヤ28-1
一部座席撤去・備品収納用ロッカーならびにテーブルの設置、
視聴覚教育用モニタとビデオ搭載用ラックの装備など主に車内の改造を施工。
モヤ115−6(訓練車)
乗務員が車輌故障など異常時の取扱を訓練するための巡回訓練用車輌として、
1995(平成7)年にモハ115-103から改造された。
車内はミーティング用のスペースを確保するため座席が一部撤去されたほか、
AV機器や資料用のロッカーが設置されている。
画像番号IMGP1166.JPGの画像は、
モヤ115−6
製造時形式車番、モハ115-103
新製落成日、1967(昭和42)年5月31日、新製配置、小山、製造、川崎車両
改造後、モヤ115-6
改造施行日、1995(平成7)年2月6日、改造工、大宮工場
廃車日、2008(平成26)年1月28日、豊田
モヤ115-6(Mz)
モハ114-827とユニットを組む
1995(平成7)年にモハ115-103から改造。
車内はミーティング用のスペースを確保するため座席が一部撤去されたほか、
AV機器や資料用のロッカーが設置。
キヤ191系(検測車)
日本国有鉄道が製造し、東日本旅客鉄道および西日本旅客鉄道に継承、
在籍した架線・信号検測用の試験気動車である。
1974年から1976年までの各年に1編成ずつ、
計3編成6両が富士重工業で製造された。
画像番号FH0154.JPGの画像は、
キヤ190−2
新製落成日、1975(昭和50)年2月6日、新製配置、秋田、製造、富士重工業
廃車日、2003(平成15)年7月11日、秋田
キヤ190-2
キヤ191-2とペアを組む車両で、
架線の検測車、屋上に測定用のパンタグラフを2基搭載、観測用の出窓を設置。
車内は両端に高圧室と床置形冷房装置を設け、中央が測定室となり、
側面にも線路状況観測用の出窓を設けた。
側窓は固定式。
画像番号FH0155.JPGの画像は、
キヤ191−2
新製落成日、1975(昭和50)年2月6日、新製配置、秋田、製造、富士重工業
廃車日、2003(平成15)年7月11日、秋田
キヤ191-2
キヤ190-2とペアを組む車両で、
は信号検測車、床下に測定用受電器・車上子を取付、電源用発電装置を搭載。
その関係で床下にスペースがなく、運転室後部に機器室を設けて機関冷却装置を設置。
車内はその他に会議室、測定室、電源室を設け、後位側に便・洗面所を設置。
キヤ190形と異なり、冷房装置は屋根上に3基搭載している。
側窓は固定式。
クモヤ441形交直流牽引電車
1976年〜1978年に72系モハ72より改造された交直流牽引電車である。
「牽引車」とは「工場や電車区などで修理車や入換用車輌を牽引したり、
自走装置のない車両や中間電動車などの試運転や移動に使用する」
(国鉄電車ガイドブック・旧性能電車編(下)より抜粋)という、
旅客扱いを行わない業務用の事業用車である。
本形式が改造された1970年代半ばでは、
大抵が一線を退いた旧型国電の改造で賄っていたため、
本形式も旧型通勤電車の72系モハ72形より改造されたものである。
画像番号FH1000.JPGの画像は、
クモヤ441−3
製造時形式車番、モハ72852 1956年度2次車
新製落成日、1956(昭和31)年12月19日、新製配置、中野、製造、日立笠戸製造
改造後、クモヤ441-3
改造施行日、1977(昭和52)年5月26日、配置、仙台、改造工、郡山工場
廃車日、2003(平成15)年7月10日、仙台
クモヤ441形(Mzc')
車内中央部に機器室を設け、主変圧器・抵抗器・CP・70kVA MGなどを搭載。
台車は種車のDT20を流用。
集電装置パンタグラフはPS16形1基搭載
主制御器は電動カム軸式のCS10
主電動機はMT40B(端子電圧750 V時定格出力142 kW)
自車の他2両分の電源供給可能な70kVA MGを搭載
クモヤ743形交流牽引電車
東日本旅客鉄道(JR東日本)がかつて所有した事業用交流牽引電車である。
奥羽本線福島 - 山形間は、1992年(平成4年)7月1日開業で、
山形新幹線による新在直通運転が開始されたが、
それに伴う軌間の狭軌(1,067mm)→標準軌(1,435mm)への
改軌工事は1991年11月5日に完了。同区間の普通列車は山形線の愛称で、
充当車両には東北本線で運用されていた719系電車を標準軌仕様とした5000番台が投入され、
山形運転所(→山形電車区→山形車両センター→現・山形新幹線車両センター)へ配置された。
当初719系5000番台の定期検査は仙台総合車両所(現・新幹線総合車両センター)で、
実施を計画されたが、同番台区分は東北新幹線区間の保安装置は未搭載の上に、
架線電圧交流50Hz20kVのみ対応であることから、
同25kVの福島以北を自力走行できないために牽引車が必要となり、
クモヤ143形直流職用車を種車に改造施工で落成したのが本形式である。
なお本形式は普通鉄道構造規則による確認のほかに、
新幹線鉄道構造規則に基づいた新幹線用交流牽引車で、
新幹線車両としての確認も取得した新幹線区間で、
自力運転が可能な唯一の在来線用電車であった。
画像番号FH1001.JPGの画像は、
クモヤ743−1
製造時形式車番、クモヤ143-3
新製落成日、1977(昭和52)年3月14日、新製配置、品川、製造、日立製作所
改造後、クモヤ743-1
改造施行日、1992(平成16)年6月23日、新製配置、山形、改造工、仙台総合
廃車日、2014(平成26)年11月8日、山形
クモヤ743形(Mzc')
台車を標準軌対応のDT60形へ換装。
制御・制動装置は719系に準拠したシステム
集電装置パンタグラフは下枠交差型パンタグラフへ交換
主電動機はMT61
保安装置は山形線用ATS-P・東北新幹線用ATC-2を搭載
東北新幹線用LCX列車無線を搭載
強化型スカートへ換装
719系に対応した電気連結器を装着
マヤ34形客車
日本国有鉄道(国鉄)が製造した軌道検測用の事業用客車である。
用途の特殊性から現場および鉄道ファンの間では単にマヤまたはマヤ車、
本形式を使用した検測列車をマヤ検と呼ぶこともある。
1959年(昭和34年)に製造された。
屋根の形状が10系客車と同様の深い丸屋根で、冷房装置は未搭載。
片方の妻面には埋め込み式の前照灯2灯を装備し、
なおかつその妻面の窓3枚(うち1枚は貫通扉窓)が非常に大きい縦長である。
観測用出窓の傍に(鉄道車両としては珍しく)丸窓がある。
以上のような特徴ある外観をしている。
また、同系列としては唯一、新製時は蒸気暖房のみを装備していた。
塗装はぶどう色2号の地色に黄1号帯の塗装であったが、
のちに青15号の地に側面中央部、
上部に黄1号の帯を1本ずつ配した塗装に塗り替えられた。
1967年(昭和42年)に北海道用として耐寒耐雪改造
(原番号+500、電気暖房設置併施で+2000)を施しマヤ34 2501へ改番された。
分割民営化直前の1987年(昭和62年)に廃車。
マヤ34 2002 - 2007
ヨンサントオに向けて1965年(昭和40年) - 1967年(昭和42年)に増備されたグループ。
外板色は製造当初から青15号となった。
また、これ以降に製造された本形式は電気暖房を新製時から装備とした。
以下の点で1から設計変更が行われた。
車体長の延長と台車をTR202A形に変更。
台車間隔は変更できないため、両端のオーバーハングが伸びた。
平屋根となりAU12形分散式冷房装置3基を搭載。
冷房化により発電セットの電源容量強化が行なわれた。
妻面の前照灯は廃止、妻面の大型窓も縮小され、
電源装置室の拡大と合わせて窓配置も変更された。
画像番号IMG 0362.JPGの画像は、
マヤ34−2004
新製落成日、1966(昭和41)年9月30日、新製配置、尾久、製造、日立製作所笠戸
廃車日、2015(平成18)年8月11日、尾久
マヤ34-2004
屋根上にAU13クーラーを4個搭載
車内は測定室のほか寝室も設置
台車はTR202A形を3基装備する。
各種検測・記録装置や冷房装置等の電源としてディーゼル発電セットを車端部に搭載
双頭連結器を装備する。
オヤ12 1
2002年(平成14年)、JR東日本土崎工場
(現在の秋田総合車両センター)で改造製作された、
動態保存蒸気機関車回送随伴用事業用車である。
スハフ12 158を種車として1両が改造され、
オヤ12 1と改番された。
同社の高崎車両センターに所属するD51 498や新津運輸区に所属するC57 180をはじめ、
2011年に復活した高崎車両センター所属のC61 20、
さらに秩父鉄道のC58 363を、イベント運転や点検による車両基地への入出場などで、
目的地まで回送する際の、また検査後に実施する本線試運転を行う際の、
機関車の状態の把握や保安機器の搭載などを目的としている。
外観に変化はないが、車内は一部座席を撤去し、
保安機器などを搭載するスペースとしたほか、
蒸気機関車の状態を把握するための装置が追加されている。
2012年(平成24年)現在は、高崎車両センターに在籍。
画像番号DSC 4798.JPGの画像は、
オヤ12 1
製造時形式車番、スハフ12 158
新製落製日、1978(昭和53)年11月24日、新製配置、尾久、製造、富士重工
転属日、1994(平成6)年12月3日、転属配置先、高崎
改番後、オヤ12 1
施行日、2002(平成14)年5月17日、改番、秋田総車セ、形式番号変更
蒸気機関車伴走車(オヤ12形)
蒸気機関車伴走車で、
外観に変化はないが、車内は一部座席を撤去し、
保安機器などを搭載するスペースとしたほか、
蒸気機関車の状態を把握するための装置が追加されている。
マヤ50−5001
オヤ31形と異なり物理的に接触させるのではなく、
光を照射し、CCDカメラにより撮影解析して、
測定する測定器を搭載しており、「光オイラン」とよばれる。
当初はスヤ50形と称したが、2003年(平成15年)に、
「East i」シリーズ(E491系「East i-E」・キヤE193系「East i-D」)との
併結改造を行った際に重量が増加したため、現在の形式になっている。
画像番号DSC 4800.JPGの画像は、
マヤ50−5001
製造時形式車番、オハフ50 2301
新製落成日、1980(昭和55)年9月29日、新製配置、酒田、製造、新潟鉄工所
一代目改造後、スヤ50-5001 限界測定車化改造
改造施行日、1995(平成7)年11月16日、改造後配置、仙台、改造工、大宮工場
二代目改造後、マヤ50 5001
改造施行日、2003(平成15)年7月1日、改造後配置、仙台、改造工、大宮工場
マヤ50-5001
2003(平成15)年に新形の試験車E491系、
キヤE193系との併結改造が行われて重量が増加してマヤ50形に形式変更されて、
スヤ50形は形式消滅した。
E491系、キヤE193系との併結に伴い、
1・3位側に高圧用電気連結器、2・4位側に制御用電気連結器が追加された。
連結器は妻面にセン受箱を設置する形で設けられ、尾灯は妻窓上に移設された。
床下のスペースがないことから、
引通し線は妻外板部と屋根上との間に設けたダクトに敷設された。
ブレーキシステムについても改造され、
電気指令式空気ブレーキ対応として床下に読替用のブレーキ制御装置、
直通予備ブレーキ、耐雪ブレーキが追加されている。
測定機器についても強化が図られ、
床下および屋根上への画像記録用カメラ増設等が行われている。
車体は二段窓のうち片側1ヵ所ずつがルーバーに変更された。
車体塗色はE491系、キヤE193系に合わせて白地に赤帯に変更された。
カヤ27形
2000年(平成12年)に1両 (501) がJR東日本大宮工場で改造された。
24系客車の電源車カニ24形 (510)から改造された。
カハフE26形の予備として使用する電源車である。
発電設備を更新したほか、種車の荷物室を車内販売などに使用する業務用室に変更した。
客室としての設備はない。
外部塗色は他車と同様のシルバーメタリックに5本帯を配したもので、
"CASSIOPEIA"のロゴマークを側面に、
列車愛称を表示した円形のテールサインを車掌室側の中央に設ける。
電気指令ブレーキの読替機能は装備せず、
本形式を使用するときのブレーキ装置はCL方式(応荷重式自動ブレーキ)となる。
画像番号DSC 8155.JPGの画像は、
カヤ27−501
製造時形式車番、カニ24-113、
新製落成日、1980(昭和55)年9月8日、新製配置、向日町、製造、新潟鉄工所
転属日、1982(昭和57)年10月、転属配置先、秋田
転属日、1988(昭和63)年、転属配置先、青森
一代目改造後、カニ24-510、
改造施行日、1990(平成2)年10月9日、改造工、土崎工場
発電装置更新工事
改造施行日、1993(平成5)年12月2日、改造工、大宮工場
二代目改造後、カヤ27-501、
改造施行日、2000(平成12)年2月25日、改造工、大宮工場
廃車日、2025(令和7)年9月16日、尾久
カヤ27-501
カシオペアの予備電源車である。
国鉄民営化後、北斗星用に改造されたカニ24を再改造の上、2000年に登場した。
電源設備はそのまま、車販準備室などを備えている。